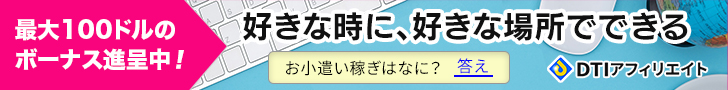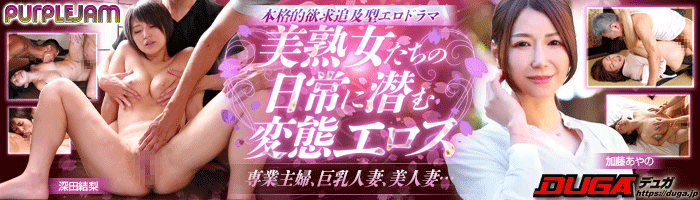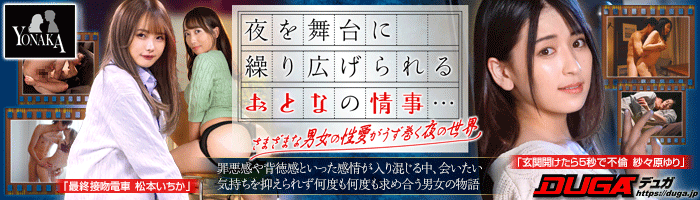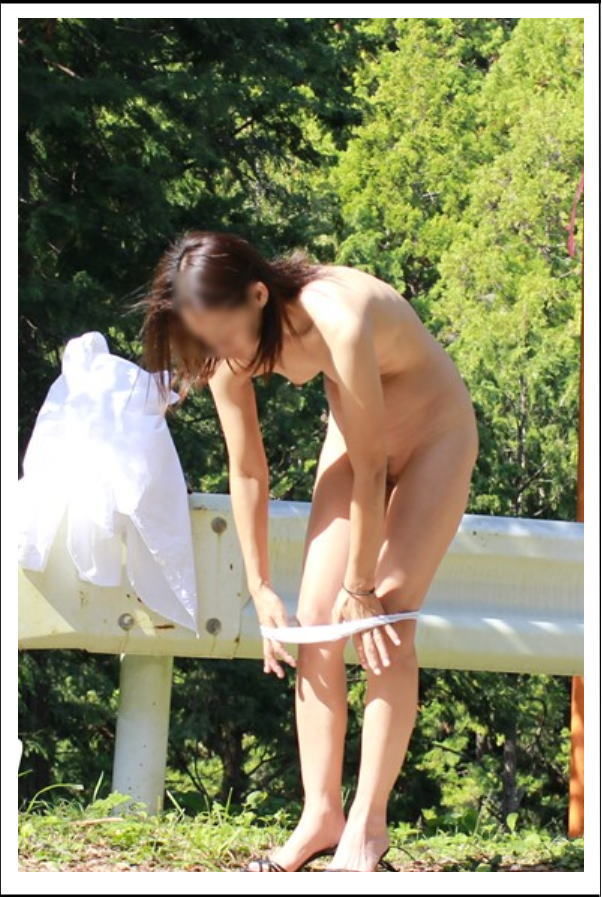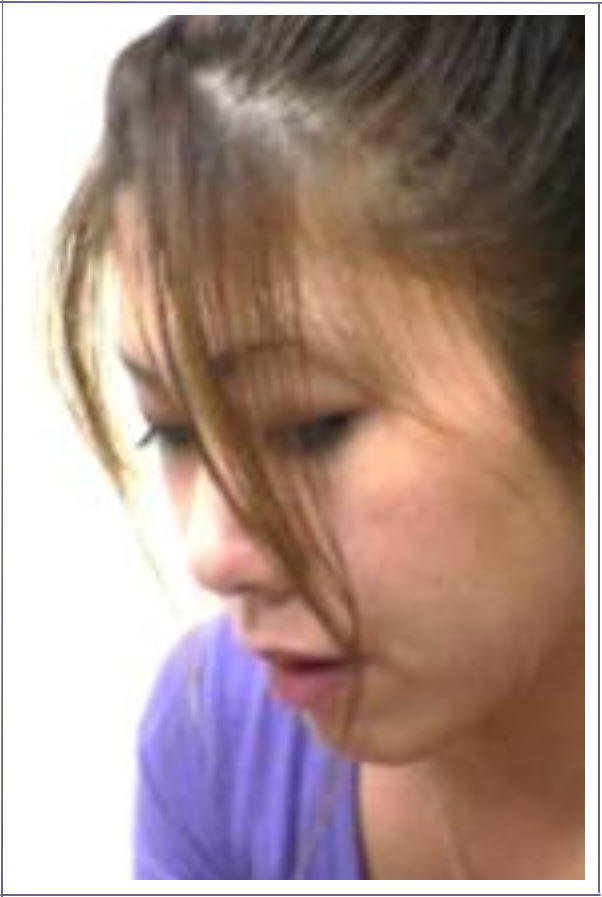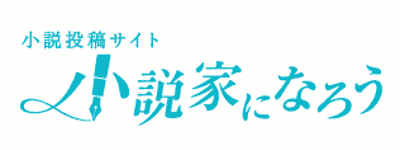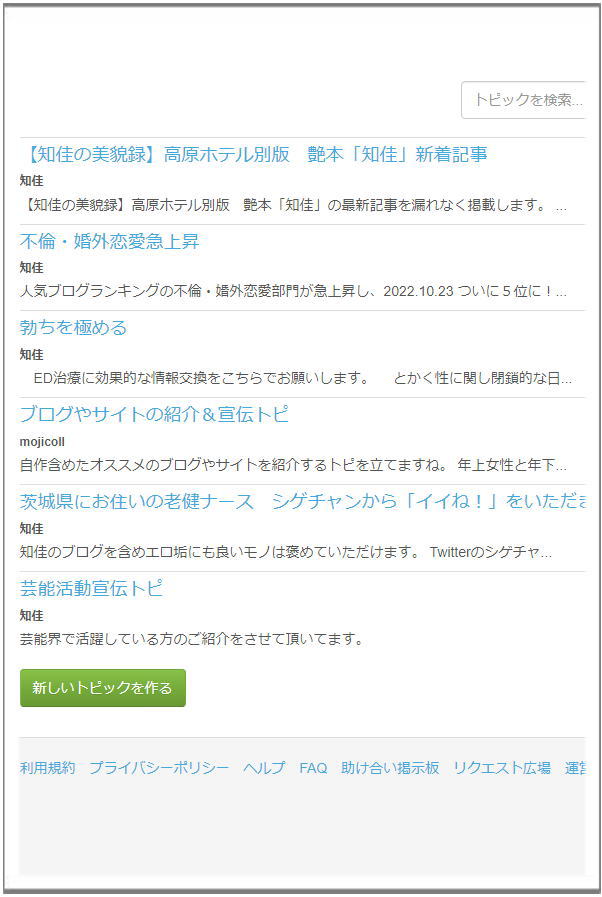嬲り合い
 とかく庄衛門はマメだった。
とかく庄衛門はマメだった。空模様が悪い時とか、用事があって遠方に出かけなければならない時にでもなければ、何処からともなくおカネの家に、仕事先に亭主の留守を見計らって顔を出した。
おカネに対し、世間話をしたがった。
興が乗ると、おカネがハッとするほど顔を近づけ、眼の奥を窺う。
余りに近さに、おカネが身動きできないでいると、胸元から立ち上がる乳房の臭いを嗅ごうとした。
おカネに乳房の、丁度覗き見えるところは 淡く血管が浮き出て、まるで搗きたての餅のようで、それだけで男心をくすぐった。
しげしげと覗き見る庄衛門の横顔に、それとわかるほど深い吐息を吹きかけるおカネ。
胸いっぱいおカネの香りを嗅ぐと庄衛門は、
「よっこらしょ」 掛け声もろとも立ち上がろうとする。
よろめいたように見せかけ、思わずその庄衛門に手を差し伸べようとするその拍子を狙いすまし、おカネの太腿に手を置き、姿勢を元に戻した。
瞬時だったが庄衛門の指先は、しっかりと女心を探った。
「えぇっ~と・・・ああそうか・・・」
謎めいた言葉を残し、庄衛門はついっと茶の席を立って縁側から遠ざかっってしまった。
気になったのはおカネのほうだった。
慌てて後を追う。
そそくさと庭先を横切って家に通ずる坂を下っていく庄衛門。
下った先をついっと横に反れた。
おカネが後追いするのを見届けると、石垣に向かって悠然と放つ態勢をとったのである。
おカネのためだった。
胸元の香りを嗅ぎ、欲しくてたまらなくなっているんだということを屹立を捧げることで伝えた。
放出しようにも、先端から出てくるのは我慢の限界を超え滲み出る涙だった。
おカネはその様子を、石垣で身を隠すようにしながら覗き見た。
庄衛門は、褌の隙間から引き出した屹立を おカネのためにビクンビクンと脈打って見せた。
視線が一点に集中するのがわかった。
おずおずと手を挿し込んで、潤みをまさぐるおカネ。
「天網恢恢疎にして漏らさず・・・」
持念
庄衛門は独り言のようにつぶやき、欲情するおカネから目を逸らせてやった。
〈 いつぞや、舐めあげてやっとことを忘れておらにゃあ、儂の棹に震い付いてくるはずじゃ 〉
オナゴの反応というものは、セク男連中より鈍い。
だが、ツボにはまれば抜け出すことなど容易にできない。
着物の端をたくし上げ、指が収まるところに収まっている。
鎮めようと蠢かすまでの辛抱だった。
「・・・あああ・・・ふん、あっ・・・」
耳を澄まさなければ聞き取れないほどの小さな声が漏れだした。
おカネが自らの指で逝き始めていた。
庄衛門は、おカネに気づかれないよう距離を詰めてやった。
空いた左手が屹立を欲しがって衣服の裾を掴み身悶えている風に見えたからだった。
そっとにじり寄った。
やがて、庄衛門とおカネは身体同士が触れ合うほどの距離になった。
ワナワナと小刻みに身体を震わせ、庄衛門の屹立に見入るおカネの、忍ばせたアソコの、その指の間からシズクが流れ落ち、太腿を濡らし陽光に照らされ光っている。
「可愛い奴じゃ」
庄衛門はおカネの額に唇を這わすと、右手でそっとおカネの手を取り、屹立に添えてやった。
周囲から決して見えないよう、右肩でおカネの左肩を押すように、身体ごと石垣に押し付けるようにしながら、その肉棒の味を伝えてやった。
遠慮がちに掌で包み込むおカネ。
愛おしさに庄衛門は、おカネの掌の中の屹立をおカネのために蠢かせてやった。
おカネの目にも、ハッキリとアソコに挿し込む時の動作に見せかけ腰を振って蠢かした。
おカネの頬が朱に染まった。
念じ続けたアソコへの挿し込みを合意してくれた証拠だった。
「確かめ合う日は・・・近い?」
「おお!!そうじゃ!!そのとおりじゃ」
ここでと言いかけたおカネを目で制した。
誰が見ているとも限らない庭先の、石垣の根元で押さえ込むわけにもいかなかった。
暫くの間は自慰で済ませていたおカネだったが、屹立の先端からいよいよもって流れ落ち始めた涙と、庄衛門の息苦しそうな表情にたまりかね、自らの意志で庄衛門をしごきはじめた。
しとどに濡れそぼった指をアソコから引き抜くと、屹立を握りしめ、そのシルを塗りたくってしごいた。
庄衛門は歯をくいしばって耐えた。
気のすむまで嬲らせてやるつもりだった。
先端から滲み出る我慢汁を愛おしそうに見つめるおカネ。
ともすればくじけそうになるおカネの腰を、庄衛門は尻に肉を鷲掴みにして支えてやった。
柔らかい肉だったが、それでいて弾力があった。
指先に伝わる感触で、おカネのアソコの中まで差し計ったように見通せた。
庄衛門が耐えがたくなって力むと、つい おカネを引き寄せてしまうことになる。
互いの距離が詰まって、おカネの唇が庄衛門の屹立を捉えざるをえなくなっていた。
おカネの吐く熱い吐息を感じたと思ったら、ぬめぬめとした唇で先端が捉えられていた。
突き抜けるような快感が庄衛門の脳天を突っ切った。
耐えがたい興奮の中、庄衛門は冷徹におカネの様子を探った。
指先がおカネのアソコに、もう少しで差し掛かろうとしている。
時間との戦いだった。
〈 右手の指はおカネのアソコに治まり、ヒタヒタと中を嬲っている 〉 そんなことを妄想しつつ耐えた。
おカネは儂無しでは一日と持ちこたえられんようになる。 いやしてみせる。
半狂乱になって屹立にしがみつくおカネの、乳房はすっかり露わになり、もはや衣服を身に着ける意味すらなく、支える庄衛門の袴はおろか、足の甲にまでシズクを垂れ流し濡らしてしまっていた。
おカネは儂を手で嬲っていようが、儂は儂であやつの心の中を嬲っておる。
( どちらが先に泣きを入れるか、そこが勝負どころじゃ 〉
射出が始まる予兆がした。
「おカネ、好きじゃ。儂は気がふれたかもしれん」
おカネの口から嗚咽が漏れた。
- 関連記事
tag : 持念