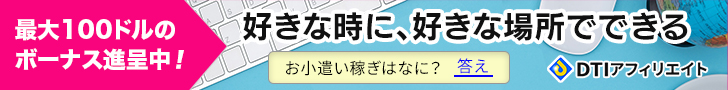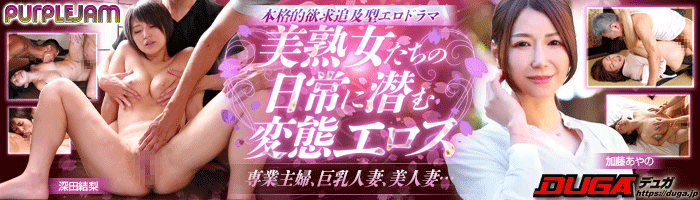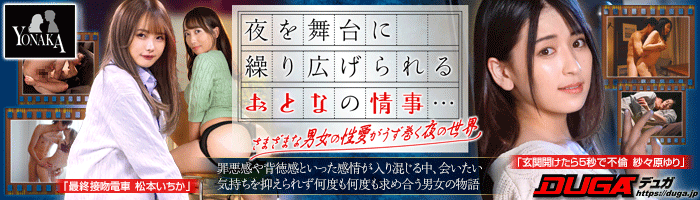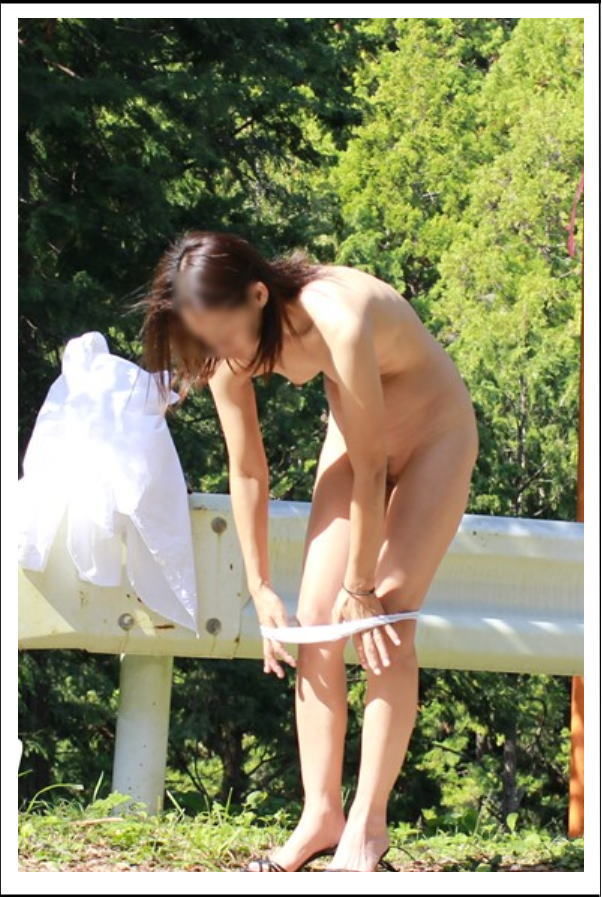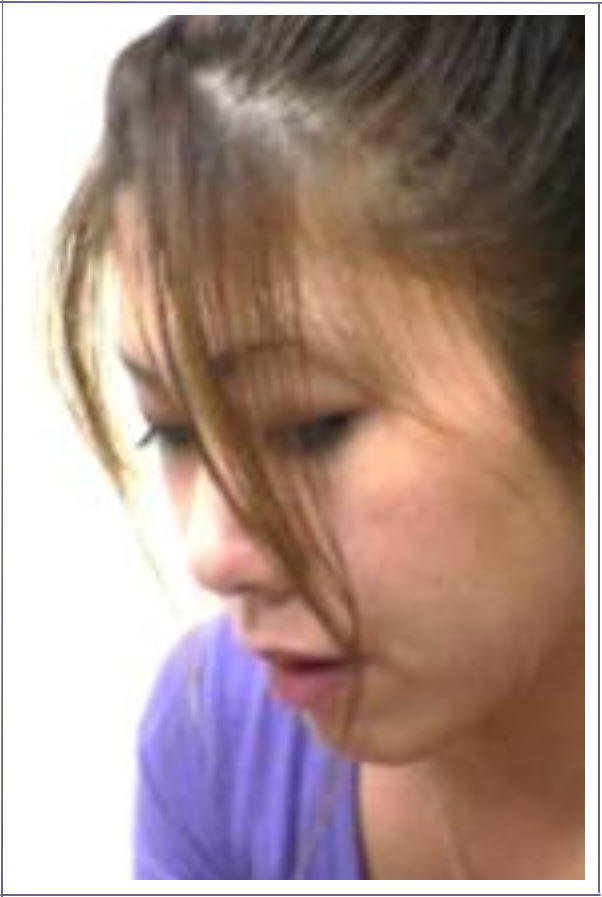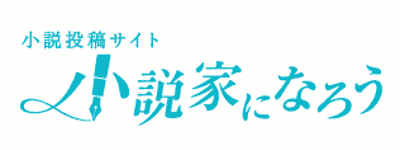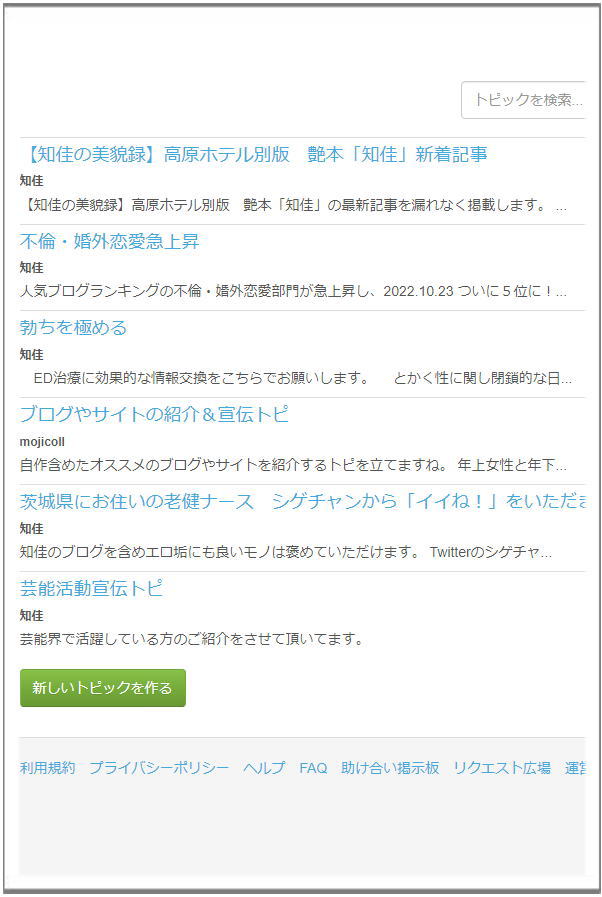疑惑 村の行事の中に穢多では参加できないものがあり、それが不幸をよんだ
夜が明けやらぬ頃起き出して、朝露が降りた畔の草を刈る。
それを持ち帰って、牛の餌とした。
田の畔の草を刈るにしても、それを無駄にしない百姓ならの工夫があったが、入沢村の百姓は畔に田から掬い上げた泥を塗り、そこに大豆を植えた。
ほんの些細なことであっても、それらがすべて食につながった。
草刈は、時として田に面する山肌を刈る。
日照時間が短い山間の村なればこそ、山すそを刈るにも、たとえ草が作る影といえども油断がならず、広範囲となる。
石高を落とすまいと必死に刈る。
作佐の女房おカネが、この山肌を刈っているとき声を荒げて近づいてくるものがいた。
本家のおツネだった。
「ちっとっ、そこはウチの土地だがね。見ちゃおらん思うて、盗っ人が」
「なにぉう!ようもようも言いがかりを。爺さんから聞かされちょった。鍬の柄丈は昔から刈り落としいうてウチに権利があるけんね」
怒鳴り声を聞き、甚六が駆けつけ、おカネの袖をつかんで引き戻した。
「ウチにゃ切り図が残っとる。あんたんとこの爺さんも了解したもんだだよ」
甚六の田の脇の畦道ですら足立家の通路だと、おツネはこの時はっきりと言い張った。
甚六はおツネに口答えを何一つ言わなかった。
「ふん、穢多(えた)めが」
すごすごと家路に向かう甚六とおカネに、聞こえよがしにおツネが罵る。
幸いに、隣近所の連中が付近にいなかったから良かったものの「穢多」を隠して暮らしてきた以上、事が知れたら村にはおれない。
返す言葉がなかった。
穢多が住み着いていることを世間が知ったら、たちまち追い出される。
「くやしい・・・」
おカネは泣いた。
おカネの生まれ育った村なら、そのようなことを聞きつければ村中総出で相手方を打ち壊しに出かけた。
「なぜ、こんな目に・・・」
いっそのこと、おカネの生まれ育った村に引っ越してはと何度も提言をした。
「いんや」
甚六は頑として首を縦に振らなかった。
おカネの村で暮らせば、それは生活が楽になるだろうが、肝心の「穢多」の身分から子供たちを解放してやることはできない。
非人ということをひた隠しに隠す村なればこそ、行く末は明るいと考えていた。
甚六一家は、ある村から夜逃げして今の地に住まいをなしている穢多だった。
町なら宗門人別帳があって放ち手形と請け手形がなければ無宿人扱いで、当然土地は手に入らない。
ところが村、事に水飲み以下の身分になると、労働苦に逃げ出し、放置された休耕田が手付かずである。
当然それは、山間にあり日照時間が極端に少なく、取れ高も限られている田ではあるが、
庄屋とすれば、安い労働者が手に入るわけで、ありがたく受け取った。
元々村とは、現代で言うところの社会村ではなく惣村(そうそん)。
法律によってまとめられた村ではなく、てんでにより集まってできた集落。
誰もが恐れおののき、崇拝するであろう神社の力、祭りごとにかまけて取り決めが行われる。
寄合で物事を取り決めると、表面的には言いながらも、その実権はあくまでも庄屋が握り差配していた。
庄屋は、奴隷制度までもうまく活用していたのである。
その穢多が、自己の地権を申し立てるということは、他にも苦しくて土地を手放し、穢多に渡ってしまったということに他ならない。
それであっても立ち合いには必ず地区の権力者が立ち会うことが、半ば義務付けられている。
だから切り図には、その割り振りが書かれている。
現代ならさしずめ地籍調査によって書かれた土地台帳付属地図に示されているが、古くは隣同士で話し合って決めた切り図が元になっている。
切り図というのは現代の土地台帳に当たる。
役所で調べてみたところで、切り図と名の付くものに正確性はない。
大半の境界線が右の土地の持ち主と左とそれとがそれぞれに言い張るものだから、二重に重なっており、たとえ草刈であったとしても、常に争いごとが絶えなかった。
何度も言うようだが、この取り決めは地区の有力者によって定められたのもであり、勢力図が塗り替えられると境界も変わる。
「いまに罰が当たる」甚六が、つぶやくように言い放ったのも、己の身分がどうのこうのというのではなく、この勢力図の塗り替えにことである。
甚六の生家は、古くは没落した武士であった。
戦に敗れ、落ちて行ったとき、畠山と名乗っていたものが、山奥に籠り、僅かの畑と獣を狩って暮らし向きを立てる間に姓は廃れ、明治新政府になって三河と名乗った。
古くは獣の皮細工をして暮らしていたので、その由来の(皮)を(河)と変えただけであったが、知識のあるものなら穢多と察しが付く。
だが、本家が三河家を認め、部落に加えたのは訳がある。
本家、足立家はもともと非人の出であった。
事の始まりは直接聞いたわけではないが、親族間の姦通をしなければならない境遇の中、沸き起こる性欲故、やめられない性癖を持つあまり、法に照らされ身分をはく奪されて非人となった。
放免となったのは、御上に大層な貢物を贈ったことによるものだが、今は確かに普通に人とはいえ、元が非人ゆえ穢多の下に格付けされる罪人である。
昔のことを持ち出されでもしたら、周辺部落に示しがつかなくなり、事は重大であるに違いなかった。
夜逃げ同然に、それまでいた村を追われ、入沢村に入植してしばらく、
幼少だった甚六は、親が語らぬことを幸いに、手伝いに駆り出されない空き間は近所中の悪ガキ共と遊びまわった。
水遊びだろうが山遊びだろうが、おおよそ同年代の男の子は一緒になって遊んだ。
そこに身分の上下はほぼなく、あるのは年嵩だけであった。
上のやることに、何でも従って遊んでもらった。
年長者が女の子に悪戯すれば、甚六も一緒になって これに従った。
親が教えてくれるもの以外、知恵のほとんどは それら先輩諸氏の入れ知恵だった。
だから、大人の男のだれそれが、大人の女の誰某とこっそりつるんでいたなどということは、直ぐに耳に入る。
恐らく、年長者の その子の親が見聞きした噂話を子供の前で披露したことで、そう思い込んでしまったんだろう。
それをまた、女の子を相手に遊びの一環として年長者がやってみせる。
甚六の、大人になってからの性教育も、おおよそそこから来ていた。
だから、一番噂に上っていた本家の性癖には気を付けたつもりだった。
運が悪かったのは、甚六は潔癖すぎて妻に対し、警戒の言葉を口に出せなかったことにある。
気の毒なことにおスヱは、本家の性癖を知らずして犯され、山に打ち捨てられ、それを恥じて死を選んでいた。
これが生粋の村育ちの女なら、その場限りの快楽だったと、簡単に忘れ去ったに違いない。
おスヱは身分違いの地区から嫁に来たのではない。
厳格に定められた「部落」から嫁いだ。
だが、その部落は戸数も入沢村とは違い、数倍あって、しかも街に向かっても開けていた。
首位を取り巻く文化圏が違った。
集落内は、向こう三軒両隣が何を考え何をしでかすかわからない人たちの集まりではなく、何事につけ穢多社会の集団として守り合う集落だった。
産まれてこの方、ひとの妻に手を出しただのということは見たことも、聞いたこともなかった。
そんな大それたことをすれば、明日の日の目を見られないとも限らない。
それだけ穢多の集団行動とは恐ろしかった。
だが、入沢村は非人部落としての表向きの顔を持たなかった。
都合の悪いことはひたすら隠し通した。
噂としておスヱが嫁ぐ前に聞かされたのは、よその村と交流したがらない過疎地にあるということぐらいだった。
入沢村の忌み嫌う噂は、おスヱが生まれ育った集落には、その時代故届かなかったのである。
そこに送り出した親ともども油断があった。
せめても、子供たちが日ごろ、どんな遊びをしているかさえ掴んでいたら悲劇は起こらなかっただろう。
村人たちの、このような忌み嫌う因襲の多くは祭りの日に限って発散される。
地蔵さんの祭りなんぞ、お堂に籠って巨大な数珠を集まったもの総出で回す大念珠繰りが行われる。
その数珠球ひとつを摘まみながら念じ、数珠が回転するたびごとに経を読み終え祈願が叶うという。
悲しいことに根が百姓、最初のうちこそ一心不乱に念じるが、「南無阿弥陀仏」のお経以外の部分を知らぬため、疲れが出始めると邪心が沸き起こる。
摘まみ廻す数珠球が、眼を閉じて廻すと妙なものに思えてくる。
触れ合う隣の人物の手が、如何にも女の手に思えてきたりもする。
お堂にはもちろん老若男女ではなく、男だけ入れる。
女はと言うと、敷地の外で声を殺して祈る。
勤行が終わり、般若湯がたんと振る舞われて帰る段になると酒の力で気が大きくなった男衆は、周囲を取り巻いていた女子衆に手を出す。
待ちかねた女子衆は祝い事だとこれを受け入れ、またひとつ因襲がつのる。
豊作の後の秋祭りでは一層盛んにこれが行われた。
男も女も、気が大きくなって後先考えないで欲の赴くままに絡んだ。
宗教がらみの因襲であったなればこそ、罪の意識も薄れ、快楽だけを貪ったものだろう。
本家の足立庄衛門なぞ、この時だけは派手に人妻の手を引いた。
人妻も、豊作の年となれば、後々なにかしらお礼を受け取ることが出来るものと、喜んで身体を開いた。
食えなくなったからと、山を越え温泉宿に酌婦・飯盛りに出かけ、そこで見知らぬ男に操を売るより、よっぽどましだったからである。
近親相姦の恐ろしさは、こんこんと親から教えられていた。
だからこそ、湯宿で見知らぬ男相手に孕んだとしても、黙っていれば健康な子供が産める。
知ってはいたが、女たちにとって、それは屈辱でしかなかった。
普段から、幾度となく言い寄られ、機が熟して絡み合う、本家のやり方が性に合っていたからだった。
甚六も本来ならこの祭りに参加できる。
ところが、世のしきたりでは非人は普通人に戻れば参加できても、穢多は催事に参加できない決まりがあった。
それを知らない近所の者から、盛んに誘われはしたものの、甚六はやんわりとこれを断り続けていた。
つまり、おカネも立ち入ってはならないと、心に決めていたふしがある。
庄衛門が秘かに心を寄せていたことを、あの日になるまで知らなかった。
快楽事さえも村八分だったのである。
知佳の美貌禄「女衒の家に生まれ」

年端もいかぬ女の子が一心不乱に市街地を駆け抜けていく。
小さなその手に文を持たされ脇目も振らず遥か彼方の海の方角を目指し駆け去った。
時は明治。
生家はこの物語の主人公 久美が母から伝え聞いた、その母の記憶にある限り
女衒 (一般的には貧農が娘を質草として女郎を商う置屋、又は揚屋”あげや”ともいう に売る。このこの仲立ちをする男衆のことを言う) を生業 (なりわい) としていた。 という
母の父親である男 (以下 女衒という) は政府非公認の岡場所のあるこの地で髪結いという表向きもっともらしい看板を掲げてはいたが、裏に回ればそも置屋に生娘を世話する売春のための人買いであり皮剝ぎなどを主な生業にし忌み嫌われていた穢多(えた)だった。
穢多(えた)は非人の次に身分が低い。
人も避けて通る河原乞食が何故と思うかもしれないが、需要が無くなった皮剝ぎ様の商売をやめ主人公久美の母が物心ついた時には髪結いの表看板を掲げており食うに困る乞食・・・風には思えなかった。 という
地方で知らぬものとてない潤沢な資金 (女衒と金貸し) に支えられ知名度も高い家柄のように思えたという。 が、久美にこう語る母は今に至っても何故家柄が穢多 (えた) なのかわからないという。
どう卑屈に見ても大陸系でも皮剝ぎでもなく食うに困る河原乞食でもなかったからである。
テーマ : 官能小説・エロノベル
ジャンル : アダルト