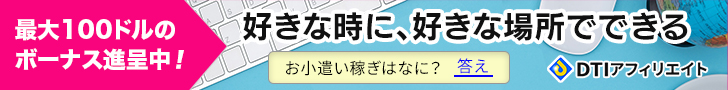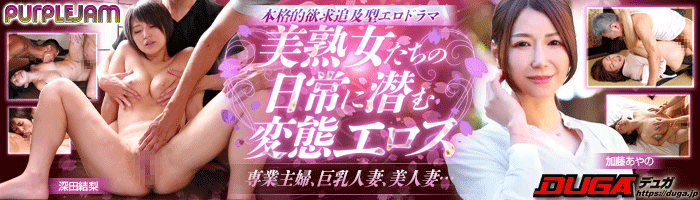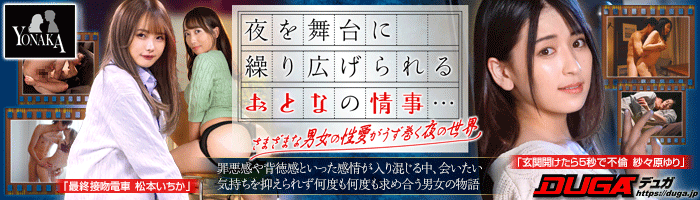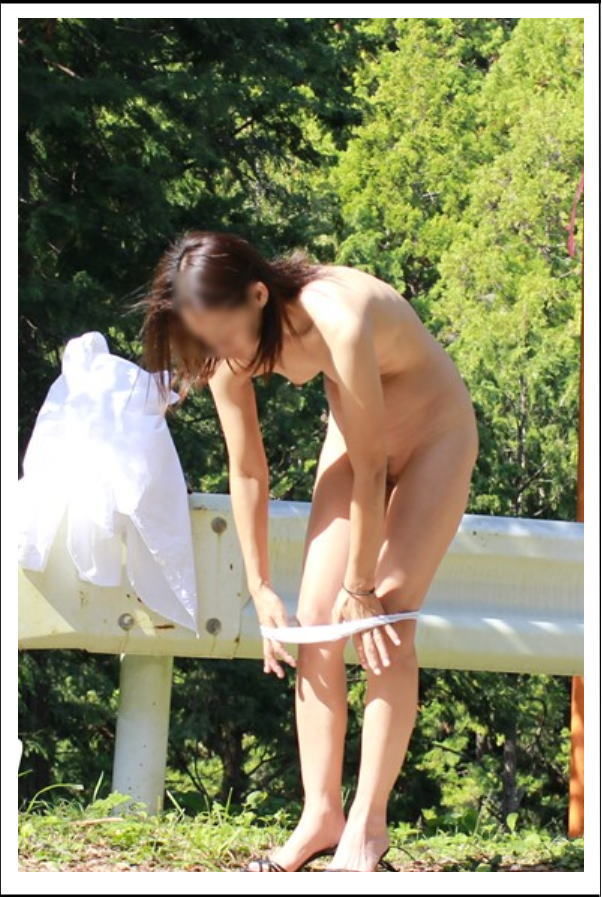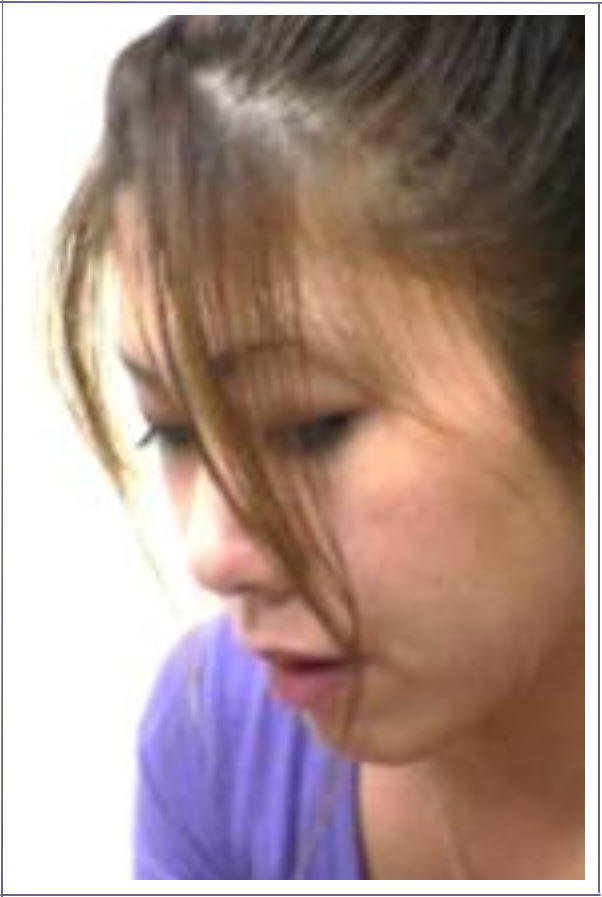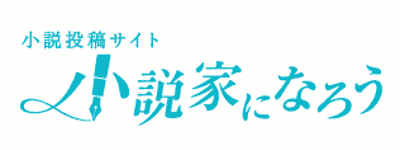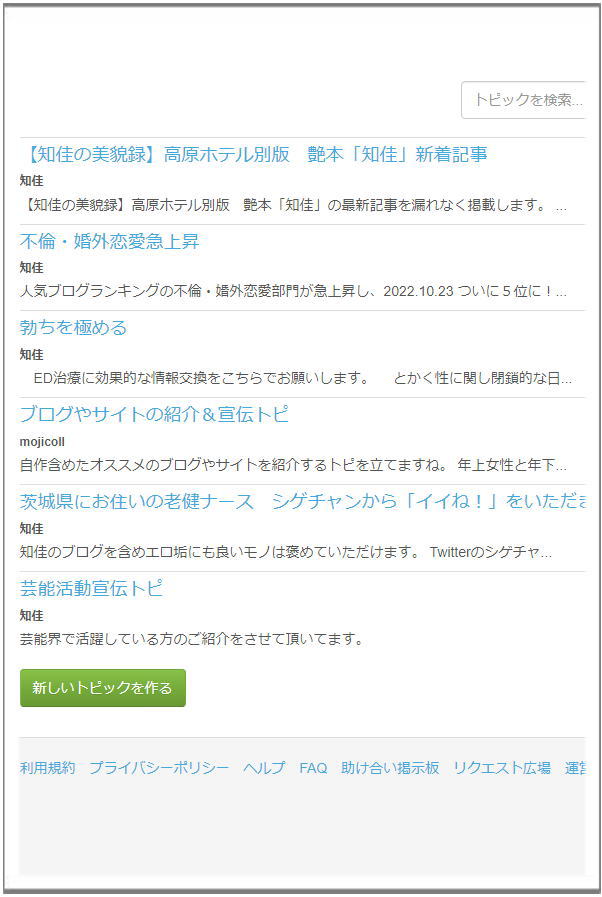疑惑 子供や夫に満足な食事を与えるための芝居
 腹上のおカネは戸惑った。
腹上のおカネは戸惑った。益々充血し、エラが張り出した亀頭が恥骨の内を嬲ってきている。
腰を使ってこの亀頭を奥に引っ張り込みさえすれば、カリ首を肉球で摘まみ嬲って頸部に押し付けて絞り出せないわけではない。
そうはさせまいと、庄衛門は突き出すおカネのアソコを太腿を使って腰全体を押しのけることで遮った。
下から微妙な位置に亀頭が来るよう己の腰を調整してくる。
おカネはこの先どうしていいのかわからなくなっていた。
確かに男根が欲しくてたまらなくなり待ちはした。
軽率な女であることは十分自覚していた。
それでも逝ってみたいと思った。
それ以上に、使命感のような目的もあった。
庄衛門から得る食べ物を、飢えた夫は山奥の炭焼き小屋でじっと待ってくれている。
是が非でも庄衛門をして食べ物を手に入れたかった。
今できることと言えば、庄衛門の首筋に唇を這わせ、熱い吐息を吹きかけ、悩まし気に喘ぎ声を聴かせてやることぐらいだった。
欲情し張ってきた乳房はとっくに与えてしまっている。
乳首だって、勃った状態になってしまっていて先ほどから舌先で転がされ、吸われ甘噛みされていた。
孕む危険のある子宮が眠る腹部だけは与えていなかった。
夫にだけ許した子作りのための卵巣がそこにある。
腹部を預けてしまえば、許されたと思って胤を仕込むべく執拗に突いてくる。
そうなれば耐えきれないことは先刻承知していた。
〈 この頃のウチは飢えている 〉
この飢えは原身につながっていることを過去の経験から学んでいた。
嫁ぐ日が迫った時、母から聞かされた男の秘密、
休むことなく射出させると薄まり、孕みにくくなる。
だから見せつけて外に出来る限り放出させなさいと。
出来ることなら休みなく射出させ、白濁したものがほとんど混じらない薄い液だけを、庄衛門を満足させるために搾り取るつもりだった。
だが、そうしている間にも庄衛門の棹は、確実におカネをオンナにしつつあった。
その結合時間をか弱いおカネの腹筋は持ちこたえられなくなっていた。
腰の細った部分を締め上げてくる庄衛門。
持ちこたえられなくなったおカネの腹部が庄衛門のでっぷりとした腹部を打ち始めた。
そうしてはならじと腹部に空間を持たせるべく体勢を変えようとしたが、遅かった。
恥骨あたりが意に反してしゃくりあげ、庄衛門にオンナの要求を伝え始めてしまっていた。
男は元来、視覚や聴覚に加え、妄想で欲望を増幅させる。
しゃくりあげ始めたおカネの、上体を押し上げると庄衛門は互いの結合部に目を凝らした。
庄衛門の屹立をどうにかしようと畳に腕を突っ張り、腰を屹立に向かって押し付けようとしたものだから、欲情し始めたアソコが棹を呑み込む様子が庄衛門の眼前で露わになった。
舐られすぎて潮を吹いたアソコが庄衛門の、抜き挿しする屹立に泡をまぶしつけヒクついていた。
それを見た庄衛門の屹立の裏筋が豊かな反応を示した。
おカネに組み敷かれた庄衛門の腰が動かないのに、屹立だけがビンビンとおカネの中で跳ねた。
射精感が募って耐えきれなくなってしまっていた。 が、庄衛門は歯をくいしばってこれに耐えた。
目が宙を泳いでしまっている割に、その指は尻の肉に食い込んでいた。
欲しがっていた。
オンナはこの男どもの反応に弱い。
亀頭冠は未だ襞の入り口付近というのに男がいきり立つ様子が臀部全体で感じられ、メスとして応じ始めていた。
挿し込みはさして深くないというのに、その興奮で棹全体を使って内壁を叩かれる刺激は使わない別の穴の奥にまで響き渡る。
この様子じゃ入り口に出されてもまずいことになる。
本能的に振り払っていた。
ビ~ンと弾けた棹が臀部の底を、その勢いで打った。
「あっ!!」 小さな、しかし悲痛な声がおカネの口から漏れた。
嫌われた・・・ 逃げないでもっと・・・
屹立に思わずワレメを擦り付け、元の位置に戻そうとするおカネ。
形相が変わった。
妻である前にオンナであることを、その形相が知らしめた。
意に反して抜かれたことを悔いている。
それを知ってか知らずか、庄衛門は倒れ込んだおカネのアソコから抜けてしまった切っ先を、シルでワレメを滑らせ後ろの穴にあてがうような仕草を見せた。
「あっ、そこはダメ!!」
悲鳴のような声を上げ振り返るおカネ。
先だっての弾ける動きで、初めてそこを突かれる刺激を求めている。
ツーンとした戦慄が過ぎったのだろう、半眼に目を閉じ眉間に苦痛の色をにじませた。
「そうか、ここも突いてほしかったのか」
後ろ向きに反りかえっていたおカネの顔が元に戻り庄衛門を見据えた。
すると庄衛門は、何事もなかったかのように再びワレメを切っ先でなぞって元の壺にめり込ませていく。
オンナの身体が徐々に熱を帯びて、そのぬくもりが庄衛門にも伝わっていった。
攻守交代の時期が来ていた。
おカネの意識は、今やすっかり子供や夫にはなく、ひたすらアソコ周辺を動き回る男根に注がれていた。
腫れ上がった男根をなんとかしたい。
その一点に意識を集中させているようだった。
庄衛門がその気ならと、おカネは腰を浮かせ跳ねあがる屹立の裏をワレメで幾度もなぞった。
勝ちに乗じたい女の浅はかな仕草だった。
亀頭の先端がマメを ともすれば舐るが、逝きそうになるのを必死で堪え、擦りあげた。
庄衛門はほくそ笑んだ。
頃合いを見計らっておカネがもてあそぶ屹立をワレメの中心でヒクつかせてやった。
その都度ビクンビクンと恥骨がしゃくりあげる。
やっと射出に域に達したと勘違いしたおカネは、急いで先端を摘まみ、蜜壺に誘う。
そこは心得ていた庄衛門が腰を捕まえて深く沈ませない。
庄衛門は待っていた。
おカネの放つ淫臭いと視線の先に溢れる愛液、それら全ての刺激によって胤の濃度が深まるのを。
おカネ自身の肌が朱に染まり、全身に脂汗がにじみ出て額に血管が浮き出るほど欲情するのを。
その時こそが想いを遂げる時期。
押し倒し、組み敷けば 自然と腰を浮かせ子宮を差し出すだろうと思って待った。
既に小半時、ふたりは身体を重ね合わせていた。
それでもおカネは堕ちなかった。
逝きそうになるのを必死で堪えたおカネは、
「ごめんささい、障子の外が気になって・・・」
ポツリと呟いた。
かすかだが、外で物音がする。
〈 しまった! アヤツめ、帰ってきてやがったか・・・ 〉
焦りが委縮につながった。
見る見るうちに萎んでしまう男根を目にしたおカネは、醒めた様子で立ち上がり、そそくさと衣服を着始めた。
すっかり着終わると、庄衛門に向かって脱ぎ捨ててあった衣服を投げてよこした。
「速く着てくださらない? ウチの人 帰ってきてたみたいだから」
見つかりでもすれば、庄屋さんとしては困るでしょう?
「今回のことは・・・」
内緒にしておいてあげると妖艶な笑みを浮かべながら云った。
庄衛門は青くなった。
〈 しまった! 罠だった!! 〉
冷や汗が出た。
人様の女房欲しさに、相手が穢多(えた)だということをすっかり忘れていた。
下手を打てば、三尺高い樹の上に吊るされかねない。
裏の小部屋に急いで忍び込み、そそくさと衣服を身に着けると小窓を潜り抜けて藪の中に脱出した。
這う這うの体で逃げ帰った庄衛門は、女房に怪しまれてはと野良仕事の支度をして裏木戸を抜けた。
土塀に沿って萱の原に出かけ、そこで冷めやらぬナニを擦ってヌクつもりでいた。
角を曲がった瞬間、物陰に身をひそめて待ち構えていたおカネの夫 作佐がノソリと現れた。
その風体たるや空恐ろしいほどに瘦せこけ白蝋化してはすまいかと思われるほどだった。
庄衛門は思わず跳び退った。
「貴奴めが、何の用じゃ!?」
驚いた弾みに、つい口が滑った。
「いやなにね、おカネのヤツが預けてたもの受け取ってきてくれんかと、泣いて頼むものだからのう」
「預けてた!? はて?何のことやら・・・」 腋に脂汗が滲み出たがとぼけた。
知ってはいたが、つい今しがた当のおカネのアソコを小半時もつついたばかり、言いあぐねた。
まさかこのような風体になった夫に、ワレメを貸し出した駄賃の取り立てを頼むとは思っていなかった。
「それなら納屋に積んである。勝手に持って行け!」
もうどうでもよかった。
恐ろしさで、一刻も早くこの場を立ち去りたかった。
「ほうですか。ほんじゃあもらって帰りますけんのう」
深々と頭を下げて立ち去っていく。
〈 食い物をよこせじゃと!? 誰の米じゃと思うとる! あの風体で女房を抱こうというんか?貴奴め、最初からそのつもりで貸出しておったんか!!」
してやられた。
いい気になって、小半時もおカネの入り口をつつきまわしていた。
あれでおカネも随分逝ったように診た。
食うものにも困る作佐のモノでは思うように使うことすらできないでいたから、それと思えないほど食わせてもらっていたおカネはずいぶん溜まっていたのだろう。
衣食足り、漲っている庄衛門の屹立にこの事情の中であっても、目の色を変えてむしゃぶりついてきた。
この機会を逃せば、再び挿し込んでもらえることは出来ない。
その、最後の望みに賭けて庄衛門を部屋に引き込んだことも事実であったろうと そらで思った。
小半時かけて夫に見せつけ、自らも楽しんでいたのだろうと。
だが、炭焼き小屋に追いやっておいた夫があのようなさまになっていようとは、流石に庄衛門でも思わなかった。
庄衛門が奮い立つほどの肉付きで迫るおカネ。
その妻の夫が餓死しようとしている。
〈 確か子がいたはずじゃ 〉
子にもろくに食わせず女房を養っていたことになる。
あの身体を維持させるには、作佐は食った真似をして茶でも啜って誤魔化し、なにもかも与えねば、この飢饉の中乗り切れなかったであろう。
このところの長雨と日照不足で小作連中に貸し出している田からの上りは思うように取り立てが進んでいない。
とても元が取れる石高はなかった。
その中にあって、近隣住民の それもうら若い嫁いできたばかりの嫁を狙って食い物を餌に寝取る。
鬼のような仕打ちだった。
恨まれていようが、日頃たんと食っている庄衛門には小作どもと違って脂ぎり、疼いてしようがなかった。
( それもこれも衣食足りてのこと 〉
作佐にも食わせてやりさえすれば、あのようなみじめな姿にならぬはず、
今にして思えば、おカネなりに考えてのことであったろう。
それを後先考えずにつついた。
おまけに庄衛門は、勝ち誇ってなにがなんでも逝かせてみせようと入り口ばかりつついた。
おカネは惑乱と正気の狭間で庄衛門から食い物を引き出そうとしていた。
〈 なあに、所詮はオンナ。造作もないことじゃ、よそのオナゴのようにの 〉
庄衛門はうそぶいた。
そう考えでもしなければ気がふれるような恐ろしさに身が持たなかった。
奥深く、心行くまで絞り出し かつ逝かせていたら状況はもっと変わっていただろうと、ここに至っても考えていた。
「少なくとも、次の機会を狙って米を貢ぐことなど造作もない」 そう考えた。
炭焼き小屋でじっと待っていた夫に今宵は、その米を食わせることだろうと思うと、庄衛門は心穏やかにはいられなかった。
「アヤツめ!!今度こそ!」
萱藪の中に隠しておいたおカネの腰巻に向かって渾身の飛沫を飛ばし、苛立ちを紛らわそうと擦った。
ひたすら虚しかった。
棹に残る粘りにおカネのアソコを思い出し、目を閉じ剥けた皮の辺りから血が滲むかで擦った。
足りなくて、足音を忍ばせ、閨を覗きに、おカネの中に墓場から這い出したような作佐のアソコが食い込む様子を観に行った。
その頃作佐はおカネの給仕で粥を啜っていた。
「ゆっくり食べないと身体に悪いから・・・」
おカネの、作佐を気遣う声が聞こえた。
「こんなになるまで耐えてくれて・・・」
すすり泣きが聞こえた。
ちゃんと着衣してたと心の中で作佐に向かっておカネは叫んだ。
「モンペが僅かに足首に引っかかってた・・・ 拒否してた」
空になった胃の腑に流し込んだお粥で、作佐は苦しげな表情をした。
目がつり上がり、気を失うのではないかと思われた。
もう寸刻遅ければ、命が尽きたかもしれない。
「振り払ってただけ・・・ ちゃんと頑張った」
ぼろ屋の板壁にはところどころ破けめがある。
そこに顔を押し付け、食い入るように我が妻が庄衛門から何かを得るのを診ていたに違いなかった。
だからおカネは腰を浮かし、庄衛門の要求に応えようとしなかったのかもしれなかった、たとえ先端だけ入っていたにしても扱いた。
腰や胸に手を回され抱き着かれて身動きできない状態ながら、アソコを結合しようとするのだけは振り払っているように見えもした。
微妙である。
切っ先は確かに割っているが、受けたように見えてもコリコリした部分は、まだ中じゃないと言いたげだった。
妬みきって覗き込む作佐、庄衛門の切っ先の行方を追っていた。
〈 儂は生き死にをかけて守ろうとしていた嫁を寝取っていたのか・・・ 〉
神仏に近い扱いを受けていた、その人妻を寝取ろうとしている。
もう野で放ちながら許しを乞う必要はなかった。
( 食い物を持って行ってやろう。これまでのように、作佐めが死なぬ程度にの 〉
渡すものを渡してやれば本気で明け渡すはずじゃ、
庄衛門は心の中で言い放った。
庄衛門の診立て
 夫が炭焼き釜に出かけていった直後のその日、偶然を装って家の軒先に現れた庄衛門と、女房おカネは縁側で茶飲み話をしていた。
夫が炭焼き釜に出かけていった直後のその日、偶然を装って家の軒先に現れた庄衛門と、女房おカネは縁側で茶飲み話をしていた。その気があって現れた庄衛門の股間は既に、おカネの目の毒とばかりにいきり立ち盛り上がっていた。
のらりくらりと世間話に講ずる庄衛門。
おカネは時間が気になって仕方がなかった。
炭焼き釜に出かけなければならない時間が迫っていた。
先日の続きをせがめるとすれば、この機会を置いてほかに、当分ない。
それは耐えきれないことだった。
あの事があった翌日も、そして次の日も庄衛門は洗濯物にぶっかけて帰っていっている。
〈 ウチ以上に欲しがってらっしゃるはず・・・ 〉
それを確かめたかったし、あの日のお返しに濡れそぼったアソコをさいぜんのようにペロリと舐めてほしかった。
庄衛門に魅せたい。
アソコがどうなってるか、庄衛門に診てほしかった。
庄衛門の屹立は、さいぜん口に含み、先端から滲み出る液をたんと味わわせてもらっている。
それからというもの、おカネの中のオンナの虫が疼いて実のところよく眠れていなかった。
他の女たちが庄衛門の屹立を迎え入れ、悩乱したという。
それはどのようなものだったのか気にかかった。
あのようなふしだらな女どもに、金輪際負けたくなかった。
庄衛門を二度と他の女に奪われたくなかった。
いつも隣にいて、必要な時にそのカリ首を使って他のオンナ、妻という人よりももっとしつこく探ってほしかった。
会話が中断し、想いにふけっているおカネを、心配そうに庄衛門が覗き込んだ。
「顔色が悪いようじゃが・・・」
「よう眠れんで・・・ 庄衛門さんは医の心得があるいう噂じゃが・・・」
診てやってもええぞ、そんでも縁側の先じゃ 具合がのう、
「オヤジがおらんうちに、上げてもらうのも・・・ 妙な噂が立つ」
「ああっ、そんなことは・・・」
おもむろに立ち上がり、帰ろうとする庄衛門の袖口を掴みおカネは懸命に引き留めた。
片足で立った拍子に盆の上に置いていた茶がこぼれ、縁側を濡らした。
慌てて被っていた手拭いで縁側を拭くおカネ。
貧乏暮らしとはいえ、茶で縁側を濡らすことなど許しはしない夫に仕えていた。
「上がってもらえたらええんじゃが・・・掃除もろくしとらんで、恥ずかしい・・・」
情けない、精いっぱいの言い訳だった。
見る見るうちに涙が溢れるのが分かった。
「縁側の先の、ほれっ、そこの座敷までじゃ。障子を閉めたら外から見えはせん」
庄衛門の言葉におカネは頬を朱に染めた。
「アレッ やんだ~ 庄衛門さんたら・・・」
「案ずるな! よう診てやるわい!」
我が家でもないのに、庄衛門はおカネを引きずるようにして縁側の奥の部屋に引き込むと、衣服を剥ぎ取っていった。
双方心得たものである。その間、おカネには屹立が与えられた。
おカネが欲しくてむせ返るような臭いを放つ朱衛門の屹立だったが、それが功を奏した。
それこそ、今日の、今の今おカネが欲しがっていたモノだった。
もしも炭焼き釜に行く途上、大の大人が放っていたとしたら、おカネは魅入ってしまっていたかもしれなかった。
それはそれで寝取られてしまう。
今朝のおカネにはそんな危うさがあった。
庄衛門はおカネの肌に、己の肌を擦り付け、要所要所に舌を這わせた。
おカネの身体が庄衛門に手を握られた、その最善から小刻みに揺れ始めていた。
障子一枚隔て、夫の留守に乗じて常日頃から言い寄る他人の庄衛門と、我慢できなくなって秘め事に講じようとしている。
「よそ様に許す」 その卑猥さ、
それでいて止めようもないほど溢れかえってくるのが分かった。
「もしも帰ってきて、ウチの人に見つかったら叱られる」
懸命に庄衛門に訴えるが、聞かなかった風を装って庄衛門は益々屹立を反り返らせて、おカネの眼前に見せつけてくる。
腰巻はとっくに脱がされ、モンペが足首に引っかかっているだけの姿になっていた。
まだ不貞は働いていない証拠として、剥ぎ取られないよう踏ん張った。
「ああ・・・待って、お願いだから辛抱して・・・」
うわごとのように呟きながらもおカネはしっかりと棹を握りしめ、放そうとはしない。
オンナが我を忘れさせた。
怒張を与えられた興奮で、挿し込みを待ちきれなくなっていることが、その肌のぬめりやヒクつく様子で、幾度となく寝取りを経験した庄衛門にはわかった。
〈 ふふふっ、思った通りじゃわい。飢えとるのう )
十中八九、庄衛門はこの方法で人妻を寝取った。
その経験がモノを言った。
表面上は気高く泊まっている。 だがその実、加齢とともに子宮が勝手に疼きオトコを欲しがって下手に見せつけられようものなら・・・
「待ってたんじゃのう、よしよし 今診てやるだで」
庄衛門はおカネの腰の括れあたりを舌でなぞった。
鳩尾あたりからゆっくりと唾で濡らした指先を這わせ、臍を下り降りて繁みを分け入るとクリを一気に飛び越え、割れた部分にその先端をヒタとあてた。
ビクッと瞬間反り返る仕草を見せたかと思う間もなく、今度は屈するように腰を折り曲げアソコを庄衛門の指先目掛け押し付け、ヌブヌブと二本の指を呑み込んでいく。
指の先端がザラつく何かを捉えた。
こねくり回しが始まった。
指先が糸を引く。
その動きに、責められているオンナ自身が反発と迎え入れを繰り返すし恥骨がヒクつき、やがて全身にヨガリと思える痙攣が走った。
潮を吹き始めたのはその時だった。
所作の繰り返しで足首からモンペが脱げた。
太腿が大きく割れ、秘密の場所を包み隠していた唇が開け放たれ、めくれあがっていった。
見下ろす尻越しに、これから挿し込もうとする壺の中が見て取れるようになっていった。
部屋中に淫臭が満ちてゆく。
おカネの動きが大胆になっていく。
屹立を持ち上げ、裏筋を舌先でなぞると、皺袋を頬張って啜り始めた。
男日照りで欲情しきったメスの、紛れもなくそれだった。
お互いにすっかり準備が整っていた。
あとは庄衛門の誘導次第、
庄衛門はおカネの口元から屹立を引き剥がしにかかった。
腰を次第に落とし、床に皺袋が擦り付くほどに体勢を変えた。
焦れたおカネの顔が庄衛門の胸元まで這いあがってきた。
その体勢であっても庄衛門はおカネのアソコから指を引き抜かなかったことが功を奏した。
ゆるゆるとおカネの身体の下の潜り込もうとする庄衛門。
おカネが再び庄衛門の屹立を自由にできた時、既に庄衛門に対し、騎乗させられていた。
先端を摘まむ形で庄衛門と向き合ったおカネ。
庄衛門はこの時になっておカネのアソコから指を引き抜いた。
腰を両手で掻き抱くと花芯にカリ首が当たるよう誘導してやった。
微妙に身体をずらしながらワレメを切っ先でなぞる。
これを幾度か繰り返した。
おカネの負けだった。
意を決しておカネはカリ首を壺にあてがった。
〈 こいつめが、やっと云うことを聞く気になりおったか。 それにしても長かったわい )
野に放ったあと、汁を舐めてやって以来夢うつつにも惑乱させられた。
ぽってりした肉襞を口に含んだ時には「勝った!!」と思った。
ところが、ものの見事に逃げられた。
掌にいた子兎を逃したばかりか、目の前で肝心な部分をいきり立つ庄衛門に向かって見せつけてくれた。
その、憎い朱の襞が己の屹立を乞うてくれている。
憎さ故、なお愛しくてならなかった。
あてがった亀頭を一気に呑み込もうとするおカネの腰を、こともなげに誘導し割るか割らないかの瀬戸際で引き抜く庄衛門。
焦れたおカネが乳房を庄衛門の預ける形で前のめりに身体を重ねてきた。
緊張と興奮でしゃくりが治まらず、亀頭をうまく花芯にあてがえなくなっていた。
庄衛門は身体ごとせり上がってきたおカネの唇を、真っ先に奪った。
〈 オラだけのオトコ 〉
おカネの意志でピタリと肌を合わせた時を待っていたかのように、庄衛門の亀頭が狭い通路を割ってめり込み、そのザラつきを捉え嬲り始めていた。
「あの時には既にココが病んでいたようじゃの。儂の見込んだ通り、早いうちにココに灸をすえねばのう」
「・・・はい・・・」
庄衛門にしがみつきながら消え入りそうな声でおカネは応えていた。
〈 歯ぎしりした、あの時の儂の思いを今度こそお前のアソコに思い知らせてやる )
苦労した甲斐があった。
女は所詮オンナ、一旦挿し込んでしまえば あとはこちらの言うがまま操れることを、散々人様の女房を寝取ってきたこの男は知っていた。
「競ってはならんぞ。ここからが肝心。病が治まるようしっかりと揉み込むんじゃ」
揉み込めば揉み込むほどオンナは病に伏せる。
末は女房に向かって怒鳴り込んでくることぐらい、とっくに知っていた。
知ってはいたが、男としての尊厳を無視されたことが許されなかった。
壺の奥、男を咥え込みたくて待ち構える腫れ上がるようにせり上がった襞も、更にその奥の、胤を求めて亀頭をつつきまわす頸部も、泣きわめくまで嬲ってやらねば気が済まなかった。
更に奥を探ってほしくて恥骨をしゃくりあげるおカネの腰をしっかりと支え、貫かないようにしながら尚もザラつきを見極める庄衛門だった。
嬲り合い
 とかく庄衛門はマメだった。
とかく庄衛門はマメだった。空模様が悪い時とか、用事があって遠方に出かけなければならない時にでもなければ、何処からともなくおカネの家に、仕事先に亭主の留守を見計らって顔を出した。
おカネに対し、世間話をしたがった。
興が乗ると、おカネがハッとするほど顔を近づけ、眼の奥を窺う。
余りに近さに、おカネが身動きできないでいると、胸元から立ち上がる乳房の臭いを嗅ごうとした。
おカネに乳房の、丁度覗き見えるところは 淡く血管が浮き出て、まるで搗きたての餅のようで、それだけで男心をくすぐった。
しげしげと覗き見る庄衛門の横顔に、それとわかるほど深い吐息を吹きかけるおカネ。
胸いっぱいおカネの香りを嗅ぐと庄衛門は、
「よっこらしょ」 掛け声もろとも立ち上がろうとする。
よろめいたように見せかけ、思わずその庄衛門に手を差し伸べようとするその拍子を狙いすまし、おカネの太腿に手を置き、姿勢を元に戻した。
瞬時だったが庄衛門の指先は、しっかりと女心を探った。
「えぇっ~と・・・ああそうか・・・」
謎めいた言葉を残し、庄衛門はついっと茶の席を立って縁側から遠ざかっってしまった。
気になったのはおカネのほうだった。
慌てて後を追う。
そそくさと庭先を横切って家に通ずる坂を下っていく庄衛門。
下った先をついっと横に反れた。
おカネが後追いするのを見届けると、石垣に向かって悠然と放つ態勢をとったのである。
おカネのためだった。
胸元の香りを嗅ぎ、欲しくてたまらなくなっているんだということを屹立を捧げることで伝えた。
放出しようにも、先端から出てくるのは我慢の限界を超え滲み出る涙だった。
おカネはその様子を、石垣で身を隠すようにしながら覗き見た。
庄衛門は、褌の隙間から引き出した屹立を おカネのためにビクンビクンと脈打って見せた。
視線が一点に集中するのがわかった。
おずおずと手を挿し込んで、潤みをまさぐるおカネ。
「天網恢恢疎にして漏らさず・・・」
持念
庄衛門は独り言のようにつぶやき、欲情するおカネから目を逸らせてやった。
〈 いつぞや、舐めあげてやっとことを忘れておらにゃあ、儂の棹に震い付いてくるはずじゃ 〉
オナゴの反応というものは、セク男連中より鈍い。
だが、ツボにはまれば抜け出すことなど容易にできない。
着物の端をたくし上げ、指が収まるところに収まっている。
鎮めようと蠢かすまでの辛抱だった。
「・・・あああ・・・ふん、あっ・・・」
耳を澄まさなければ聞き取れないほどの小さな声が漏れだした。
おカネが自らの指で逝き始めていた。
庄衛門は、おカネに気づかれないよう距離を詰めてやった。
空いた左手が屹立を欲しがって衣服の裾を掴み身悶えている風に見えたからだった。
そっとにじり寄った。
やがて、庄衛門とおカネは身体同士が触れ合うほどの距離になった。
ワナワナと小刻みに身体を震わせ、庄衛門の屹立に見入るおカネの、忍ばせたアソコの、その指の間からシズクが流れ落ち、太腿を濡らし陽光に照らされ光っている。
「可愛い奴じゃ」
庄衛門はおカネの額に唇を這わすと、右手でそっとおカネの手を取り、屹立に添えてやった。
周囲から決して見えないよう、右肩でおカネの左肩を押すように、身体ごと石垣に押し付けるようにしながら、その肉棒の味を伝えてやった。
遠慮がちに掌で包み込むおカネ。
愛おしさに庄衛門は、おカネの掌の中の屹立をおカネのために蠢かせてやった。
おカネの目にも、ハッキリとアソコに挿し込む時の動作に見せかけ腰を振って蠢かした。
おカネの頬が朱に染まった。
念じ続けたアソコへの挿し込みを合意してくれた証拠だった。
「確かめ合う日は・・・近い?」
「おお!!そうじゃ!!そのとおりじゃ」
ここでと言いかけたおカネを目で制した。
誰が見ているとも限らない庭先の、石垣の根元で押さえ込むわけにもいかなかった。
暫くの間は自慰で済ませていたおカネだったが、屹立の先端からいよいよもって流れ落ち始めた涙と、庄衛門の息苦しそうな表情にたまりかね、自らの意志で庄衛門をしごきはじめた。
しとどに濡れそぼった指をアソコから引き抜くと、屹立を握りしめ、そのシルを塗りたくってしごいた。
庄衛門は歯をくいしばって耐えた。
気のすむまで嬲らせてやるつもりだった。
先端から滲み出る我慢汁を愛おしそうに見つめるおカネ。
ともすればくじけそうになるおカネの腰を、庄衛門は尻に肉を鷲掴みにして支えてやった。
柔らかい肉だったが、それでいて弾力があった。
指先に伝わる感触で、おカネのアソコの中まで差し計ったように見通せた。
庄衛門が耐えがたくなって力むと、つい おカネを引き寄せてしまうことになる。
互いの距離が詰まって、おカネの唇が庄衛門の屹立を捉えざるをえなくなっていた。
おカネの吐く熱い吐息を感じたと思ったら、ぬめぬめとした唇で先端が捉えられていた。
突き抜けるような快感が庄衛門の脳天を突っ切った。
耐えがたい興奮の中、庄衛門は冷徹におカネの様子を探った。
指先がおカネのアソコに、もう少しで差し掛かろうとしている。
時間との戦いだった。
〈 右手の指はおカネのアソコに治まり、ヒタヒタと中を嬲っている 〉 そんなことを妄想しつつ耐えた。
おカネは儂無しでは一日と持ちこたえられんようになる。 いやしてみせる。
半狂乱になって屹立にしがみつくおカネの、乳房はすっかり露わになり、もはや衣服を身に着ける意味すらなく、支える庄衛門の袴はおろか、足の甲にまでシズクを垂れ流し濡らしてしまっていた。
おカネは儂を手で嬲っていようが、儂は儂であやつの心の中を嬲っておる。
( どちらが先に泣きを入れるか、そこが勝負どころじゃ 〉
射出が始まる予兆がした。
「おカネ、好きじゃ。儂は気がふれたかもしれん」
おカネの口から嗚咽が漏れた。
tag : 持念
疑惑 人妻おカネのモンペや腰巻に執着し始めた庄衛門は
 男と女の、このようなふしだらな行為を許せる風潮では、当時はなかった。
男と女の、このようなふしだらな行為を許せる風潮では、当時はなかった。入沢村でなくとも、男女が並んで歩いただけで厳しくとがめられた時代だった。
それ故、気持ちを伝える手段と言えば、
何かをそれとなく届けるとか、
周囲の目に触れるか触れないかの瀬戸際のところで、
相手にだけわかるよう晒すしかなかった。
おカネと庄衛門はこれを、村の若い連中が行うように秘かに行った。
妙な話だが、当時は排泄行為を、今のように完全密閉の空間で行う習慣を貧乏屋では行えなかった。
潜むように物陰に隠れて、女はしゃがむ以外になかった。
男は堂々と道端に放出するのが普通だった。
だがそれは、気になる相手からみれば、
まだ温もりのある間に嗅ぎに行き、
手で触れることが出来たなら、
「オラのために・・・」
気持ちが伝わるのである。
そこで庄衛門は、決まった場所で決まったように放出した。
それを見たおカネは、それとなく物陰に忍び込み、しゃがむのである。
その距離が次第に縮まったのは言うまでもない。
ある日庄衛門は、おカネが用を済ませて立ち上がった瞬間を見計らって、
素知らぬ顔で近づき、
湯気の上がる地面にしゃがみこんで、
今放出し終わったおカネを見上げた。
おカネは慌てた。
なにしろ、モンペの前ひもは後ろに廻して最初から結んであってよかったものの
前で結んでいた紐をほどいて、尻をまくっていたからたまらない。
焦るあまり、たくし上げようと試みたモンペの後ろが、
豊かな臀部に引っかかり、
まだシズクの垂れるアレを覆い隠せなかった。
庄衛門はそれを見逃さなかった。
「おいっ、まだシズクが垂れとるぞ!」
こういったかと思うと、
おカネの背をポンと押した。
前のめりで倒れた拍子に、おカネは四つん這いでアレを庄衛門に晒す格好になってしまった。
「どれどれ、しょうのない奴だ」
再びしゃがみこんだ庄衛門は、ぺろりとおカネのシズクを舐めとってしまった。
しまったという思いがおカネに沸き起こった。
〈 他人じゃなくなってしまう 〉
夫の甚六に知れたら・・・
そう考えただけで胆が冷えた。
地面に崩れ落ちるようにおカネは身を投げ出し、
必死で胸を押さえた。
この状態から庄衛門に押さえ込まれ、胸を開けられ、吸われたりすれば
拒絶しきる自信がなかったからである。
「恥ずかしいシルまで舐めとられた気がした・・・」
相手を、横目でにらみながらジリジリと地面を這いずって逃げようとした。
「えらい匂いがしたぞ。どうれ、儂もひとつ」
おもむろに庄衛門は前を開くと、
すっかりそそり立ってしまったアレを取り出し、
おカネの放った痕に向かって放出の姿勢をとった。
微妙な時間が流れた。
庄衛門の、充血しきったソレからは
放出しようにも路が開かなかった。
反り返りながら、懸命に力む庄衛門。
だが、滴の一滴も その先端方出てこない。
豪快な、そのさまを見せ付ければおカネも納得しやすまいか、
その考えが甘かった。
ただでさえ、おカネ欲しさに充血し放出を妨げているのに、
その狙うアレから滲み出たシルを舐めてしまっていた。
前を開く直前に褌の端で我慢汁を拭い取り、
何の変哲もないソレを晒し、力みに合わせ腰を振る
妙な格好をするだけになってしまっていた。
「おいっ、おカネ。手伝って・・・」
言いかけて脇を見ると
おカネの姿は消えていた。
おカネはおカネで、甚六に見つかってはと
懸命に水場に向かって走っていた。
「見つかる前に洗い流せねば・・・」
庄衛門の唾液で間違いが起こってしまう。
生まれて初めて男の愛撫というものを、まさかの庄衛門から受けてしまっていた。
それも、庄衛門のやることなすことに、
すっかり我を忘れシルが垂れるほどになっていたソレにである。
混乱する頭を冷やすには、
ソレごと谷川に冷水で冷やし、清める以外に方法がなかった。
尻を隠すべきモンペは後ろを開け放ったまま、転がるように走っていた。
地面にシルの一滴も垂らすまいと、前を掌で押さえつつ走った。
「庄屋が・・・庄衛門さんが・・・」
押さえた掌に生暖かいシズクが溜まるのが分かった。
「どうにか・・・せんと・・・」
しゃがみこみ、指を挿し込んでは溜まったのもを掻き出して、誰にも、殊に庄衛門に見つからぬよう秘かに枯草の柔らかい部分を使って拭い取った。
なんとか乾いたと思いきや、また立ち上がって走った。
「あんた・・・オラ・・・悪いことした」
水辺に辿り着くと、
モンペを脱ぎ捨てて水に入り、下半身を洗った。
すっかり下腹部が冷え切って、
どんなに指を挿し込んで掻き出そうとしても
ヌルミすら感じなくなるまで探った。
すっかり擦れて血が滲むほどに擦り洗った。
それを覗き見ていた庄衛門には、
おカネが庄衛門のいきり立つものを、実は欲しくて、
治まりが付かず、
指を使って感情を押し殺そうとしているように映った。
透き通るような谷川の水の中で、
すっかり上気したソレに指を挿し込んで、しゃくりあげる腰を空いた掌で抑えつつ鎮め
自身の指で興奮が治まるまで掻き回している。
そう感じた。
おカネ自身、なにがなんだかわからないまま、とにかく洗い清めた。
それでも、自宅に帰り着き、甚六と向かい合わせに坐して食事のもてなしをするときなど、
庄衛門の臭いを甚六に嗅ぎつけられはすまいかと冷や汗が出た。
正座でもしようものなら、
踵が嬲ったソレに食い込む。
すると再び庄衛門の舌の、唇の感触が甦って濡れた。
甚六の手前、もてなしが忙しく、正座もできないという風に装いはしたが・・・
〈 オラを欲しがってた。押さえ込まれる 〉
これまでのように、気安く近寄れば、きっと犯される。
そう思う先から濡れた。
「あん人も、オラのこと・・・だのにオラは・・・どうしたらええだか」
腰巻のその部分は、もう危ういほどに湿っていた。
モンペを通して、腰巻の中が危うい状態になっていることを、
甚六に悟られはすまいかとヒヤヒヤしながら給仕を済ませた。
庄衛門から逃げ延びながら、いつのまにか身体が庄衛門を受け入れようと蠢いていることに気づいた。
甚六は食事を終えると昼間の疲れが出たのか、
その場で横になり、鼾をかき始めた。
その隙に、おカネは外に出て裏に回り、モンペを下にずらし腰巻を脱いだ。
替えの腰巻を履くまでの間、モンペに下はスッポンポンだが、
腰巻の濡れがモンペを通して透けて見えるのは何としても避けたかった。
汚れた腰巻は何気ないように汚れ物と一緒に洗い場に置いておいた。
この様子を、裏の竹やぶの中から、眼を光らせ盗み見るものがいた。
その翌日からだった。
モンペや腰巻を干しておくと、
肝心な部分に何かが付着して黄ばみ、ゴワゴワになってしまっている。
ぶっかけだった。
おカネの奥深く、渾身の思いを注ぎ込みたくて、
実は、治まりが付かなくなった庄衛門はおカネの自宅付近を連日うろついたのだが、
どうにも同意を得て押さえ込む手段と言おうか、
突破口が見当たらなかった。
だが目の前には、熟れきった人妻が立ち働いている。
板壁の隙間から覗き見ては、己の分身を擦った。
秘かに貢物を置いて「逢に来た」の合図代わりとし、立ち去ることも忘れなかった。
そうこうして見つけたおカネの、大切なまだ洗わない下着に向かって鼻面を突き付け、
胸いっぱいに香りを吸い込んだ。
吐き気がするほど肉体はおカネを欲し、その興奮ゆえの血圧上昇で後頭部が傷み、行き場を失った皺袋から飛び出せない胤の圧が前立腺を圧迫し、下腹部にも鈍痛が走る。
「あのアマめが・・・」
己のもとに屈しようとしないおカネに、焦がれるゆえの憎しみが増していく。
咄嗟に思いついたのが、ぶっかけだった。
せめて分身に向かって放出でもせねば、気が治まらなくなっていた。
このことに気が付かないおカネは、ひょっとすると付着したままの下着を、
それともとうに知っていて、秘かに身に着け楽しんでくれるかもしれないとも思った。
もしも知ったうえで身に着けてくれ、身悶えてくれることさえ分かれば、
それこそ真の気持ちを、秘かに推し量れる、またとない手段だと思ってしまい、ありったけぶっかけようとした。
たまりにたまった胤は、自身の力で寸止めすることなどできないほど勢いよく飛び出しきった。
射出の瞬間、全身に鳥肌が立つほどゾッとするような快感が駆け巡った。
「ふふっ、この勢いのあるモノをアソコが受け入れたなら、間違いなく惑乱するはず」
妄想の中で、おカネが何度も欲しがり、よがり声をあげしがみつく。
「ええ具合なアレじゃった。儂のを挿し込むとキツキツじゃった風に見えたでのう」
やっとのことで萎えたオノレをズボンの、褌の中にしまった。
帰り際、おカネの家の、いつもの庭先で、おカネがかつて喜んだ臭い付けを試みると、膀胱が空になるほど放出できた。
庄衛門の頭上に幸運が、一気に舞い降り、おカネと間もなく結ばれるような気がしてならなかった。
初手は妙だな、〈 ひょっとしたら月のものでも着いていたことがくがわからず洗濯を 〉、が、どんなに考えても思い当たるふしがなかったし、生まれてこの方見たことも聞いたこともなかったので頓着しなかった。
貧乏暇なしというが、のんびり洗濯をしている暇などない。
洗いあげたはずの腰巻の、アソコに触れる部分が妙に、多少ゴワゴワするけれど、〈 生地が傷んでいたところに太陽さんの照り返しが当たったものだから 〉そう思って、おカネはそのままの状態でいつもの通り身に着けた。
働き出すと、もうその忙しさに気が紛れてしまったが、その間にもアソコは汗蒸し、じんわりとゴワゴワがその汗様のモノで元の射出された時の形に戻り始め、おカネの女のオンナの部分を刺激し始めていた。
身に着けて働き出し、おおよそ小半時も過ぎたころ、妙にアソコが火照り、湿るのに気がした。
それに加え、胸元からなにやら人恋しい臭いが立ち上って鼻腔をついた。
その匂いをかすかに感じるたびに、風邪を引いたわけでもあるまいに頬が火照った。
そして、何位に反応してか、しっとりと、さらに一層アソコが潤みを帯び始めている。
おカネの放ったシルの刺激に耐えかね、庄衛門が洗濯を終え干していたおカネの下着に残していった胤に、おカネのオンナが反応し始めているとは・・・おカネこそ、どこか懐かしい香りだと感じてはいたが、さすがにそれが庄衛門の胤だとは思い浮かばなかった。
甚六から日頃、お情けを受けていなかったから、胤の、卑猥な気持ちにさせられた時に滲み出るシルとの混合臭いをすっかり忘れ、己の身体の、男への変化に気づかなかったのである。
庄衛門が秘かに忍び込んで、おカネに向かってまぐわいたい合図を、胤を擦り付けるという卑怯な手段でよこした。それが秘かにおカネの下腹部付近を通して実を結んだのである。
おカネは、甚六に気づかれないよう作業の合間に、付近の野で手に入れた柔らかそうな枯草を使って、用を足すように見せかけながら、とにかくこまめにシメリを拭き取った。
「オラとしたことが、漆にでもかぶれたか・・・」
恥ずかしさでいっぱいになった。
「あぁイライラする、妙な臭いに乳まで張りよるわ」
さては先だって冷水につかりながら、指で擦りすぎたんではあるまいかと、しゃがんだ時に中を覗き見たりもした。
「あれ嫌だ。拭いたばかりというに、まだ出てきよる」
だがそれが、甚六の、何とも言えない不可解な行動で、その原因を知ることになる。
いつぞや、秋野法然まつりの宿になった、あの家の奥の間で呆れたことにまぐわい合っていた男女から発散されていた臭い・・・
それが今、女房のおカネの身体から発せられている。
ねめつけるように甚六はおカネの御居処を見て回った。
寝床に入ってからも、時々布団を持ち上げて、中から香り来る臭いのもとを探った。
そうしてとうとう、ある夜のこと、甚六がたまりかね
おカネの臭いがする部分に手を伸ばしてきたのである。
その時になって初めて、おカネはゴワゴワしていたものが何か、思いついたが、知らん顔でその場は通した。
添い遂げて初めて、我が女房のソレの様子がすっかり変わり果てていることに気づいた甚六。
下手に疑えば、せっかく嫁いできてくれた女房を手元から解き放つことにもなると、
己の中に沸き起こる悩乱に、わざと背を向け、素知らぬ顔をする哀れな甚六は、
ここで我妻を取り戻さねばという焦りから、尚更のこと委縮してしまっていた。
寝ぼけた拍子に触ったように見せかける甚六だったが、身に覚えのあるおカネは、それだけで身体を固くしてその場から逃げようとし、寝返りを打って夫に背を向けた。
夫婦は、息をひそめ背を向けながら夜の明けるのを待つようになっていった。
本人は気づかないようなふりをしていようとも、
庄衛門がおカネの衣服に浸み込ませたゴワゴワするものから発散される淫臭いという、
下腹部がもたらす温もりとシルで溶け出し、開いた胸元から立ち上る、或いはシル同士が交じり合い醸し出す粘りというものの刺激に
女としての本能からか、たとえそれが洗濯物に付着させただけの胤であっても性で感じてしまい、焦がれた男に対し、その懐かしさのあまり、身体の芯からごく自然に潤みが生じているのは確かだったからであった。
疑惑 庄衛門の言付け
この時代の、ましてや入沢村などという、ひとも通わぬ僻地に公民館などありようもない。
従って順番制によって祭りごとの宿番を務める以外、慶事 ことに寄り合いは仲間内の中で最も権力を持った家で行った。
足立家か長嶋家がそれにあたる。
何かにつけて席順は、上席に庄屋が座り、順次上役から席を詰め、端役などは座敷に入りきれなくて隣の板の間に坐することになっていた。
双方の庄屋の家は、それだけに豪勢で広々としており、門をくぐる前に既に端役などは射竦んでしまい、発言すらまともにできなかった。
それ故に、決まりごとはただ淡々と上座の控え役が庄屋の意に沿ってあらかじめ書き付けて置き、その書付を読み上げるのが常だった。
決まりごとの中の主なものに道普請や草刈、催事の日付などがあったが、あれほど忌み嫌うまぐわいや夜這いなどについては一切触れていない。
全てがこれ、きれいごとで済ませようとしていた。
従って常日頃、その寄り合いで決まった条項の履行が正しく行われているか、確かめて回るのは庄屋の役目となっていた。
誰もがよほどのことでもない限り、寄り付こうともしない甚六の家に、足立庄衛門はよく顔を出した。
顔を出しては、女房のおカネをからかった。
一言二言、寄り合いで決まった事柄を口にし、作法通り確認を取る。
庄屋の家に招かれ、上座の、睨め付けるような視線の中、決まり事を聞いて戻ってくる甚六は、その文言の一行文すら覚えてこれなかった。
極まりが悪くなった甚六は、それがどんな深夜帯であろうと、おカネが止めるのも聞かず鎌や鉈・鋸を持って血相を変え家を出て、心が休まるまでそれを振るった。
そんなことだから、おカネにすれば庄衛門の来訪は心強かったことは間違いない。
ただ、決まり事を一通り話し終わってその後、自然とシモの話に及び行くのが、何とも言い難かった。
普段は鳥や獣、木々や草花と会話を交わす以外、何の楽しみもない過疎の村で、隣の誰某がこのような卑猥なことをこっそりやっているなどと話を持ち掛けられると、顔はそっぽを向いていても耳を攲ててしまっていた。
気が付けば、ツッと庄衛門の手が伸び、おカネの大事なところを撫でているなどということも、一度や二度ではなかった。
思わず後づ去りするおカネに、屈託なく笑い飛ばし、股間をそれとわかるほど膨らませた状態で立ち去る庄衛門。
おカネは、茶の後始末をしながら、秘かに身を揉むしかなかった
なにしろ村から聞こえてくる噂話は、肝心な部分が真綿でくるんだような塩梅になっており、真のところは知りえなかったからであった。
「オラを気にかけてくださる」
卑猥なことであるにもかかわらず、むしろ良いほうに捉え、微笑ましく憎からず思ってしまうおカネがそこにいた。
甚六とおカネ夫婦の間に、滅多なことで営みなどない。
あるのは食べ物の心配と世間への愚痴ばかりだった。
たまに、ホッと一息ついてソニ気になりかけているというのに、
甚六は日ごろの疲れから後ろを向いて背を丸め、寝入ってしまっている。
とても淋しくて抱いてほしいなどと言い出せる雰囲気にはなれなかった。
野生動物の世界でもそうであるように、栄養も行き届かず、気持ちの中に何かに勝るゆとりすら持ち合わせていない甚六に、性の営みなどということは願っても無駄であった。
女房である前に、ひとりの女であることを忘れようと必死にもがく日々もあった。
庄衛門のソレは、物足りなさを必死に忍んでいたおカネにとって、むしろありがたい行為と言えた。
久しく忘れていた、芯部の熱くなる想いをおカネは楽しんだ。
こうしておカネは、遠間に庄衛門の姿を見届けると、相手がたとえ気づいてくれなくても、頭を下げ、姿が視界から消えるまで見送るように、自然になっていった。
「オラを見てた。また前を膨らませて・・・ フフッ」
庄衛門も、気づかないフリをしていながら実のところ、その姿がおカネの視線から外れるか外れないかの瀬戸際で、おもむろに豪快に野に向かって放つことをやってくれたりもした。
「アッ、あんなとこで・・・」
見ているうちにおカネの方ももよおして、しゃがみこんだりもした。
立ち去ろうとするおカネ、
すると、踵を返した庄衛門がおカネのシルシに引き寄せられるように、その痕を確かめに来る。
地面に伏せ、臭いや味を確かめる庄衛門。
物陰からこれを覗き見るおカネ。
ふたりだけに通じる秘密、全身が火照るような想いを、おカネは自身の中で楽しんだ。