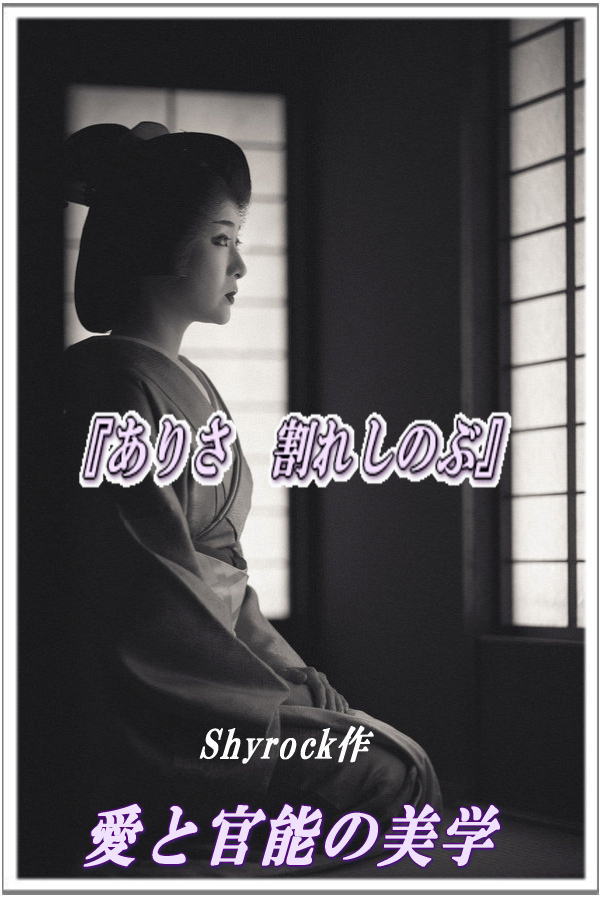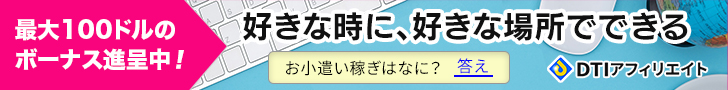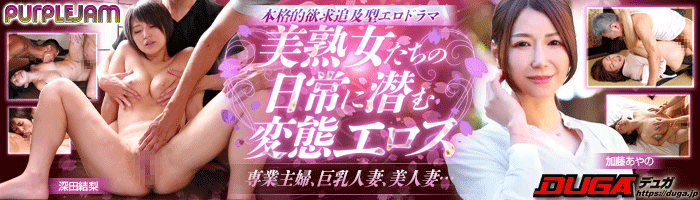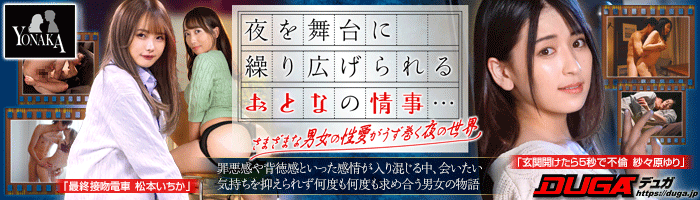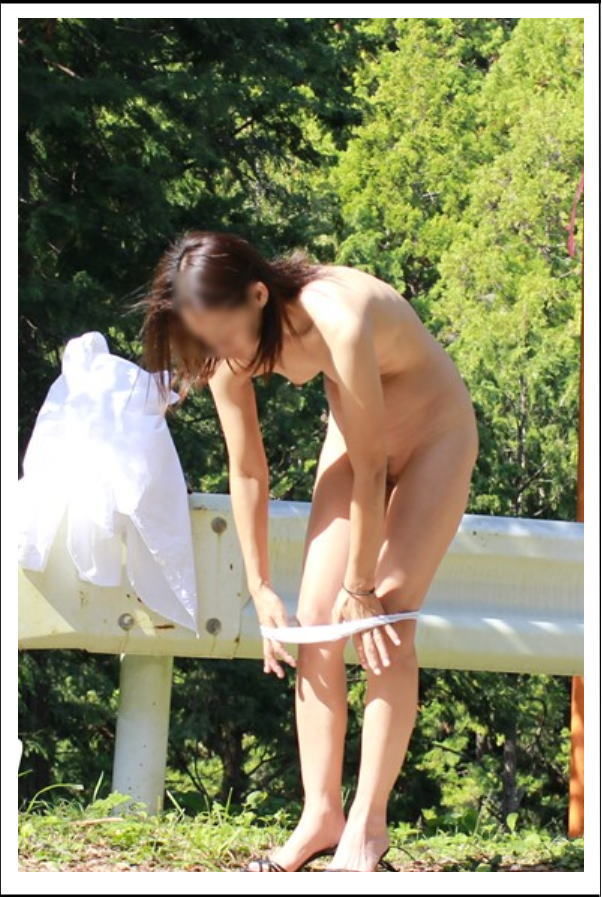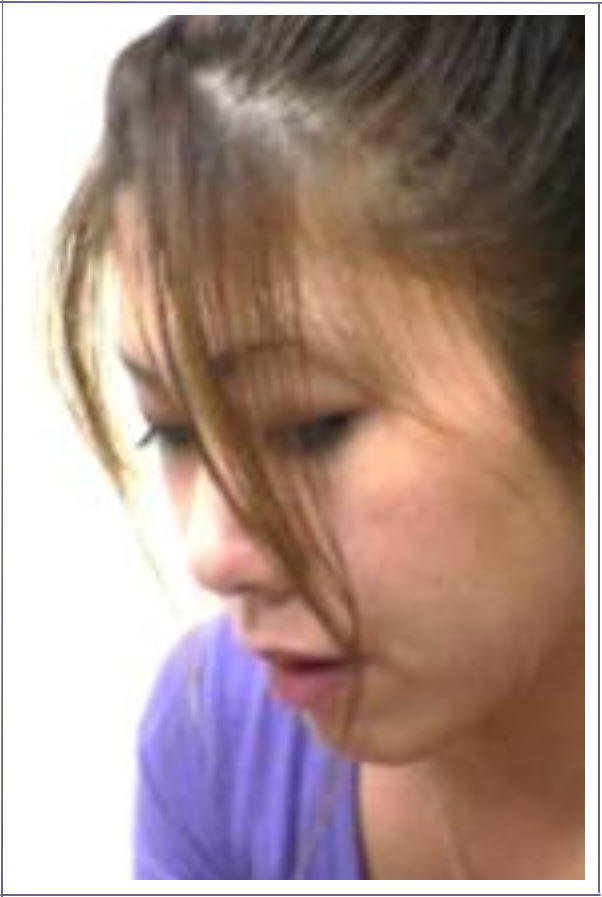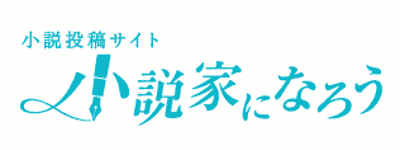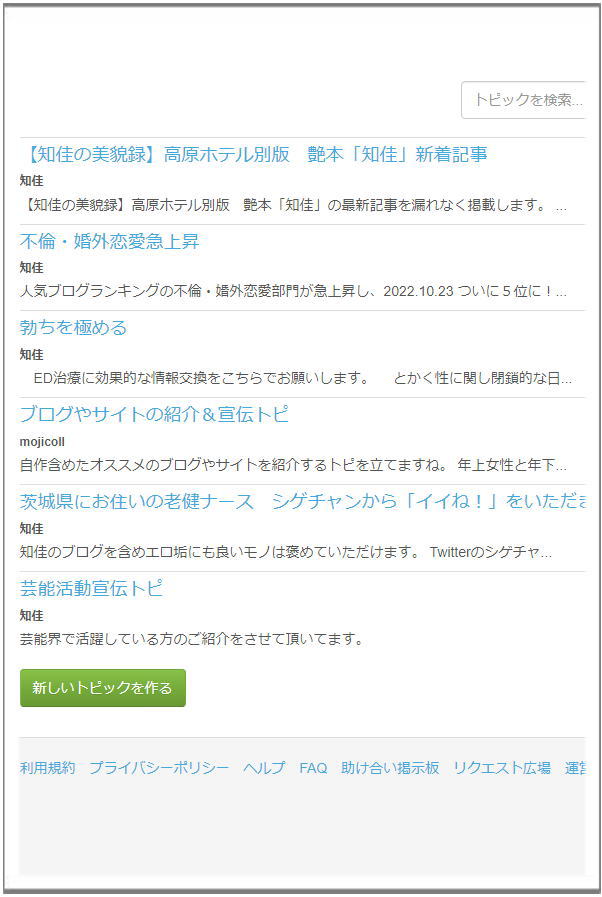「そんなぁ・・・そんなことしてまへん・・・」
「ひっひっひ、嘘ゆ~たらあかんで。何でも学生の下宿に入り浸りやったそうやな~?それやったら、ここをこないに触られたくらいやないな?もっとええことしたんやろ?」
「してしまへん・・・」
「嘘ゆ~たらあかん。ここに大きいもんを入れられたんやろ?ちゃうんか?どや?わしのとどっちが大きかった?」
「そんなん知りまへん・・・」
「どうしても知らんゆ~んやな?正直に白状したら堪忍したろて思てたけど、嘘つくんやったら、やっぱりお仕置きをせんとあかんわ」
丸岩はそう言いながら、布団からありさを引きずり出して、ズルズルと床の間まで連れていった。
「いや~!何しはるんどすか!?堪忍しておくれやす~!」
「何をて、決まってるやないか?お仕置きや、お仕置き」
丸岩は嫌がるありさを予め用意していた麻縄で、床の間の柱に立位のまま縛り付けてしまった。
さらに日本手拭いで猿ぐつわまで噛ませて口を封じてしまった。
「ううっ!ううう!」
「あんまり大声出されて、女中がびっくりして飛んで来ても困るさかいな~。ひっひっひ・・・」
柱に後手縛りでしかも猿ぐつわと、戒めを施されてしまったありさが自由にできるのは、むっちりとした2本の足だけであった。
丸岩はありさを縛ったままにしておいて、押し入れから奇妙な道具を持ち出して来た。
どうも、台所で使う『すり鉢』と『すりこぎ』のようだ。
そして包装紙から、こげ茶色の『芋』らしきものを取り出して来た。
声の出せないありさは、目を丸くしてその得体の知れないものを見つめた。
(あれは芋みたいやけど、一体どうするつもりやろか・・・)
丸岩はこの後、驚いたことに、すり鉢に芋らしきものを入れて、すりこぎで潰し始めたのだ。
ある程度潰れると、今度はグルグルと掻き混ぜた。
まさかこんな座敷で料理を作るわけもなかろうに、丸岩は一体何をしようと言うのだろうか。
充分にとろみが出るまで混ざった頃、丸岩はニタリと嫌らしい笑みを浮かべた。
「ふっふっふ・・・、ありさ、これ何か解かるか?これは
山芋や。食べたことあるやろ?
山芋はな、滋養強壮の食べもんとして昔から有名やけど、他にも女の淫薬としても有名なんやで。知らんかったやろ?今からたんと食べさせたるさかい、楽しみにしときや、ひっひっひ~。ああ、もちろん、下の方のお口に食べさせたるさかいな。ぐっふっふっふ・・・」
丸岩はそういいながら、すり鉢を持って、ありさのそばににじり寄った。
(うぐうぐうぐっ!)
顔を横に振り拒絶の態度を示すありさではあったが、身体を拘束されてしまった今逃れる術はなかった。
丸岩はすり鉢から
山芋を指でひとすくいし、ありさの顔に近づけた。
「ひっひっひ、ありさ、お前のアソコにこれをたっぷりと塗ったるさかいな。どうなるか楽しみにしときや。あ、そやそや、その腰巻きちょっとじゃまやさかい、取ってしもたるわ。ぐっふっふ・・・」
ありさの腰を包む布地はパラリと床に落ちて、着衣は肌襦袢だけとなってしまった。
しかし下半身を覆うものはすでに何もなく、無防備な状態で丸岩の異常な欲望の前に晒されてしまった。
必死に膝を閉じ合せ、抵抗を試みるありさであったが、男の力には抗うべくもなく、その侵入を許すことになってしまった。
丸岩の指はありさの真直ぐに伸びた一本道のような亀裂に触れた。
「ぐふふふ・・・」
「ううっ!」
丸岩はニヤニヤと卑猥な笑みを浮かべながら、丁寧に陰唇部分へ塗り始めた。
続いて、実の包皮を開いて剥き出しにし、実に擦りつけるように塗り込めた。
「さてさて、ほんなら、次はこのかいらしい穴の中も、たっぷりと塗ったるさかいな。ぐひひひ・・・」
山芋が滴る指は、ついに裂け目の奥深くにも侵入を開始した。
内部の襞のある部分はその感触を楽しむかのように、特に念入りに摩擦を加えるのであった。。。
「ううっ、ううっ・・・ううっ・・・」
秘所が焼けるようにカーッっと熱くなって来た・・・
そして次第に激しい痒みがありさを襲い始めていた。
額からは大量の唐辛子でも食べたかのように、大粒の汗が吹き出していた。
「ぐっふっふ・・・どうや?痒いんちゃうんか?」
ありさは苦悶に歪んだ顔を縦に振った。
「せやけど、しばらくはそのまま我慢してもらおか。よその男を咥え込んだ罰(ばち)やさかい、それぐらいは辛抱してもらわんとあかんわなぁ」
「ぐっ・・・ううう・・・」
丸岩は底意地の悪さを露骨にありさにぶつけたのだった。
とにかく痒くて堪らない・・・そして熱い・・・
(ああ、辛い・・・)
ありさは身を捩じらせて、
ムズ痒さと懸命に戦ったのだった。
しかし時間が経つに連れ、我慢も限界に近づいていた。
狂いそうなほど痒い。
「うぐうぐうぐ~っ!」
ありさは
猿轡を噛まされて叫べない苦しさを、態度で現すしかなかった。
身体からは
大量の脂汗を流し、腰を精一杯に捩り出した。
ありさの股間からは、おびただしい愛液が
山芋と交じり合って太股がボトボトになるほど流れ出していた。
「どや?ぼちぼち掻いて欲しいんとちゃうんか?」
最初その言葉にも顔を背けて無視をしていたありさであったが、ついに耐えかねて
屈服の態度を表わしたのだった。
「ふふふ、首を縦に振ったな?ふっふっふっ、そうかそうか。そんなに痒いんか?よっしゃ、ほな、ぼちぼちええもん咥えさせたるわ。ぐっひっひ・・・」
丸岩は横に置いていた木箱から、奇妙な形の道具を取出した。
ありさはそれを見た瞬間、顔が青ざめてしまった。
それもそのはず、丸岩の取出した道具というのは、江戸時代から伝わる木製の「
張形」で、周囲が異常に太く、一般男子のそれよりもふた周りぐらいは大きい代物であった。
「ありさ、ほんとやったら、わしのもん咥えさせたるとこなんやけどな、わしまでかいなるのんかなわんさかいに、代わりにこの太いもんでしっかり擦ったるわ。気持ちええで・・・ぐひひひ・・・」
本来のありさならば、そのおぞましい形状の
異物を脚で蹴ってでも拒絶していたところであろうが、今はそんなことができる状態ではない。
何でもいい、とにかく身体の痒みを鎮めるものが欲しい。
そんな思いから、ありさは屈辱に身を焦がしながら、丸岩の差し出す淫猥な
異物を受け入れたのであった。
「うう、うぐぐ・・・うううっ!」
激しい
身体の火照りと痒みのせいで、愛液と
山芋の混じり合ったものはおびただしく溢れ太股まで伝っている。
丸岩は舐めるような目つきでありさの苦悶の表情を楽しみながら、太い
張形をゆっくりと沈めて行った。
(ズニュ・・・ズズズ・・・)
「ううっ~~~!」
丸岩は
張形を深く押込んだあと、手を休めてしまった。
痒みを止めるために、不本意ながら丸岩の手を借りなければならないというのに。
丸岩は不敵に笑った。
「ふっふっふ、わしの役目はここまでや。痒みを止めたかったら、自分で腰をくねらしてごりごりと擦りつけることやな。ふあっはっはっは~!」
何という底意地の悪い仕打ちであろうか。
空腹の者にご馳走をちらつかせておいて、『お預け』と言っているようなものだ。
「くうっ・・・うっ・・・ううう・・・」
「痒いか?ふふふ・・・、はよ、腰を動かさな狂うてしまうんちゃうか?はっはっは~!」
ありさは脂汗を流しながら必死に耐えてはいたものの、肉体的にすでに限界に達していた。
挿し込まれた
張形に自ら腰を振りながら貪るように食らいついたのだった。
「う~っ、う~っ、ううう~っ!」
「はっはっは~!とうとう腰を振り出したか。よっしゃよっしゃ、それでええのや。もう二度と浮気なんかしたらあかんのやで?ええなぁ」
丸岩は凄みながら、ありさの顎を指で摘むように持ち上げた。
そして止まっていた
張形の反復運動を再開させた。
ありさは身体を弓なりに反らせ、いつしか快楽の園をさまよい始めていた。
「がっはっは~、なんぼ拒んでも、女の性ちゅうもんは哀しいもんやなあ~。わっはっはっは~」
「うぐ・・・ううう・・・ううっ!」
「ありさ、お前はわしのもんや。他の男には指一本触れさせへん。これでよう解ったなぁ?ふっふっふ・・・」
人前では滅多に涙を見せないありさではあったが、ひとり床に就くといつも泣いていた。
「俊介はん、会いとおすぅ・・・、あんさんに会いとおすぅ・・・」
いくらさだめとは言っても、好きな男と引き離されて、嫌いな男に添わねばならないことがとても悲しかった。
自分にさだめられた籠の鳥のような身の上を呪わしくさえ思った。