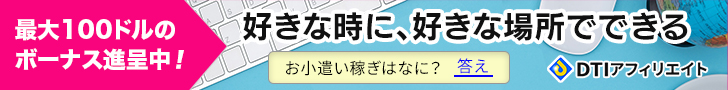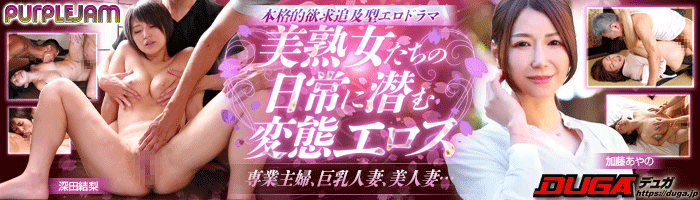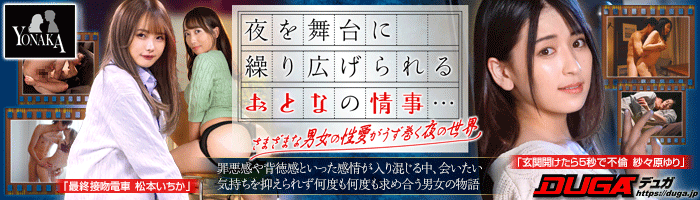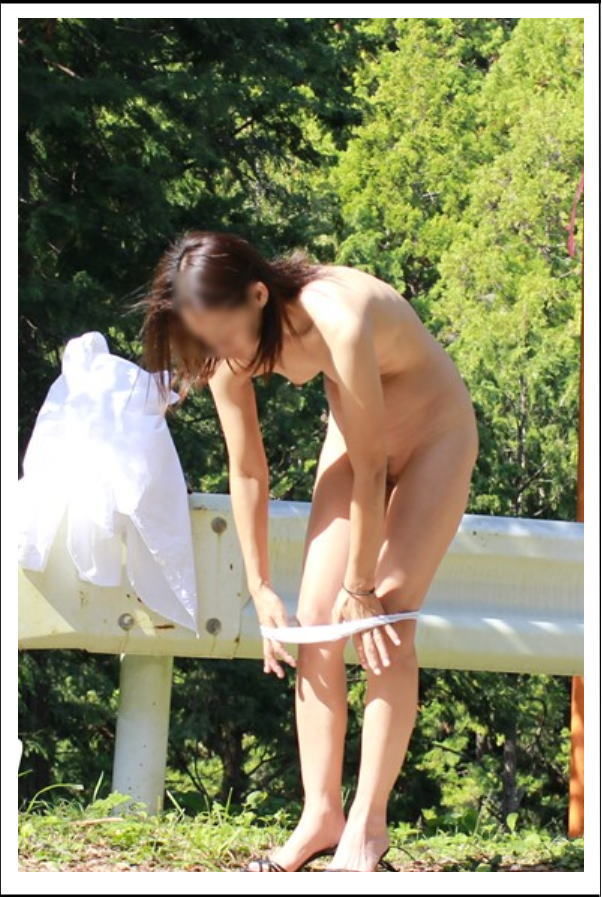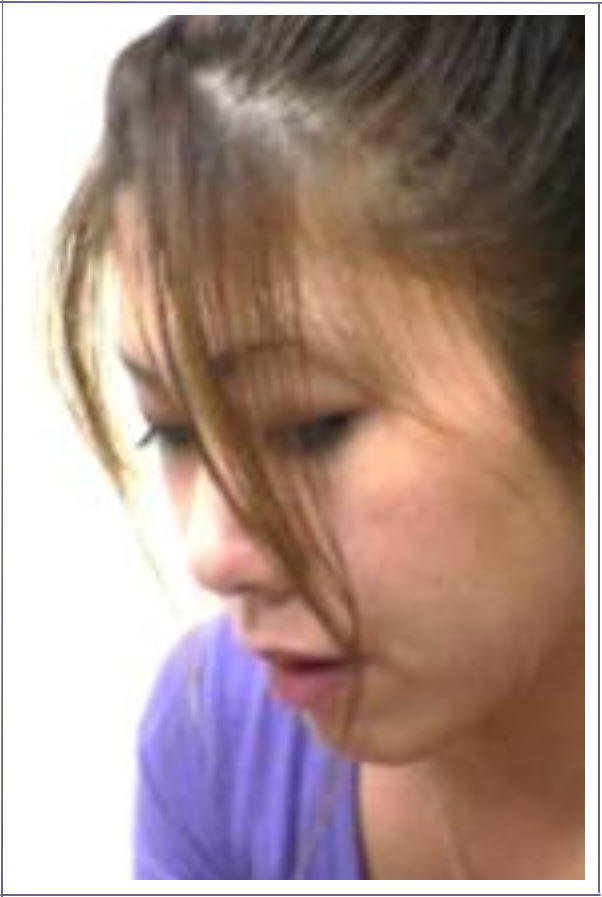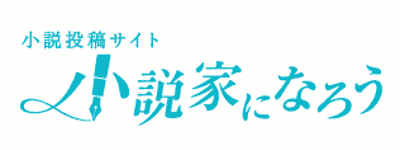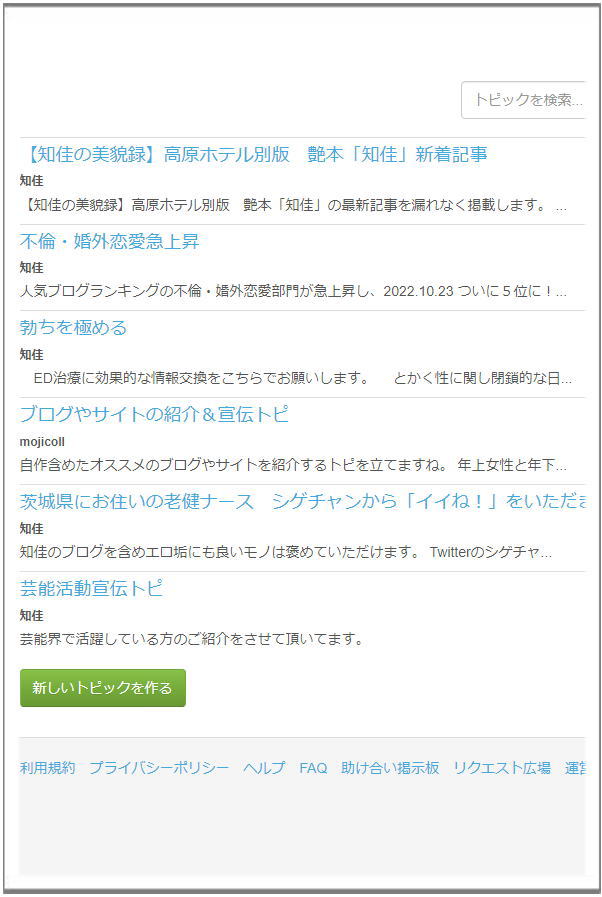村の衆の餌食になった和子
 野辺の送りを、和子は最初に出会った時に爺様が誘い込んでくれた田の畔でひっそりと行った。
野辺の送りを、和子は最初に出会った時に爺様が誘い込んでくれた田の畔でひっそりと行った。不思議と涙は出なかった。
通夜が済むまで和子は、それでも爺様の近くにいようと離れの小屋に身を潜ませていた。
爺様とかくれんぼに見せかけ心なしか契った思い出の場所である。
だがこの日、本葬が始まると和子は密かに家を抜け出してこの場所に急いだ。
親戚一同が出そろう婆様の家には、いかに世間知らずとはいえ到底顔を出すことはできなかった。
爺様を見送りながら和子は、出会った時から亡くなる直前までのことを思い起こしていた。
爺様を揺り動かしたのも、自身がそれにつき従ったのも、深く考えをめぐらせると行き着く先はお互いへの嫉妬だった。
爺様が誰に嫉妬して和子を苛ませていたかというと、それこそが爺様が激怒した寝物語の男ではないかと思われた。
それを言うならわたしは誰に向かって嫉妬していたのかと、見送りの列を見ながら和子は考えた。
遥か昔に爺様がしでかした女遊びに嫉妬したかと問うてみた、そんなことなら男であれば誰でもやっていることと答えは簡単に返ってきた。
全てが終わった今となっては、もうどうでも良いことのように思われた。
遠くでは、野辺の送りが終わって三々五々参列者が婆様の家に引き返して来ていた。
着の身着のまま田んぼの畔で見送りをしていた和子にも、容赦なく夏の日差しが降り注ぐ。
あっという間に汗みどろになっていった。
着替えや荷物を受け取りに婆様の家に引き返すことなど出来よう筈もないことがわかる。
目立たぬよう、藪に身を潜めながら和子は、僅かでも平野が開けた方向に向かって移動を始めていた。
あの開けた山間を抜ければ、元居た市内に帰れるんじゃないだろうかと和子は思った。
何が疎いかと問われたら、このあたりが一番疎いかもしれないと、この後応えることになる。
和子が住む市内は、村を流れる川の下流域に広がる平野でなければならないが、和子がこの時向かった先は廃村などとは真逆の隣村に向かう峠越えの方向だった。
従って和子は、更に山の奥へ奥へと歩を進めていることになる。
朝のあの騒ぎである。
前日の、婆様がこっそり小屋に運んでくれたおにぎりの夕食以降、何も口に入れてはいなかった。
空腹より、村人に知られることなく抜け出すことだけを考えて歩む和子に、空腹感はなかった。
峠にさしかかると道は一気に狭くなった。
農免道が行き止まりになった代わりに林道が伸びていることなど和子が知る由もなかった。
うっそうとした杉木立に囲まれた山道は、真昼であっても薄暗い。
ましてや陽も暮れようとしている山道である、足元もおぼつかなくなっていった。
道に迷いそうになり、登りの中間にある分岐点でとうとう和子は歩みを止めた。
その時になって初めて、市内から来た道と違うことに気が付いたが、今日一日どこを歩いていたのかすら思い出せないでいた。
道を知らない以上、引き返す勇気すら湧いてこなかった。
仕方なく和子は、疲れていたこともあって路傍の石に腰掛け背を山際にもたせ掛けてまどろんだ。
藪蚊に悩まされながら眠りについた夢の中で和子を呼ぶものがあった。
爺様のようでもあり、足蹴にしてきた男たちであるようにも見えていたのもが、時間とともに次第にはっきりと姿を現して和子に覆いかぶさってきた。
和子が、己の欲得のため蹴落としてきた女たちの亡霊のような気がした。
わけても美紀は、呪いの言葉を吐きつつ一心に和子の首を締めてきていた。
あれほど控えめだった美紀の顔が、その恨みで権化と化している。
あまりの恐怖に、和子は飛び起き、一散に訳も分からぬ方向に向かって走り出していた。
逃げる途中、何度も転んだし、追いかけてきた亡霊に組み伏せられそうになった。
火事場の馬鹿力というのがあるが、この時の和子はまさにそれに似た力を使って追う怪物から逃げていた。
暗闇の中で追ってくる権化に、ついに捉えられた和子は、恐怖で潮を吹き、気を失った。
爺様の野辺送りが終わった後は爺様宅に村中の人々が集まって婦人たちが焚きだした精進料理を肴に酒盛りが行われていた。
村の葬儀とは、およそこの方式で昔から変わることなく営まれていた。
個人が無類の酒好きとあって、位牌の前で今回は特に盛大に酒盛りが行われた。
散々飲み食いした村の衆の、誰から云い出したわけでもなく姿を消した、あの爺様を墓場に送った和子を追おうという話が出た。
場の雰囲気を盛り上げようとした好きものの女房達がこれを面白半分にたきつけた。
なにひとつ娯楽もなく、毎日重労働に明け暮れる村であってみれば、唯一の楽しみと言えば隠れ潜んで行う凌辱と乱交であった。
村の女子が生贄になるわけではない。
街から来た、好きものの女が餌食となるだけの話である。
たとえ間違って孕んだとしても痛くも痒くもない。
いつもの如く、密かに処分して口を拭ってしまえば、村で起きたことは誰にも知られる心配はなかった。
どんなふうに凌辱を受けるのか、女房たちにとっても知りたくて、覗きたくて仕方がない。
だから酔いに任せて女房達は男どもにたきつけた。
酔えば色事の話が出るのは古今東西同じである。
情交に至っては、足入れが度々行われる村とあって誰も彼もその良さを知り尽くしている。
耳をそばだてているだけで、疼いて仕方がないとつぶやき、下腹部を宴席で晒しそうになる女もいたほどだった。
村故に、あの不文律が隅々まで働いており、和子は見失うことなく誰かが、こういうこともあろうかと見張り続けていた。
今こそ爺様に気兼ねなく爺様以外手つかずの女が抱けると、日頃女子に飢えていた若い衆は勇みきった。
宴席の座卓の下で、この話でいきり立った棹を好きものの人様の女房に見せつける輩もいるほどだった。
見せつけられた女は、そっと晒してくれた男をこっそりつねった。 「同じ気持ちよ」と伝えていた。
集団心理は抑えられないものとなった。
夕やみを縫って追手が秘かにかかった。
杉木立の中で錯乱状態にある和子を押さえ込んだのも、美紀の亡霊ではなく村の衆だった。
惑乱中、何度か村の衆は和子を押さえ込み勇みきったひとりが挿し込もうとしたが抵抗にあって成し得なかった。
和子と違って夜目が効く村の衆は暗闇でも和子の肢体を十分に確認できた。
だからこそ、襲いかかり 次々と剥ぎ取られて剥き出しになった見事な肢体に舌なめずりしていた。
組み敷かれ、押しのけようとしたときには既にひとりの男の挿し込みが始まっていたのである。
潮を吹いたのはその真っ最中であった。
最初挿し込みを図った男はしたたかに和子の噴き出した潮に股間を濡らすこととなる。
その時肩口や乳房を押さえ込んでいた男が気を失った和子を軽々と抱え上げ、山の奥の、かつての廃村の住人が住んでいた廃屋に、山を越え連れ込んだ。
集団がそのあとに続いた。
和子が噴き出した潮の臭いがまず、闇夜の中で凌辱に牙をむく男衆の欲情を掻き立てた。
濡れそぼった衣服が剥ぎ取られると、それを脇にいた男たちが一斉にひったくるようにして持ち去り、各々が戦利品の臭いを嗅ぎ、舐めた。
股間に押し当て、未だ乾かない潮を己の棹や皺袋に刷り込むものまでいた。
欲情した男たちの、その時の和子を巡る騒ぎは、例えば足の指を舐めるもの、耳たぶを齧るものなど まるで腐肉を食い漁るハイエナの如くであった。
爺様がいたればこそ、和子はこれまで安穏として暮して行けたのである。
気を失ってはいたものの、その夜和子に向かって、村の男衆は次々と襲いかかり情欲を体内に注ぎ込んで、明け方近くに去っていった。
ポチッとお願い 知佳


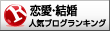
恋愛・結婚ランキング
google51904d4c43421b58.html
BingSiteAuth.xml
- 関連記事
-
- 下腹部を晒しそうになった女房の性
- 村の衆の餌食になった和子
- 爺様が逝く