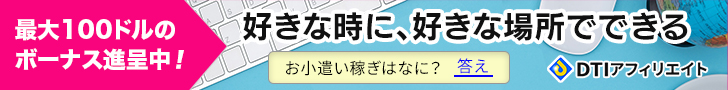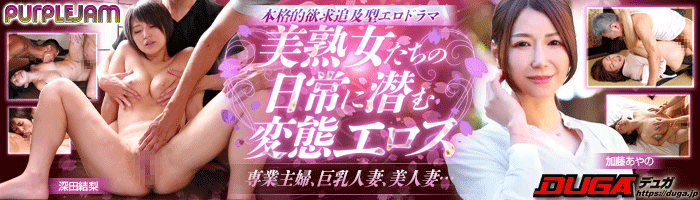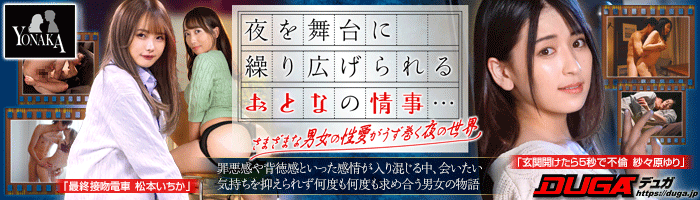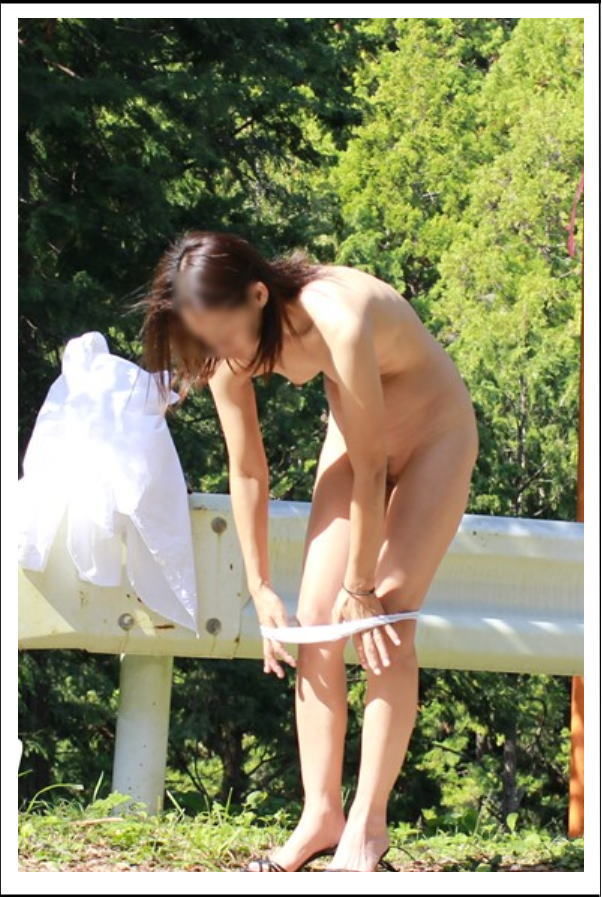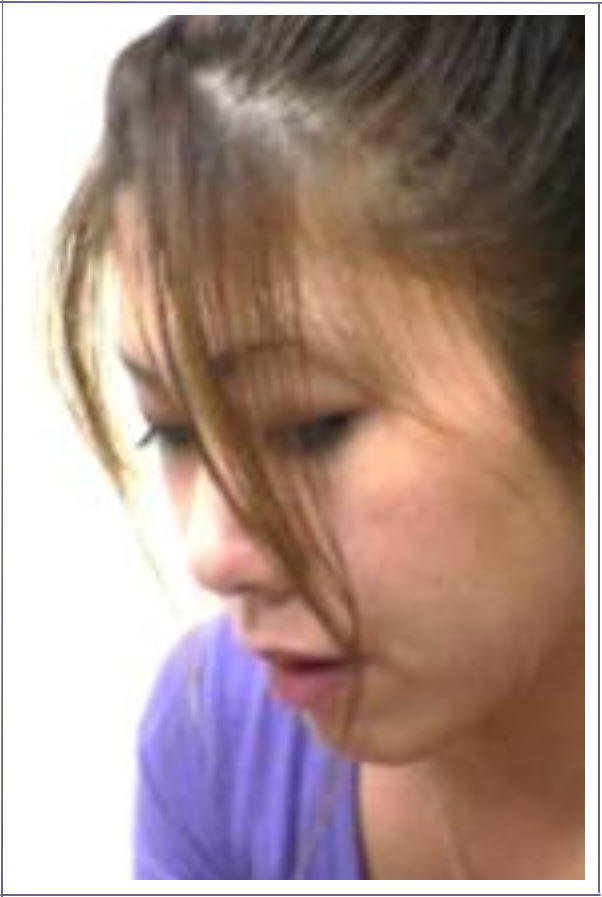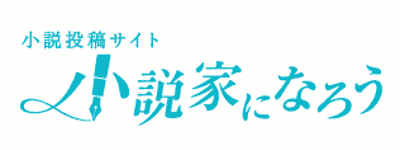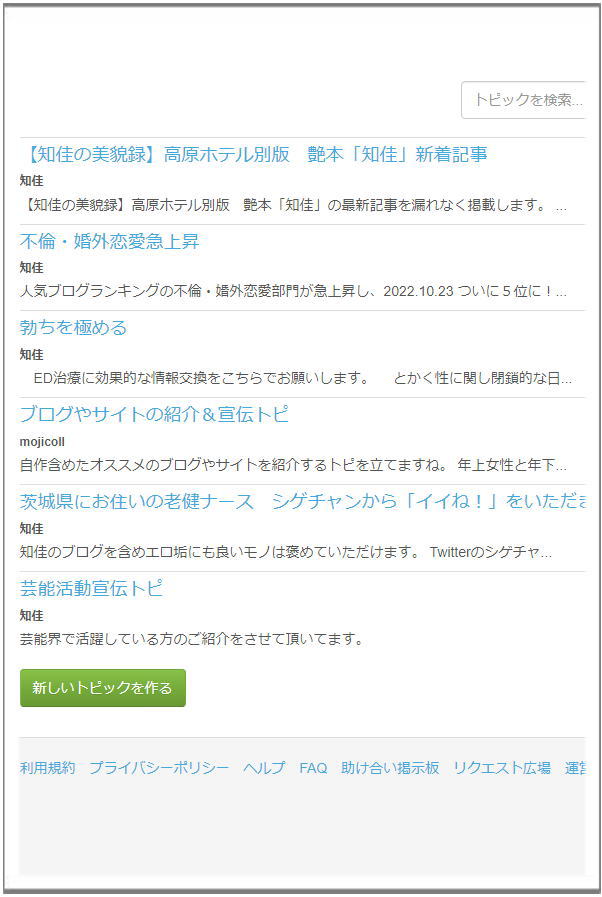疑惑 庄衛門の言付け
この時代の、ましてや入沢村などという、ひとも通わぬ僻地に公民館などありようもない。
従って順番制によって祭りごとの宿番を務める以外、慶事 ことに寄り合いは仲間内の中で最も権力を持った家で行った。
足立家か長嶋家がそれにあたる。
何かにつけて席順は、上席に庄屋が座り、順次上役から席を詰め、端役などは座敷に入りきれなくて隣の板の間に坐することになっていた。
双方の庄屋の家は、それだけに豪勢で広々としており、門をくぐる前に既に端役などは射竦んでしまい、発言すらまともにできなかった。
それ故に、決まりごとはただ淡々と上座の控え役が庄屋の意に沿ってあらかじめ書き付けて置き、その書付を読み上げるのが常だった。
決まりごとの中の主なものに道普請や草刈、催事の日付などがあったが、あれほど忌み嫌うまぐわいや夜這いなどについては一切触れていない。
全てがこれ、きれいごとで済ませようとしていた。
従って常日頃、その寄り合いで決まった条項の履行が正しく行われているか、確かめて回るのは庄屋の役目となっていた。
誰もがよほどのことでもない限り、寄り付こうともしない甚六の家に、足立庄衛門はよく顔を出した。
顔を出しては、女房のおカネをからかった。
一言二言、寄り合いで決まった事柄を口にし、作法通り確認を取る。
庄屋の家に招かれ、上座の、睨め付けるような視線の中、決まり事を聞いて戻ってくる甚六は、その文言の一行文すら覚えてこれなかった。
極まりが悪くなった甚六は、それがどんな深夜帯であろうと、おカネが止めるのも聞かず鎌や鉈・鋸を持って血相を変え家を出て、心が休まるまでそれを振るった。
そんなことだから、おカネにすれば庄衛門の来訪は心強かったことは間違いない。
ただ、決まり事を一通り話し終わってその後、自然とシモの話に及び行くのが、何とも言い難かった。
普段は鳥や獣、木々や草花と会話を交わす以外、何の楽しみもない過疎の村で、隣の誰某がこのような卑猥なことをこっそりやっているなどと話を持ち掛けられると、顔はそっぽを向いていても耳を攲ててしまっていた。
気が付けば、ツッと庄衛門の手が伸び、おカネの大事なところを撫でているなどということも、一度や二度ではなかった。
思わず後づ去りするおカネに、屈託なく笑い飛ばし、股間をそれとわかるほど膨らませた状態で立ち去る庄衛門。
おカネは、茶の後始末をしながら、秘かに身を揉むしかなかった
なにしろ村から聞こえてくる噂話は、肝心な部分が真綿でくるんだような塩梅になっており、真のところは知りえなかったからであった。
「オラを気にかけてくださる」
卑猥なことであるにもかかわらず、むしろ良いほうに捉え、微笑ましく憎からず思ってしまうおカネがそこにいた。
甚六とおカネ夫婦の間に、滅多なことで営みなどない。
あるのは食べ物の心配と世間への愚痴ばかりだった。
たまに、ホッと一息ついてソニ気になりかけているというのに、
甚六は日ごろの疲れから後ろを向いて背を丸め、寝入ってしまっている。
とても淋しくて抱いてほしいなどと言い出せる雰囲気にはなれなかった。
野生動物の世界でもそうであるように、栄養も行き届かず、気持ちの中に何かに勝るゆとりすら持ち合わせていない甚六に、性の営みなどということは願っても無駄であった。
女房である前に、ひとりの女であることを忘れようと必死にもがく日々もあった。
庄衛門のソレは、物足りなさを必死に忍んでいたおカネにとって、むしろありがたい行為と言えた。
久しく忘れていた、芯部の熱くなる想いをおカネは楽しんだ。
こうしておカネは、遠間に庄衛門の姿を見届けると、相手がたとえ気づいてくれなくても、頭を下げ、姿が視界から消えるまで見送るように、自然になっていった。
「オラを見てた。また前を膨らませて・・・ フフッ」
庄衛門も、気づかないフリをしていながら実のところ、その姿がおカネの視線から外れるか外れないかの瀬戸際で、おもむろに豪快に野に向かって放つことをやってくれたりもした。
「アッ、あんなとこで・・・」
見ているうちにおカネの方ももよおして、しゃがみこんだりもした。
立ち去ろうとするおカネ、
すると、踵を返した庄衛門がおカネのシルシに引き寄せられるように、その痕を確かめに来る。
地面に伏せ、臭いや味を確かめる庄衛門。
物陰からこれを覗き見るおカネ。
ふたりだけに通じる秘密、全身が火照るような想いを、おカネは自身の中で楽しんだ。