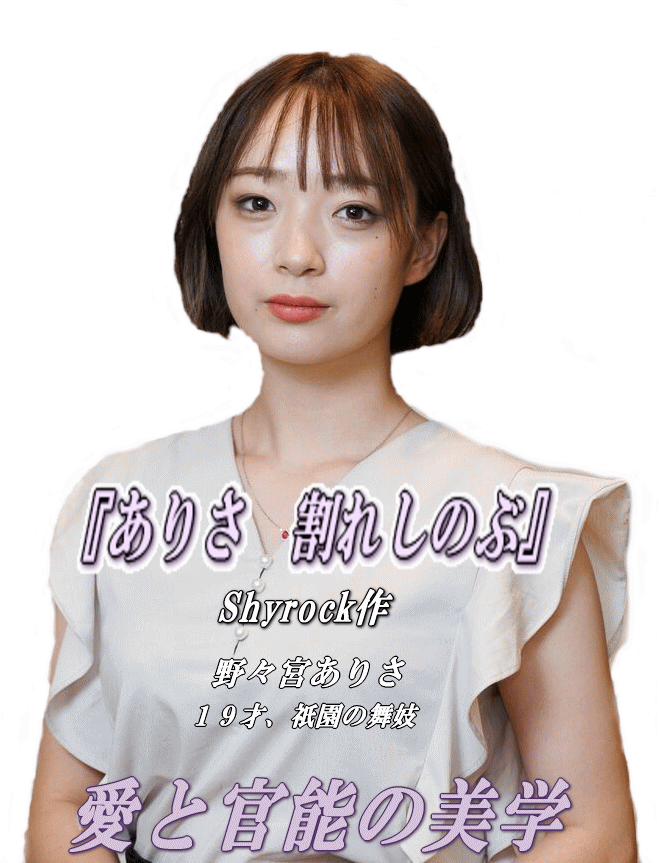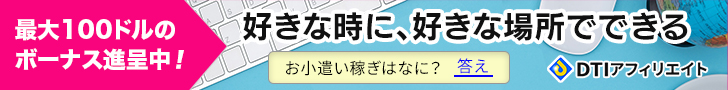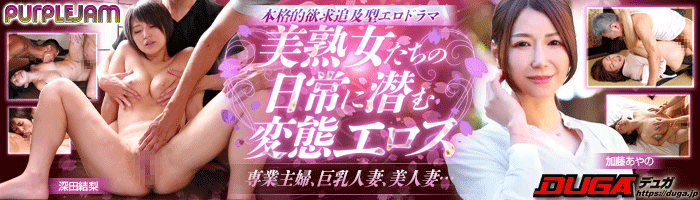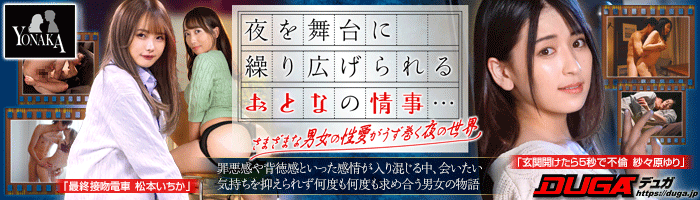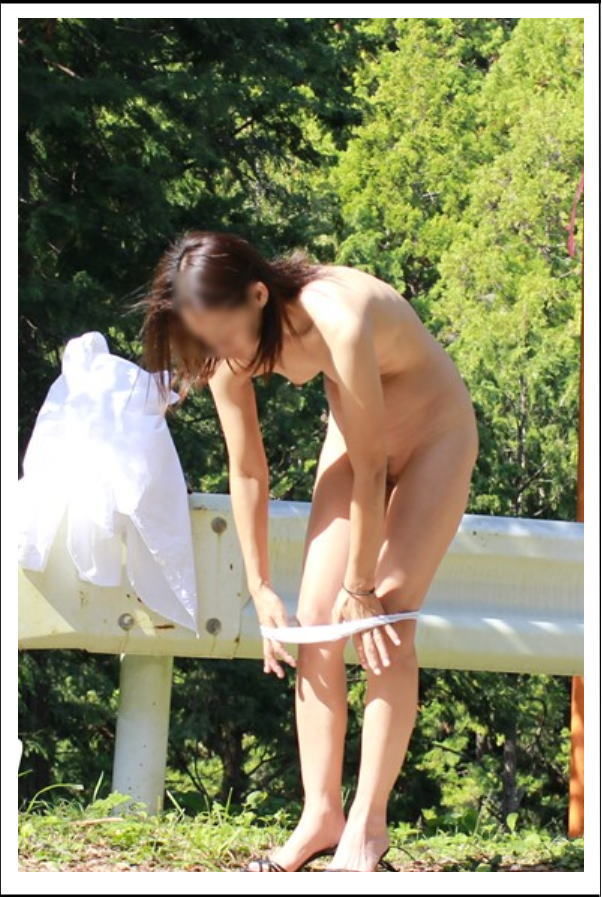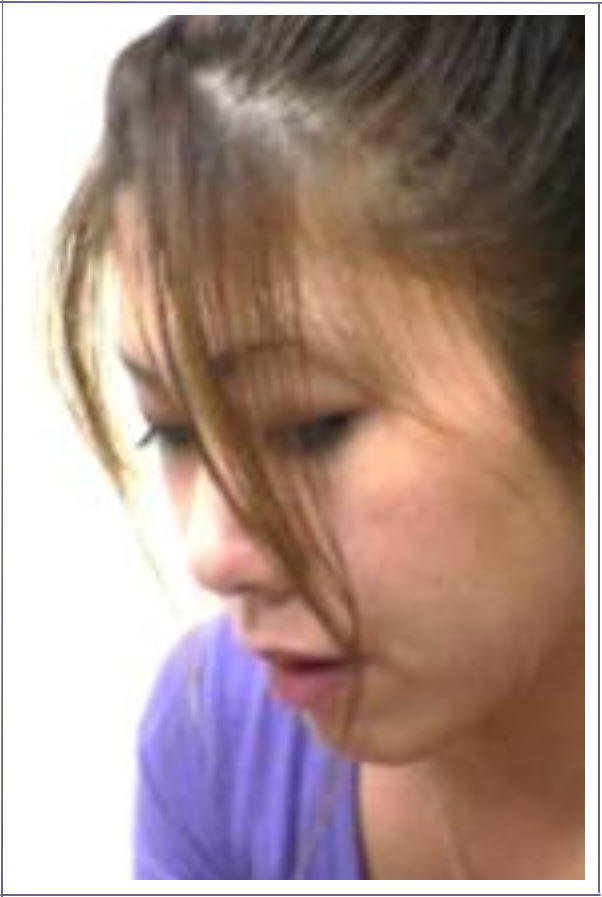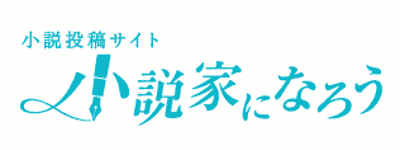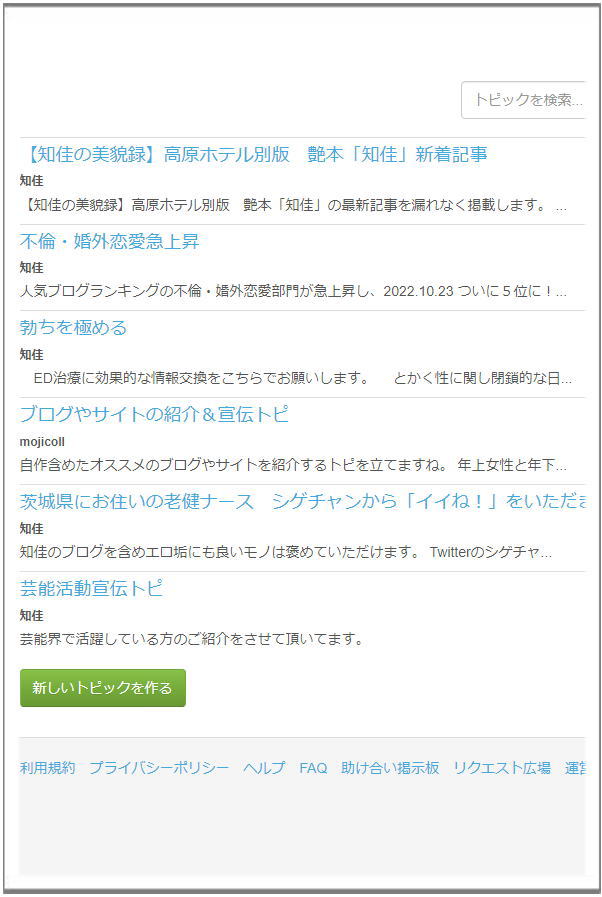官能舞妓物語
官能舞妓物語 image
主な登場人物
image
主な登場人物
野々宮ありさ 十九才、祇園の舞妓
本村俊介 二十一才、K都大学四回生
昭和初期。小雨がそぼ降るうっとうしい梅雨の日暮れ時、ここは京都木屋町。
高瀬川を渡って祇園に向うひとりの舞妓の姿があった。
すらりとしたいでたちで目鼻立ちの整ったたいそう美しい舞妓で、その名を〝ありさ〟と言った。
衣装は舞妓らしく実に華やかなもので、上品な薄紫の着物には一幅の名画を思わせる錦繍が施してあった。豊かな黒髪は〝割れしのぶ〟に結い上げられ、菖蒲の花かんざしが彩りを添えていた。
歳は十九で舞妓としては今年が最後。年明けの成人を迎えれば、舞妓が芸妓になる儀式「襟替え」が待っている。襟替えが終われば新米ではあっても立派な芸妓である。
そんなありさに、早くも「水揚げ」(舞妓が初めての旦那を持つ儀式)の声が掛かった。
稽古に明け暮れている時期はお座敷に上がることもなかったが、踊りや三味も上達して来ると、やがて先輩の芸妓衆に混じって何度かお座敷を勤めることとなった。
そんな矢先、ある財界大物の目に止まり、声掛かりとなった訳である。
だが、ありさは「水揚げ」が嫌だった。好きでもない人にむりやり添わされることなどとても耐えられないと思った。しかし芸妓や舞妓はいつかは旦那を持つのが慣わしだし、それがお世話になっているお茶屋や屋形への恩返しでもある。
旦那が見初めれば、芸妓・舞妓には選択権はなく、お茶屋や屋形の女将の意向に従うのが当たり前。それが祇園の掟。
そして今夜が、その辛い「水揚げ」の日だ。
雨のせいもあったろうが、ありさはおこぼがいつもより数倍重いように感じた。
【注釈】水揚げ
今は少なくなったが、芸・舞妓は旦那と呼ばれるスポンサーを持つのが普通とされていた。
水揚げとは、舞妓が初めての旦那を持つ儀式の事。
大昔は、旦那の選択権は芸・舞妓には無く、旦那が見初めれば、お茶屋や屋形の女将、
男衆が言いくるめて、強制的に添わされた。
水揚げには大きなお金が動くから、屋形側から少しでも条件の良い旦那にお願いをする事もあったようだ。
ただ、現在の祇園には「水揚げ」そのものが無いので注意を。
現在では、客がある舞妓の旦那になりたいと願っても、その舞妓が旦那を持ちたいと思わない限り、それは叶わぬ夢に終わることになる。 今の祇園では、旦那云々というよりも、普通の恋愛としてとらえている芸・舞妓が多いように聞く。事実、落籍されて(ひかされて…芸・舞妓を辞めての意)、そのまま結婚してしまう例も多くなった。
ありさが高瀬川を東に渡り終えた時、急におこぼの鼻緒がプチン・・・と切れてしまった。
「あぁん、いややわぁ、鼻緒が切れてしもた・・・、どないしょぅ・・・」
屈んで足元を眺めて見たがなすすべも無く困り果てた。
白足袋も鼻緒が切れた拍子に足が地面に滑り落ちて、つま先が少し濡れてしまったようだ。
途方に暮れていたら近くを通り掛かった青年が声を掛けて来た。
「どうしたのですか?」
ありさは声がした方向をそっと見上げた。
そこには優しそうな眼差しの鼻筋の通った背の高い青年が立っていた。
角帽、詰襟、下駄のいでたちから見て大学生のようだ。
「はぁ、それがぁおこぼの鼻緒が切れてしもたんどすぅ・・・」
「それじゃ僕に任せなさい」
青年はそういってポケットから白いハンカチを取出し、長身を折り曲げてありさの足元に屈み込んだ。
そのため雨は番傘を差せない青年の背中を濡らした。
「あ、すんまへんなぁ。せやけど、お宅はん、雨に濡れますがなぁ」
ありさは慌てて、自分の傘を青年の頭上にかざした。
遠くから見れば、相合傘の中で芸妓と大学生がいったい何をしてるのだろう・・・と、きっと奇異に感じたことであろう。
青年は人目も気にしないで、懸命にハンカチを鼻緒代わりに結わえ付けた。
見ず知らずの自分のために、雨に濡れながら鼻緒を結わえてくれる青年の横顔を、ありさはじっと見詰めていた。
「あのぅ…、お宅はん、学生はんどすなぁ?」
「ええ、そうですよ」
「その帽子の印からして、K都大学ちゃいます?」
「よく分かりましたね。そうですよ、今4回生なんです」
「そうどすか、えらいんやなぁ・・・」
「そんなことないですよ。それにしても可愛い足だなあ」
「えぇ?うちのおみやどすかぁ?そんなん、誉めてもろたん初めてやわぁ・・・あははは~」
「おみやって?」
「あ、おみやゆ~たら足のことどすぇ。京都ではそない呼ぶんどすえ」
「へえ~、そうなんだ。それは初めて聞いたよ」
「はい、できましたよ。これで大丈夫。格好良くはないけど、暫くは持つでしょう」
「やぁ、嬉しいわぁ~、お~きに~。お陰で助かりましたわ」
「それじゃ、僕はこれで」
「あ、ちょっとお待ちやす~。あのぅ・・・もしよろしおしたらお名前、教えてくれはりません?」
「名前ですか?本村俊介っていいます。あなたは?」
「うちは、ありさどす~。よろしゅうに~」
「ああ、どうも」
本村と名乗る青年は照れ笑いしながら、帽子のひさしに手を置いた。
「ほな、おおきに~、さいなら~」
「さようなら・・・」
先斗町を経て祇園へ向うありさとは反対に、青年は河原町の方へ向って行った。
ありさはふと立ち止まりもう一度振り返った。
そして、黒い学生服の後姿をじっと熱い眼差しで見送っていた。
ありさは胸に熱い血潮がふつふつとたぎるのを押さえることができなかった。
お座敷に来る男たちとはあまりにも違う。いや、違い過ぎる。
今通り過ぎて行った学生の凛々しさと清々しさは、ありさの胸に鮮烈な印象を残した。
だがそんな感傷を振り払うかのように、ありさは再び祇園に向って歩き始めた。
愛と官能の美学
花街のセクハラ
- 関連記事
-
テーマ : 官能小説・エロノベル
ジャンル : アダルト
tag : きむすめ未通女凌辱お風呂入りうぶな旦那制度悲恋混浴花街結婚強制性交