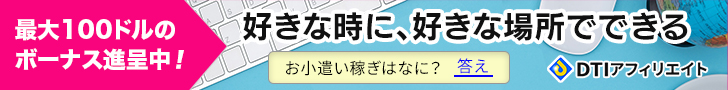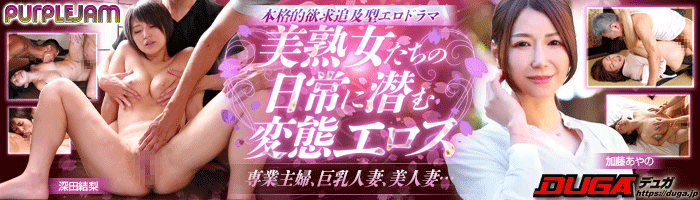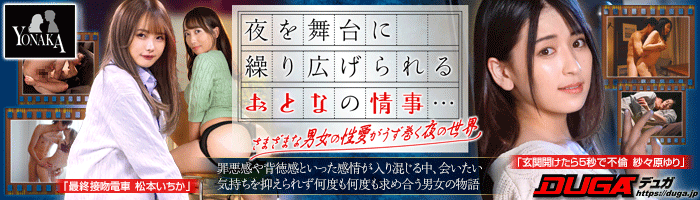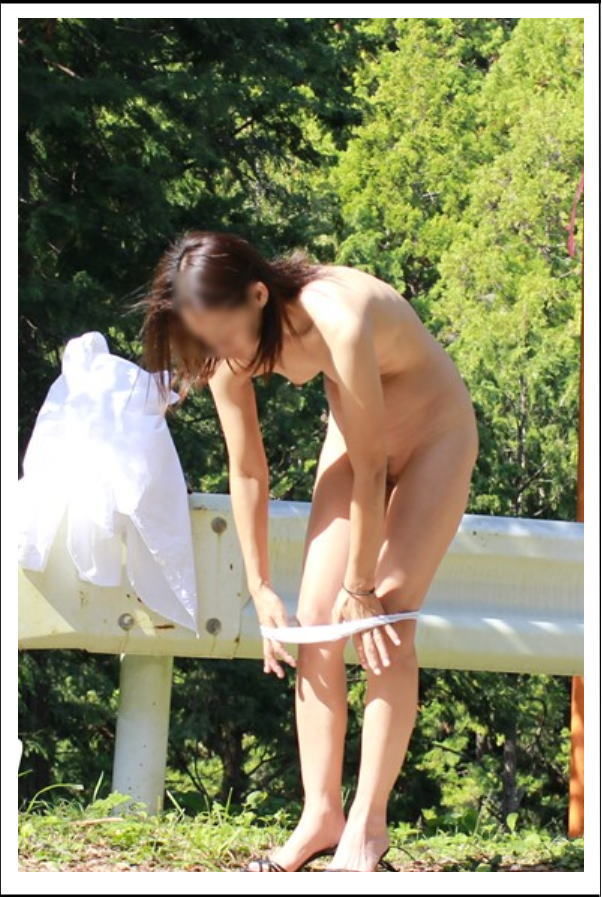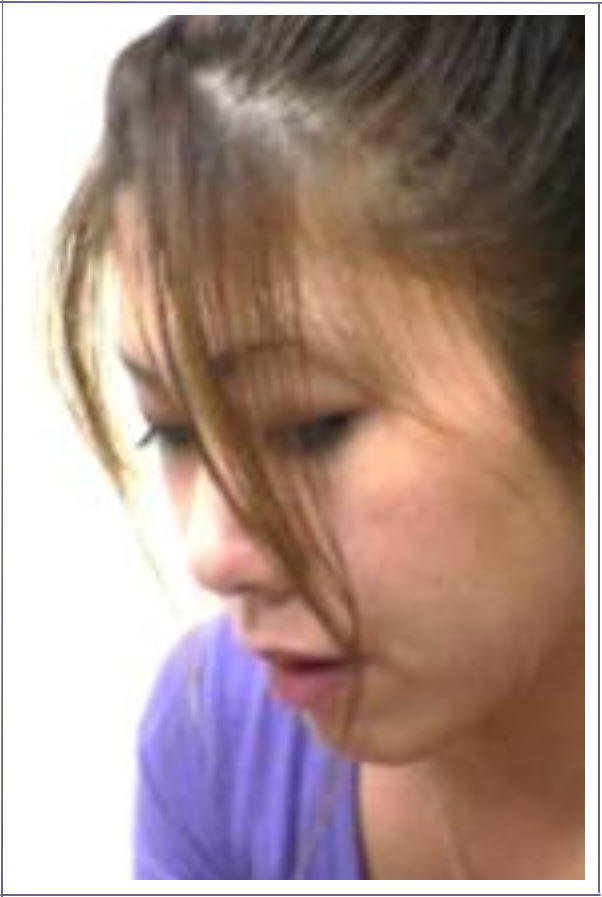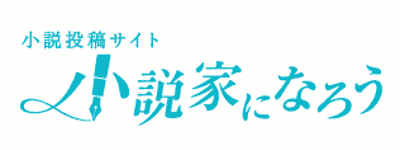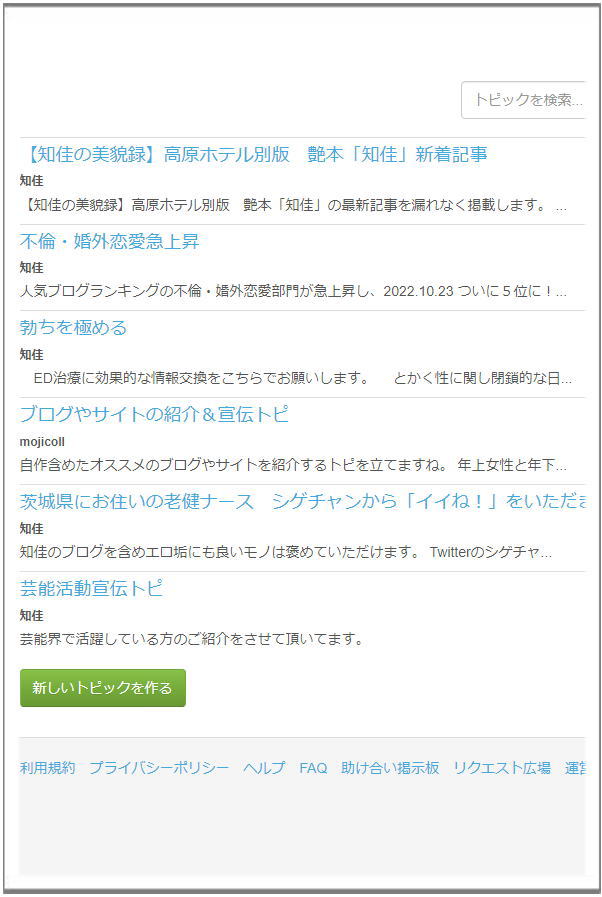逆恨み
 何が気に食わなくてそっぽを向くのか、何に苛立つから当たり散らすのか、周囲はもとより本人ですら筋道を立てて説明できないでいた。
何が気に食わなくてそっぽを向くのか、何に苛立つから当たり散らすのか、周囲はもとより本人ですら筋道を立てて説明できないでいた。「そうか・・・、今年の夏は妙な天気だったからな~、はよう秋がきてくれにゃ~かなわんのう」
「ほんになぁ、けど、あんたんちは楽じゃからえぇわ。うちなんか・・・秋が来てもなぁ・・・」
「けんどなぁ、秋祭りにゃあ冨美ちゃんも着飾って来るんじゃろ? 今年の祭りは楽しみだて」
地主の慎次と並んで歩きながら世間話をしていた冨美は「今年の祭りは・・」という慎次の言葉を聴いた途端足を止め、「どうした?」と聞き返されると「用事を思い出した」と、いきなり脇道に向かって大股で歩いて去ってしまった。
普段は、これでも田舎暮らしをしようと覚悟を決めて来たのかというほど楚々とした歩き方しかできない女である。
訳が分からないまでも、女のスイッチが入ってしまっていることだけはわかった。
狐につままれたような気持ちでただ呆然と小作の妻冨美を地主の慎次は見送った。
「なんだありゃ?」
当てが外れた思いだった。
「ちょっときれいだからとおだてりゃ調子に乗りやがって」
このまままっすぐに歩けば、ふたりの恋が成就できる場所に辿り着くと慎次はもくろんでいた。
「あいつだってこうなりたいから近寄って来たんじゃないか。それを、何を今更・・」
他人同士が秘かに野で睦み合うことは、昔からよくこの村では行われていたことだった。
「あ~ぁ、やめたやめた。馬鹿らしなった」
ましては冨美とは、心は通じ合っていると自負していた。
もう、いつ睦み合っても、いや、隠し子がいたっておかしくないほど冨美は俺に惚れぬいていたはずではなかったのかと自問してみた。
慎次はこの村で生まれ、この村で育った。
村には高校がなかった、だから中学を卒業すると街の高校に通った。
冨美と知り合ったのは慎次が3年になったときの夏に催された街の花火大会でだった。
「こんな騒がしいとこで花火見ても気分が悪いだけじゃ。河原へ行かんか?」
仲間を誘ってみたが、花火より女が目当ての奴らは慎次の提案にそっぽを向いた。
「ちぇっ、すきにせーや」慎次はどちらかというと静かに花火を見たかった。散り際の余韻を楽しみたかった。
花火見学にしては遠すぎる川の土手で、冨美も丁度その花火を観ていた。
「どっから来たん? 街で観んのんか?」
「ううん、街はなんや変なやつばかりおるから好かん」
「ほうやな、花火は散り際の・・・なんや侘びしいいうか・・・そんなんがな」言いながら慎次は照れて見せた。
「あんたも仲間と別れて来たん? 変な人」冨美は笑った。
清らかな川のせせらぎが、ドーンと打ちあがった花火のパチパチという音がした散り際に一層情緒を添えているように思えた。
花火が打ち上げられていた僅か1時間、短い会話を交わした。たったそれだけのことであっても心が通じ合えるものがあった。
「こんなしょうもない学園祭へようこそ」
次にであったのは冨美が通う女学校の学園祭で、冷やかしに来ていた男子学生の中に慎次を見つけ、冨美から声をかけた。
「まあな、みんなが行こうっていうから」
「まだ名前訊いてへんかった。なんていうの?」
「慎次や。慎むに次って書くんや」
「そう、わたしは冨美。ほら、とみの上に点がないやつ、それに美しいって書いて フミって読む」
「そうか、冨美か。好い名やな」
「ふ~ん、わたしは古臭くて好きになれないけど・・ねぇ、ベル番とアドレスは?」
花火の思い出で話は盛り上がり、お互いに連絡先の交換をした。
「ちゃんと登録してくれた?」
「あとで登録しとく。なんや操作するの面倒やしな」
「えぇ~、信じらんない。それって扱い方ほとんど知らないってやつ? いまどき?」
「うっるせーなー、機種替えたらわからんようなっただけや」
「かしてみ。わたしがしてあげる」
冨美からすれば、当然慎次から付き合ってほしい旨の連絡があるものと信じて待った。
「変やな~、使い方まだわからんとか・・・」
仕方なく何度か冨美からメールを送ってみたが返答は返ってこなかった。
連絡のないまま、慎次は卒業を迎え、学校から消えた。
受け取った連絡先の電話番号も、もうその時には「この番号は現在使われていません」とむなしい返答が帰ってくるばかりだった。
次に慎次と出会ったのは社会人5年目に入ったときだった。
小さな洋品店の販売員をしていた冨美に慎次の方から声をかけてきた。
「可愛らしい女の子がいるから見に行こう」と同僚に誘われて来たと慎次は冨美に告げた。
「そう言われて何度か店の前を通ってみたんやけど、あんまりきれいになってて気ー付かんやった」
「えー、わたしのこと~? そんなに変わった?」
「うん、めっちゃきれいになった。知ってるって言ったらみんな驚いてた」
遠まわしに交際を申し込まれたと冨美は思った。
「コーヒーでもってやつ?」
「うん、そんなとこかな」
デートとはまでは言えない街ブラをふたりは楽しんだ。
手が触れ合うよう、わざと身体を密着させる方向に傾けたのは、この時も冨美の方からだった。
「ほらっ、あのあたりに上がった花火を河土手から見てたんだね」
「そうだったっけ?なんだかあのころと変わったから・・・」
「そうよ、ひとりで花火見てたわたしに声をかけてくれたじゃない」
自然を装って手を絡めた。
いつの頃からか慎次は、冨美の手を引いて歩いてくれるようになっていった。
「慎次くんて足が速いから、一緒に歩くの大変」
「えっ、そうなん?気がつかんかった。ごめん」
他愛ない会話の中にも冨美にとって幸せが満ちていた。
当然次はプロポーズの言葉を口にしてくれるものと冨美は、またしても待った。
暫らく会えない日が続いたある日の午後、慎次から呼び出された。「決心してくれた」冨美の心は沸き立った。
ところが口から出た言葉は「俺、結婚したんだ」だった。
慎次は許嫁がいながら冨美と手を繋ぎながらデートをしていた。
「そうだったの、体調を崩して入院でもしてるかと思った」
極めて明るくふるまってみたものの、冨美の心はボロボロに傷ついた。
「ねぇ、奥さんてどこで知り合ったの? どんな人?」
「うん、家を継ぐことになって資産家の女と見合いさせられて。俺んち名前だけは地主やけど赤貧洗うがごとくなんや。仕方なくな」
そんな慎次だったが、婚約とか結婚と言われても冨美には諦めきれなかった。
「ひょっとしたら資産家の嫁なんかとは上手くいかず別れ・・・」「子供が生まれなかったら・・」「性格の不一致」と、さまざまな理由を妄想しては慎次と結ばれる日を待った。
「そうだ、毎日近くで顔を合わせるようになったら」そんな邪心と言おうか、軽い気持ちで地主の慎次の下僕に当たる、小作の遼の家に嫁いだ。
押しかけ女房だった。
遼は女に対しては最低の男だった。
ガタイが小さい癖に自己顕示欲だけは人一倍強かった。
おまけに性欲旺盛というほどでもないのに、やたらと女を抱きたがった。
女を組み敷き、身動きが取れないようにしておいて挿し込むと終わったときに素直に従うようになる。
自分の持ち物が女に通じたと錯覚を起こし、それがまた次の犯行に繋がった。
その対象が地区の中学に通う女の子たちだった。
学校の帰りが遅くなった女の子を橋の下や繁みに影に引きずり込んでは犯した。
泣き叫ぶようなことはしなかった。
みながみな、覚悟を決めたように言われるまま下腹部を差し出し、遼を迎え入れている。
遼にしても街の風俗嬢を抱くより余程良かった。
それというのも熟成した女と比べ未通というのは狭かった。
ガタイが小さい故に未通こそサイズに合っていたからである。
問題が発覚しなかったのはひとえに地区の風習にあった。
自分たちの親でも、隣近所の異性と密通し、終わった後はお互い様と口を濁す。
それを観て育った子供たちにとって男女の睦み事は、さして騒ぎ建てするほどのことでもなかったのである。
冨美がこの男に目をつけ、結婚に踏み切ったのにはわけがあった。
それがこの弱みだった。
遼が女欲しさにうろついていたのを見つけ、上手に誘って身体の関係を持った後、学生に卑猥な行為を強要したことをネタに強請り、結婚を迫り嫁いだ。
嫁いでわかったことは、この村では向こう三軒両隣が、ろくに生活力もないのにことごとく張り合っているという現実だった。
地主は小作を目の敵にし、小作は水飲みを虐げた。
家に不幸が続いた水飲みの長男であり家長でもある悟は、辛抱し切れず村から逃げた。
嫁と幼い長男を残して姑である母親とともに病院に行くと告げ出かけたまま帰ってこなかった。
村の者は「あのままじゃ、悟のやつ今に逃げ出すぞ」と噂し合い、まるで手ぐすね引いて待っていたふしがあった。
百姓、つまり田畑を耕すということは女子供の手に負える代物ではない。
残された母親は子供のために鍬を手に取ったが小さな畑のひと畝耕すこともできなかった。
たちまち水飲みの家は行き詰った。
「ねぇ遼さん、頼むよ。ほんのちょっとの間貸しとくれな」
今日は米一升、明日は千円と小作の家に無心に来た。
「そうは言われてもなぁ~、ウチも手いっぱいなんだ。まぁ仕方がない、今度だけだぞ」
最初の頃だけは良い顔をして遼は水飲みの妻美也子に、女房冨美の陰に隠れてこっそり申し出てきた量より大目に手渡し、わざわざ自宅まで見送りしていた。
「うん、あんたんとこも大変だ。とにかく気を落さんと頑張るんだぞ」
「本当に、恩に着ます。いつかちゃんとお返しに上がりますから」
息子一人だけの家によその男を上げるわけにもいかないから、自宅の灯が見えるところまで見送ってもらうと美也子は遼の手を取って頭を下げ、自宅に向かった。
遼は元来た道を引き返すそぶりをしながら美也子の家に忍びより、壁の隙間越しに中を覗き見し隙を窺った。
「ちくしょう、早くしやがれ」
藪蚊と戦いながら美也子が一日の汗を流すため、破れた壁の内にある風呂に入るため脱ぐ瞬間を待ち、それをおかずに扱いた。
「相変わらずいい身体してやがる。悟なんかに抱かすにゃ勿体無い」
風呂を終わって着替えるのを待って自宅への道を帰って行った。
「あれじゃまた借りにくるわい。そんときゃちょこっと触るぐらい・・・へへへっ、たまらん」
ところが、積もり積もって返済の目途が立たなくなると、打って変わって身体を要求してきた。
「いくらなんでも、仏の顔も三度までっていうじゃないか。返す当てがなけりゃ・・・わかってるだろう?」
拒めば長男が掛けて寝ていた布団まで剥ぎ取って持ち帰る有様だった。
「返してほしけりゃ、いい返事まってるぜ」
「いくらなんでも、それだけは勘弁しとくくれな。後生だから・・・」
美也子は泣く泣く遼の申し出を受けた。
「子供が家出待ってるんだ。早くしとくれな・・・」
「何をお高く留まってんだ。ちょちょっと吸わせてくれって言ってるだけじゃねぇか」
「余所の人が見たらなんていうか・・・お前さんもそこんとこ良く考えてくれな」
それでも美也子の抵抗にあい、唇を奪うのに数日を要した。
「お前も旦那がいなくなって不自由してたんだろう? どうだい、吸われた感想は」
「何言ってんだ。借りたもの帳消しにしてやるっていうから吸わせたやっただけじゃないか。お前こそ冨美さんとご無沙汰じゃなかったんかい?」
美也子は殊の外強気に出たつもりだったが、なにもかも忘れて抱き合い唇を貪り合えば衣服も乱れる。
遼に鍛え抜かれた胸に乳房が押し当てられ、身体が擦れ合ううちに衣服からはみ出し、こぼれた。
「震い付きたくなるほど真っ白なきれいな肌してるじゃないか。こりゃあ遠目で風呂に入る姿を観るよりずっといい」
「なんだい、いやらしいたらありゃあしない。壁の隙間から裸を見るだけじゃ治まらなくなったとでもいうのかい?」
「お前ってやつは。気がついてて・・・」
唇を奪うと次は胸だった。
「あっ、何するんだい。まだ許したわけじゃないよ」
「口を吸われなきゃ言うことが訊けないとでもいうのか」
唇を奪い続けているうちに美也子の胸が肌蹴始めていて、そこから覗く乳房が、乳首がまぶしかった。
「・・・んん、だめったら!そこは・・」
唇を奪いながら、半ば強引にその肌蹴た胸に手を差し入れ乳房を揉みしだいていた。
「すごいよ。こんなすごい女をほって出ていくなんてな」
「あの人は帰ってきます。だからあの人に見つからないうちに・・・」
全身を久しぶりの男に羽交い絞めされている。
美也子の強引さというより抱きしめ奪おうとした男に抗いきれず身を揉んだことで遼の心に、身体に火が着いた。
「帰るまでの辛抱を仕込んでやるだけだよ。黙っといてやるから一度コイツを銜え込んでみろ」
美也子の下腹部に火のように火照った遼の分身が強く押し付けられた。
「あ~ たまらん。すごいよ美也子。もうこんなに熱くなってるじゃないか」
「もう・・・もう・・・」
もはや夫婦の閨とかわりない、どちらかというと甘い攻防に変わっていった。絡みつく下半身を美也子こそ躱そうとしないばかりかピッタリ寄り添うような仕草を見せたのである。
遼の背中に回した手が、次第に腰に下がってきて、やがてピッタリと分身を花芯の中心に押し当て膨らみを割れ始めた窪みに押し付けはじめていた。
「誰かに見られてる・・・こんなことして、知らないから・・・責任とれるの?」
遼は美也子の下腹部に手を滑らせた。
性を十分熟知していた人妻の弱みに付け込んで、ついに美也子の口から要求の言葉を吐かせ、ここから先はこのまま身体を重ねなければ治まらない状態にまで攻めきった。
「ほら、触ってごらん。美也子のことを毎日想い続けるあまりこんなになってたんだよ」
美也子の手を取って遼は己の股間に導いた。
「ああ・・・すごい。ごめんなさい維持張って、待ってくれてたのね」
「待ったよ。気が狂いそうになりながら待ってたんだ」
「うれしい・・・ちゃんとしてね」
萱の生い茂る草むらに夜更け、美也子を呼び出し月明かりの中で遼は美也子への想いを遂げるべく全力で凌辱した。
村の誰もが一度はお世話になろうと狙っていた抱き具合のよさそうな美也子を、小作の遼が真っ先に頂いたことに、その夜は酔いしれた。
「うっうっうっうっ・・・!」
美也子の腰が躍った。
腹腔が沸騰し、腹内圧が上がった。
「んむむ・・・むううう・・・」
頭を精一杯後ろに倒し、胸に響くような声を上げながら美也子は遼の亀頭冠を壺で吸引してくるのだった。
吸引力の強さがそのまま耐え続けた年月を物語っていた。
油断すれば射精感が沸き起こる前に抜かれてしまいそうになるほど肉球を使った搾り込みが強かった。
誰も見ていないことを良いことに、これ以上の恥辱はないというほど開かせ割り込み、美也子をして、久しぶりの男の味に泣き叫ばせた。
遼はついに美也子を乗りこなしたと安堵した。ところが・・・
「ねぇ、わたしのこと、大切に想ってくれる?」
「当然だろう?誰よりの大切だよ」
美也子も負けてはいなかった。
「なら、これからも必要なもの、頼むわね、わ・た・しの遼さん」
身体を要求されるたびになにがしかの金か米を媚を売って持ってこさせた。
小作の家とて他人を養うほど裕福ではない。
それでも美也子は生きるために娼婦の如く媚びて要求した。
持ってこなければ他の男に身を任すと脅しまでした。
「遼さんとわたしたちのこと、みんな知ってるみたいよ。今日○○さんに誘われちゃった。ねぇ、どうしたらいい?」
「断れ!ダメに決まってるだろう?お前は俺のものだ」
事実、遼の隙を見て言い寄る男には甘い顔をしてわざとついていった。
「わたしのこと、みんななんて言ってるの?教えてくれたら・・・」
科を作って誘った。
「あの野郎!おれの美也子に・・・」
そうするたびに遼は凄い剣幕で美也子を叱咤し、狂ったように抱いた。
水飲みの耕作地は山間の急斜面を切り開いた僅かばかりの田畑しかない。
日の出は遅く、逆に日の入りはとても早かった。
捨て置けば野面積みの石垣は谷底めがけて崩れ落ちてしまう。
おまけに耕地は土が硬く、水源がなかったためろくな野菜ができない。
雨が降らない日など、谷あいから水を担ぎ上げて散水しなければならなかった。
それに加えて獣に食い荒らされれうことがあり、収穫は自宅で食べるのにも事欠いた。
美也子はひとりでこれをこなした。
必死だったが、とても生活費を捻出できるものではなかった。
子供はそれでも育った。
学費も増えれば、食用も日増しに足りなくなる。
その分を密かにほかの男に言い寄って、遼との関係をちらつかせ、貢がせた。
噂はたちまち村の男衆の間で広まった。
そのため美也子と遼の関係は冨美に好意を寄せる、ある男の陰口で冨美の知るところとなる。
月夜の晩になると遼は、なけなしの金と米を抱えて萱の原に出かけていく。
冨美はこっそり後をつけ、ふたりが睦み合うさまを出来うる限り近寄って見聞きした。
恋してやまない慎次との夢は成就できないのに夫は水飲みの美也子とねんごろになり、楽しんでいる。
美也子のあられもない声を聴きながら、いつか自分もそうなりたいと最初の頃こそ慎次に向かって冨美は情念を燃やしていた。
今日こそと思ったその日に慎次が夏祭りの話題を振ってきた。
冨美に夏の花火の、そのあとに続く苦い思いが蘇った。
慎次こそ、冨美を裏切り続けたことを棚に上げ、冨美に再び密事に「誘わせ」ようとしていたのである。
何事につけ我慢・辛抱してきたのに、取り残されたのは結局冨美だけだった。
侮辱だった。「呪ってやる」鬼になった。
ポチッとお願い 知佳


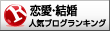
恋愛・結婚ランキング
google51904d4c43421b58.html
BingSiteAuth.xml
- 関連記事
tag : 取り残された