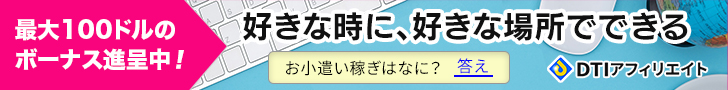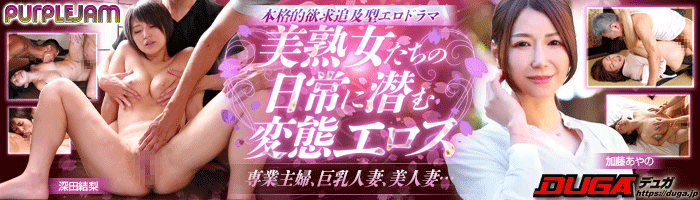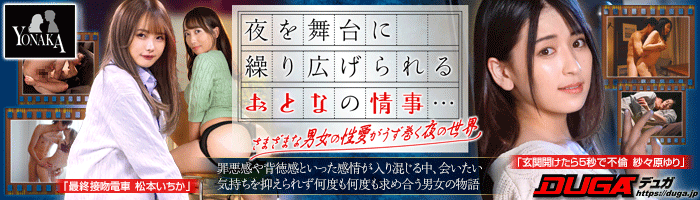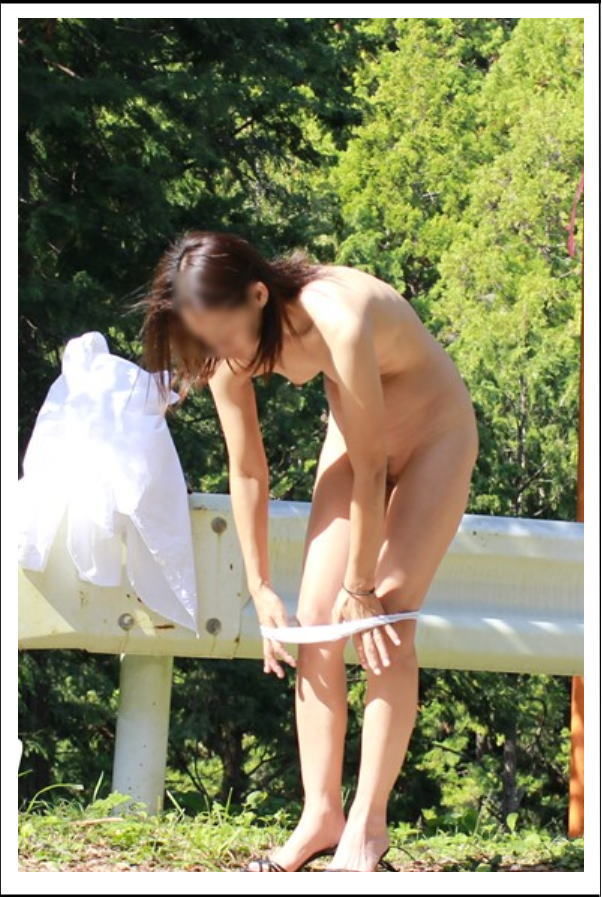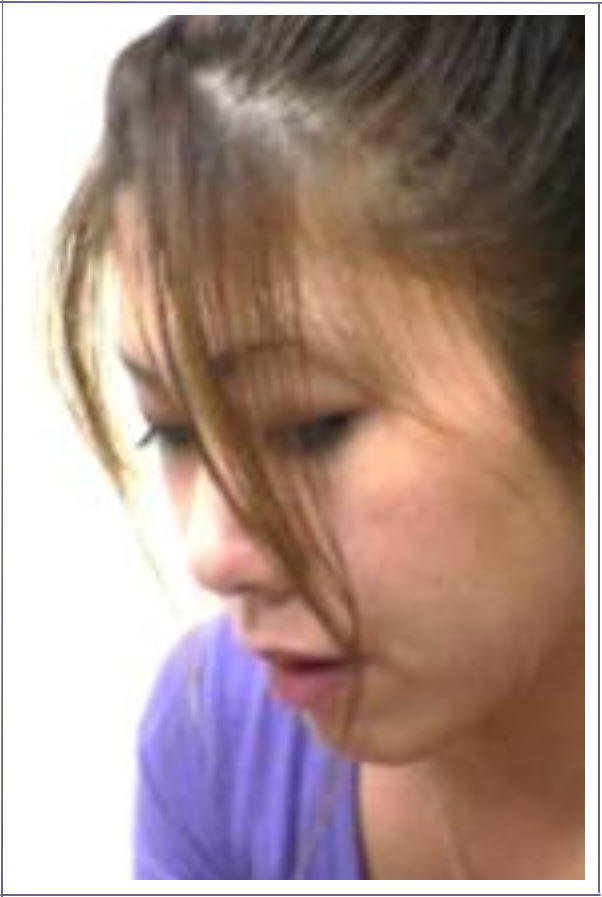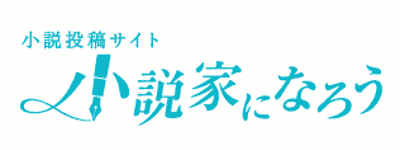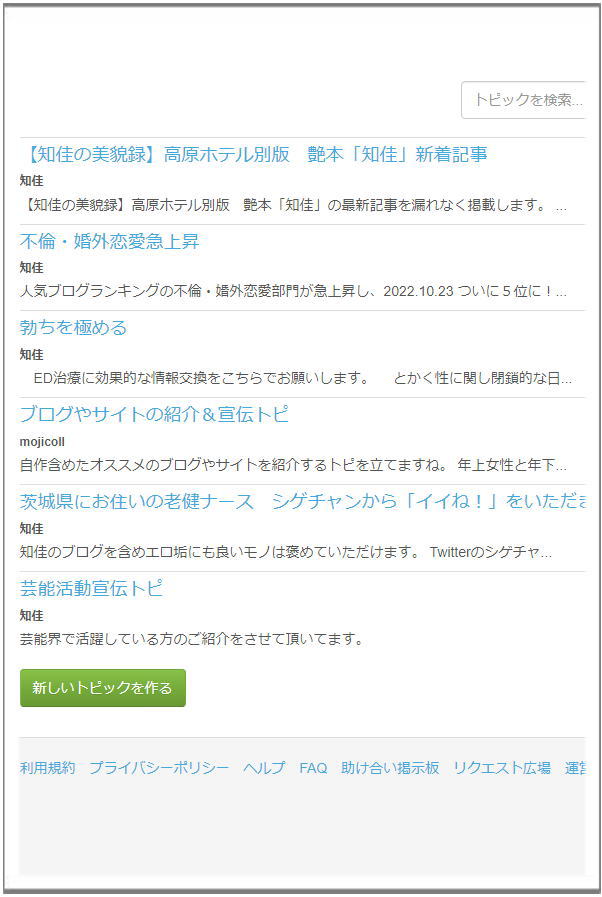疑惑 悪しき因襲
30戸にも満たない小さな、穏やかな入沢村が騒然となった。
村でも神童で通っていた本家、足立家の跡取り、庄衛門がどうしたことか突然高台から真っ逆さまに飛び降りた。
幸いなことに、崖下にはその年、本家の母屋の屋根の葺き替えにと刈り取られ、高く積み上げられた萱があり、庄衛門はその上に頭から落ちた。
胆試しに高台から飛び降りたんだろうと、崖下で萱を刈り集めていた村の衆は思った。
「あん、高台から躊躇いもせず飛びんしゃる。本家の若さんは大したもんじゃ」
「ほんにのう。旦那は葺き替えの屋根に、よう登りんしゃらなんだが、若さんは胆のええことで」
作業に従事していた分家の嫁、おえんも、今飛び降りたばかりの庄衛門を頬を染めて見つめていた。
跡取りがなぜ、高台にいたかというと、
「庄衛門さんに見張ってもらわにゃ、分家連中にゃ境がわからんけえのう」
「ほんにほんに、長嶋さんとこ入り込んで刈ったりすりゃ、えらいことだで」
声をからして、庄衛門は下の連中に刈り取りを見張っていた。
萱葺き屋根の吹き替えは、足立家では30年ぶりとなる。
曲がった萱や寸足らずの萱が1本でも混じってしまうと、そこだけ屋根が漏ることになる。
押さえ木に使う真竹にしても、わざわざ庄衛門が出向き、竹やぶに入って選んで切り出していた。
寝る間も惜しんで体を鍛え、勉学にいそしんでいた庄衛門。
「ありゃ~、若さんがぁ~」
おえんは助け起こすべく萱の山に近づき、素っ頓狂な声を出して退いた。
おえんの声に驚いて駆けつけた村の衆も、庄衛門の姿に慄然とした。
口から泡を吹き、眼はあらぬ方向に向かって飛んでいた。
顔面は蒼白で、行動ものろのろと、見当もつかない方向によろめく、第一、口走る言葉が理解できなかった。
表情までもが一変していた。
神主に坊主とおおよそ村周辺の医の心得のあるものが呼び寄せられ、事に当たったが回復が望めないどころか、悪化する一方で、終いに座敷牢に入れられた。
「狐が憑いたとしか思えん」
誰もが囁き合ったが、おえんだけは事の真相を知っていた。
この地方ではおえんがまだ子供だった頃、飢饉に見舞われたことがある。
田植えの時期になっても雨が降らず、難儀して植えたと思ったら、今度は長雨が続いた。
気温が上がらなかったその年は大凶作となった。
本家筋は、分家に餓死者を出してはならじと頼母子講にすがった。
その返しに難渋しているときに、
「返せんなら、嫁を出せ」そう迫られた。
「本家筋の嫁に娼婦のまねごとを迫るとは・・・」
だが、袂を逆さに振っても無いものはない。
どうせ他人にくれてやるなら・・・分家の一人が婿入りした旦那の庄左エ門に断りもせず、泣きわめくおツネを強引に押さえ込み一晩中まぐわった。
明け方近くになって開放してやったものの、放精と淫液で閨はひどいありさまだった。
この様子を、隣の部屋で息を潜ませ覗いているものがいた。
作佐の女房おカネだった。
夫が本家の嫁に横恋慕していることは、うすうす気が付いていた。
それが、まさかこんな形でおツネと夫がまぐわうことになろうとは思わなかった。
おカネは心底おツネを恨んだ。
後に、夫作佐の度重なる暴力に耐え兼ね、台所の片隅で泣きながら娘おえんに話して聞かせたのが、この忌まわしいまぐわいだった。
翌日、嫁は頼母子講に借金の肩に本家から送り出されたが、一晩違いで嫁は分家の子を孕んでいた。
嫁が返されてきて十月十日(とつきとおか)、元気な男の子が生まれたが、庄左エ門はおろか、分家の誰もがこのことに口をつぐんだ。
腹の子が、誰の子なのか、知っているのは表面上は嫁だけとなった。
「あたしさえ黙っていたら・・・」
おツネは心に誓い、何事もなかったかのように振る舞った。
腕力にはたけているものの、どちらかと言えば愚鈍な作佐に対し、庄左エ門は夫庄衛門に似て利発だった。
いつしか庄衛門は、庄左エ門を自慢の息子として近隣に自慢するようになっていった。
そしてこの事件、気がふれた庄衛門の顔つきは、おえんの義父にそっくりだったのである。
入沢村の秋は深い。
紅葉は村全体を赤く染め、山々にはその年のほう年を祝うがごとくキノコ類が所狭しと生えていた。
村の人々は、刈り入れを終えると山野に憩いを求めて分け入る。
シメジや香茸、松茸と背負子(しょいこ)に入りきらぬほどお宝が採れた。
キノコ狩りの、ほんの一休みのつもりで、谷あいに向けて立つ古木に生い茂っていたアケビのい弦を見つけた甚六親子。
甚六は我が子のために、気に近づき、足元にあった小石を踏み台に古木に足をかけた。
右足に力を入れた途端に小石が砕け、甚六は谷底に転がり落ちてしまった。
「ワァ~ッ、おとっつあん」
転がり落ちるように後を追う一家。
転がり落ちた痛みで身動きできない甚六の足元には、背負子(しょいこ)からこぼれたキノコ類が散乱した。
せっかく手に苦労して採ったキノコが勿体なくて、懸命に拾う長男の竹造。
父親の容体が心配で、懸命に抱き起そうとする長女のおヨネ、その時末娘のおミヨは横臥する父の足元で妙なものを見つけ、拾い上げた。
「これ、なあに?」
おヨネが拾い上げた棒のようなものを見て、甚六は思わず後ずさりした。
よくよく見れば、長男が拾い集めているキノコに交じって、なにやら白い破片が散在する。
人骨だった。
おヨネが拾い上げたのは、大腿骨と思われた。
「儂が足をかけたのは、頭蓋骨だったのか・・・」
谷あいから見上げたアケビの弦は、甚六が片手を伸ばす、ほんの少し上で、まるで首つりに都合の良い恰好で、そこだけ支えていた枝が折れて垂れ下がっていた。
首をつらねばならなかったものの霊は、時を隔てて甚六親子を、そこに呼び寄せていた。
末の娘、おヨネが産まれてまもなく、母のおスヱが忽然と姿を消した。
2日経っても3日経っても帰ってこないおスヱに、甚六はただならぬものを感じ、庄屋の庄左エ門に相談の上、山狩りを行った。
陣頭指揮に当たった庄左エ門は、甚六の女房の扱い方が悪かったんだろうと家出説を唱え、おスヱの里方面を重点的に探させた。
甚六が、おスヱは山で迷ったことも考えられると主張したが、聞き入れてもらえなかった。
結局、おスヱは見つからぬまま、一月後に葬儀を済ませた。
甚六は入沢村に生まれながら、生家は田を持たなかった。
いや、持たなかったというより、先代が女に狂ったことで仲間から耕作地を女に貢ぐ金の代償として奪われた。
食うや食わずの生活が続いた。
食いつないでいくには、山子(やまこ)しかなかった。
「庄左エ門さん、前々から頼んどった山だがのう」
「おう、甚公か。また酒代欲しさに妙な言い訳しよる」
「いんや、コメが買えんでのう」
だが、山を買うにはそれ相当の資金がいる。
「コメが買えんもんが山のゼニ、どうやって払う?」
せせら笑うばかりだった。
資金を持たない甚六に、山を分けてくれたのは隣村の連中だった。
「甚六さん、悪いことは言わん。諦めさっしゃい。あん庄左エ門は鬼じゃ」
「じゃが、儂ァ、あの家しか住むところがないけんのう」
「まァええわい。あそこは儂らでは切り出してもゼニにならん」
「ほんに、恩に着ます」
それだけに、その山は甚六の家から歩いていくには酷すぎる、遥か彼方にあった。
甚六が、なぜにこの場所を指して子供を伴ってキノコ採りに訪れたかと言えば、それこそが入沢村の連中では道に迷う危うさに入り込めない奥地にあったからである。
そこは豊かな自然に囲まれた別天地だった。
おスヱはその日、我が子の世話を終えると、夫の待つ窯に向かった。
山越えの杣道の別れで足立庄左エ門と出会った。
「あらっ、本家の庄さん。山周りですか?」
「山を売れっていうモンがおってのう」
「こん山は、はぁ 木切ったばかりじゃけん、買ういうたら土地ごめかいのう」
「そげんこたぁ答えられんじゃろが」
「そりゃあ失礼しました」
一通りのあいさつをして、夫の待つ脇道に入って間もなく襲われた。
「誰が好き好んでこんな山奥へ・・・待ちかねとったよ」
「庄さん、上段が過ぎるんじゃないかえ」
庄左エ門であっても、誰が通るとも限らない杣道では襲えなかったと見える。
「何するんですか!こんなことがおツネさんに知れたら・・・やめて!」
「だれがお前らごときの言葉を信じるか。お前ら山子は黙って儂の言うことを聞いてりゃええんじゃ」
「本家、気がふれたか」
おスヱはひたすら山の下の方に、転がり落ちるように逃げた。
「わっははは、逃げろ逃げろ」
道々、襲っては逃し、襲っては逃しし、そのたびに着ているものをひとつひとつ引き裂き、剥ぎ取っていった。
それでもおスヱは懸命に逃げた。
庄左エ門はおスヱを、尾根一つ越えた隣の峰に追い込み、そこで身体の芯部に残る乱暴を働いた。
庄衛門にとって、美しい女ほど信用できないものはなかった。
女房のおツネは、どこの誰ともわからない男と契って胤を宿して戻ってきている。
その腹いせに、今度は本家をかさに着て、庄衛門自身が周囲の連中に女房を襲った。
おツネに負けないほどの女房を幾人も襲ったが、誰一人として最後まで庄衛門を拒絶したものはなかった。
事が始まり、時が経つにつれ、女房どもは庄衛門を包み込むようにして放精を受けてくれた。
気をよくして、この日の獲物と定めた甚六の女房に襲い掛かったのだ。
ところが甚六の女房おスヱは、最後まで庄衛門を受け入れようとはしなかった。
「たかが水飲みごときが生意気な!これでもくらえ」
おスヱの横っ面にビンタが飛んだ。
渾身の力を振り絞って逃げ惑い、抵抗を試みていたおスヱに、もう余力は残されていなかった。
殴打された瞬間、気を失ってぐったりと動かなくなった。
庄衛門は悠々と、おスヱを割り、その体内深く放精し、痕跡を一切残さぬよう始末したのち、遠回りして家路に向かった。
小柄なおスヱは、庄衛門の手によって担ぎ上げられ、更に峰続きの別の山の頂、三角点に捨てられた。
そこは入沢村と両隣村の境界に当たっていた。
おスヱは侵されて後、夫の待つ窯に、幾度も戻ろうとして放浪し立ち往生した。この村出身ではないおスヱには方角が分からなかった、諦めたが、それでも別の峰に這いあがっては夫の待つ山を探した。
汚された身体が元に戻ろうはずもない。
おスヱにはわかっていた。
庄左エ門の体液は、のたうちまわるうちに益々オスとして欲情しきっていて、ビンタで身動きが取れなくなった身体の深部に大量に放出されたであろう、身体の芯まで届けられていたことを覚悟した。
どう間違っても孕まないではいられないことを、子を産んできた母なればこそ、流れ落ちるさまで知っていた。
隠れ潜みながら甚六の姿を窯付近で見守ること3日、飲まず食わずの身体に、もう体力は残っていなかった。
死後の力を振り絞って谷あいに、よく花を咲かせるアケビの弦を探し求め、登って実を採ろうとしたが叶わず、生きる気力を失いそれで首を吊った。
甚六が、仕事に疲れると良く採ってきてくれた、おスヱの大好きな甘いアケビの、「子供たちに見せたらブランコになると言って喜ぶだろうね」と語り合った、皮肉にもその弦だった。
アケビがまとわりつく木の脇には、甚六がおスヱでもアケビが採れるよう、竹竿を、まるで柿の実を採るかの如く先をカニの手のように細工して立てかけていた。
それだけ愛着のある、しかも人も通わぬ山奥のこの木で首をくくる人物とは、女房のおスヱを置いてほかになかった。
「ようわかったよ、おスヱ。お前はあの村が嫌いなんじゃ」
骨を拾い集めると炭窯の一番奥に祭壇を設け、切り出した木を詰めていき、火をつけた。
「この窯は炭は取らん」
全ての物が完全に燃え尽き、灰になりきるまで甚六は寝ずに火を焚き続けた。
「すまんのう、おスヱ。わかっとるんじゃ、本家のヤツ」
噂は聞いていた。
止めようにも、情けないことに身分が違いすぎて口が利けなかった。
「いつか罰が当たる」
多くの女を抱える。
それは権力の象徴でもあった。
土地と財宝の奪い合いは、必然的に戦いに打ち勝つため人を増やさねばならなかった。
中央の誰かが、ろくに末も考えぬまま「産み増やせ」と一言つぶやいただけのことであったが、その命が下々に下るたびに歪めて捉えられ、女と土地の奪い合いとなる。
小競り合いは、ことあるごとに繰り返され、その度に女は奪われ、辱められた。
ひとり身の女はもちろんのこと、人妻であってもその対象となった。
夜這いである。
夜這いとは、読んで字のごとく寝込みを襲って女を犯すと思ったら大きな間違いで、昼日中であろうと、隙あらば女を襲って胤を仕込んだ。
村なればこそであった。
村人が総出で立ち働いていたなら起きないこのような事故も、せいぜい夫婦が近場で声を掛け合って働く程度で、時と場合によっては周囲に誰もいない孤独の空間で働く。
人恋しさはこの上ない。
優しくでもされようものなら、しがみつきたくもなる。
それが、隙と言えば隙になった。
便利なようであってモンペは、脇が開いていて、その気になれば容易に手を差し込める。
間違って差し込んでしまえば、邪魔になるのは腰巻だけであった。
狙われたが最後、どうあがいても逃れようがなかった。
のしかかられた女は、それらのことを必死で隠し通した。
今の世のように、医学が発達し、生まれてきた子が誰の子か、産んだ当人以外知る由もない。
そこに、女だてらに男あさりする人妻も現れた。
多くの男とまぐわい、ふんだんに子を産めば、それだけ食料は不足する。
主家の跡目相続に敗れた者は、仕方なく未開地を目指して山深く入植していった。
そしてそこでもまた、元々暮らしていた部族との諍いがあった。
諍いの結末は、必ずと言っていいほど買ったものが負けた者の女を奪う。
奪うものは奪われるものを目と鼻の先に据え置いて、その者の女を犯し胤を仕込んだ。
そうやって、奪った女を相手に胤を仕込んで子をなすことが、戦いに参加したものの褒章ともなった。
発端は気まぐれな中央に役人の独り言。
それがいつのまにか、血で血を洗う女と土地の奪い合いとなった。
戦いに敗れ、這う這うの体で逃げ延びた者は、決まって復讐に執念を燃やす。
いつの世か、仇を討たんがために周到な計画を練って、お宝を奪い返そうとした。
爺様が悟の母や紗江子の母、貞子らを相手に情交を繰り返したのも、元はと言えば己が権力や女を、あるものに奪われた、そのやるせなさを紛らすために弱い立場の者を組み敷いただけだった。
せめても、そ奴らの手にかかたとはいえ、表面上は手元に残っている女たちに向かって、我先に胤をまき散らそうと攻めよっただけだった。
いかにも勝ち組に見える爺様も、目の前で己の妻を蹂躙された口である。
たまたま近くに居合わせた地区の産婆が、ことの重大さに、爺様の妻が敵勢の胤で孕んだことを知ると、有無を言わさず先がカギ状になった串を突き刺し掻き出したと言います。
その後、いかように爺様が精魂込めて仕込もうとしても、婆様は受け付けず、生涯子を持たずして爺様は没しています。
爺様が和子に向かって言い残した「この村に、せめて儂のような・・・」とは、敵勢を退けてでも胤を仕込もうとするような豪の者がいてくれたらと。
決して爺様の思いが通じたわけではない。
紗江子と、その母貞子らは別として、悟の妻美佐子を寝取った橘遼は、その走りだったかもしれない。
目の前で美人の誉れ高い妻の美也子が、同じ村の庄屋、橘遼に襲われ、寝取られたことは、彼のこの仇を討たんやという腹の底から湧き上がる嫉妬心に火をつけた。
始まりは確かに中央の「産めよ増やせよ」の掛け声だったかもしれない。
だがそれを、地方の末の末まで行き渡らせようと、妙な努力をしたものがいなければ、殊更に今のような他人の持ち物である嫁・人妻の奪い合いが始まろうはずもない。
噂に上った人物の中の最右翼に、あの廃村の村の大地主、足立寛治がいた。
だがそれなら、爺様と比べて、それほどまでに力を持っているかと言われれば、そうでもない。
むしろ開墾地からとれる石高では、遥かに爺様のほうが上だった。
場所的にも、廃村は僻地の中の僻地、爺様の住む村のほうが、ずっと街に近く、動きがとりやすい。
頻繁に目指す、その時期が訪れた人妻のもとに通いつめ、口説き落とすには難儀なものがある。
そう考えると、最初に誰かが道をつけ、その手の女に仕込んだところに足立寛治や爺様が、うわさを聞いて忍び寄っていってお零れに預かったというほうが筋が通っている。
近隣の村々を、頻繁に渡り歩けるもので、しかも具合が丁度良くなったと診る、心得のあるもの以外、事は成しえない。
村というものは街と違う。
隣近所でも、子供ならいざ知らず、大人は滅多に顔を合わさない。
よそ者が村に這い入り込んできても、野良仕事に忙しい村人は、てんでバラバラに、或いは草深い野に、木々が生い茂る奥山にと立ち働き、顔を合わすことも、まずない。
夫婦であっても、夫が共に仕事を手伝えと、強く言わない限り思いついた場所で、これまた思いつくままに働く。
例えばその日、「その気のある」女房が、ある目的をもって夫や村人と、わざわざ離れた場所で立ち働いていたとしよう。
そして目的を持つ人物が、よくそのことを知っていたとしよう。
誰にも見とがめられず、知られることもなく誘い込まれる、その意思に従って近づける。
よろしくない目的を秘めたよそ者が入り込み、胤をまき散らすに、何の支障もないわけである。
行商であるかもしれないし、郵便配達員、昔のことと考えれば馬車引きまでも含まれよう。
だがしかし、先に述べたように「その気のある」ことを専門的にうかがい知るには、行商や馬車引きでは知識が足りなさすぎる。
ましてや行商では、海が時化ると売り物が手に入らないし、売り物があったとしても連日全戸回るほど運べないから無理がある。
かつての郵便局員は、今と違って相当優秀な人材の中から選ばれていて、必要とあらば全戸回ることもでき、家族構成から人物像まで熟知している。
だが、女性のメンスのこととなると敷居が高すぎはしないかという疑問も残る。
その点を、頻繁でなくても、捉え方さえ正確ならと考えると、各家庭をほとんど網羅していた薬売り業がある。
置き薬を売るものなら、そのあたりは別段怪しまれることなく解決するに足る聴き取りを行い、場合によっては「お試し」と称して何かを盛ったかもしれないし、秘かに明け渡させ嬲ったかもしれない。
ともかく、先人の誰かが足立寛治や爺様に先立って、本来は公にならないご婦人方の秘め事を、大胆不敵に執り行い、飽きると捨てて行った。
睦み合おうとする人妻は、最初の頃こそ絶対に夫に見つからないよう、慎重に事を運んでいる。
経験したことのある女性の、誰に聞いても異口同音にこういう。
だから、これらの悩みを調べてもらうにつけ、こういうこともやったという。
「淫臭が酷くて嫌われるんです」
「ひどいというのは、どういった程度のものですか?もし差し支えなかったら拝見できませんか?」
「ここではなんだから・・・裏を抜けたら田んぼの畔のところに萱の繁みがある。そこでなら・・・」
魅せてもいいという。
「よろしいですよ。簡単なことですから」
畑の野菜の出来を見てもらうと言い訳して出てくる塾妻に従って萱に繁みに分け入って、
「どれどれ、どんな具合なんですか?ほんの少し魅せてください」
「脇から覗くだけにしてくださいよ」
そうは言ってもモノの順序に情というものがある。
男は慎重に人妻の腰を、そろそろと抱いた。
着衣の上からではあるが、肌と肌をピッタリ密着させ、首筋に熱い吐息を吹きかけながら、その時を待った。
人妻の肌が、次第に熱気を帯びてくるのが分かり始めると、着衣越しに人妻の内股に忍び込ませた陳棒が、盛んに腰巻の中をつついた。
「・・・まだですか・・・時間が・・」
辛抱できなくなったと見えて、人妻の方からせかす言葉を口走った。
「慎重には慎重を期さないと・・・わかるでしょう?」
「・・・はい、でも」
「よろしいでしょう。具合を拝見します」
次第に力を籠め、終いには鷲掴みしてしまっていた手の指を滑り込ませ、シルを掬い取って嗅いでみて、
「これは・・・」わざと深刻な顔つきになり、耳元で囁いた。
「もう少しよく診てみないと、なんとも・・・」
一気に体制を跪く形に変え、更に分け入り、顔を秘部に埋め、片足を持ち上げつつ舌を這わす。
「んんっ、あっ、あああ・・・そこは」抵抗があった。
「辛抱してください。相当長い間患われていた部分を放置されていましたので、療治にはそれ相当の・・」
鼻にツンとくる臭気があった。
大人の女を知らないで育った亭主には、耐えがたい匂いだったのかもしれない。
嗅いだだけで胃の腑がせり上がるような感じがしたろう。
本来なら、その匂いを嗅ぐと収まりがつかなくなる部分がある。
それが逆に作用すると、狭心症の前兆のような悪心を覚える。
だが、男にとってそれは、未通に限りなく近い。
完璧なまでに寝取るには、これほど好都合な条件はなかった。
「濡れ具合がよくわかりませんので、これを・・・」
程よい張り型を、担いできた薬箱の底から取り出すと、濡れそぼったソコに挿し込む、
「あああ・・・もう、もう」
掻き回しながら、垂れ流れるシルの具合を確かめ、
「ついでに奥の方もよく診てみましょう」
亭主では拝めなかった屹立を、そっと女に握らすと、待ってましたとばかりにシルが溢れた。
期待に震える指先が、そっと切っ先をなぞった。
今や遅しと先走りが、女に組み敷くべき強い意志を伝えた。
久しぶりに見る屹立に、すっかり魅入ってしまっている隙に張り型を引き抜き、
「どうしたい? ん?」
耳元で囁いてやった。
ツンと尖った乳首を弾いた。
「あっ、ああ」
もう、どうにもならなかった。
女に握らせたままの屹立をあてがわせ、ゆっくりと腰を使って挿し込んだ。
「あああっ、いい・・・」
首っ玉にしがみついてきた。
男は反り上がった己のモノで、隅々まで掻き出した。
新たな泉が、コンコンと湧き出てくる。
腰を打ち付けるたびに、シズク交じりの肉壁を棹が擦る卑猥な音が響いた。
皺袋を伝って、シズクが滴り落ちすっかりお互いの脚は濡れそぼっている。
何年振りかの陳棒にすっかり逝かされた人妻は、相手の言うがままに妙薬をあてがわれ、約束事を取り交わした。
終わった直後には、もう待つ身となっていた。
そう、肉に酔うと極端に女は様変わりする。
萱の原で橘遼と美也子が契ったように、太鼓をたたいて舞を踊るまで派手とは言わないが、
息を呑んで見守る観衆の前であからさまに結合部を晒し、
身悶えて、のしかかる男に出し入れを繰り返えさせていることでもわかるとおり、
視姦も快感を増す道具と捉え、怒張を底支えする覗き見をわざとさせるため、あえて呼び寄せるような行動を取るようになる。
付け火をした人物は、その点を重視し、ご婦人がその域に達しかけると、サッと身を引いて後継に譲っている。
よほどの身分だったと見える。
肝心なところはこの点で、本格の不貞好きな身体になってしまったご婦人は、爺様たちがご婦人方の前に堂々と現れ、意気揚々と誘って挿し込んでしまうことが出来るほど、理性を欠いて誘ってきている。
好意さえ示してくれれば、誰彼構わずまぐわうんだというほど欲を纏ってしまっている。
そうなる直前に身を引いたことになる。
ほんの少し前の時代なら、冬場の雪に埋もれ農作業に従事できない時分には、飯盛り女・酌婦として湯治場で、亭主了解のもとで身を売った。
それからすれば、時代が少し変わっただけで、身を売るのも快楽が好きなればこそ苦も無く出来、亭主も大目に見てくれればこそ、陰で間男と契ることもできたといえる。
最高学府に学びたいが、学費はともかく、生活費の工面が出来ないと身を売る・・・は良く知るところ。
社会に出て、結婚するに至っては、当然処女として振る舞うが、実は至る所に映像が出回っていたり、その世界では超有名人だったりもする。
性に対し、あけっぴろげになっていく女性に反し、男性は身分に縛られ、物陰に潜んで事をなしたがる。
こよなく淫行に溺れてしまったオーナーだったが、水飲み上がりの悟が最初からこのような真似ができるとは思っていなかった。
「裏には、誰か別に人物が介在している」
それを突き止めれば、ひょっとしたら会社を再興出来はすまいかと考えた。
- 関連記事