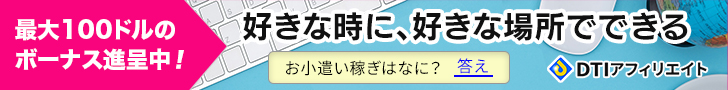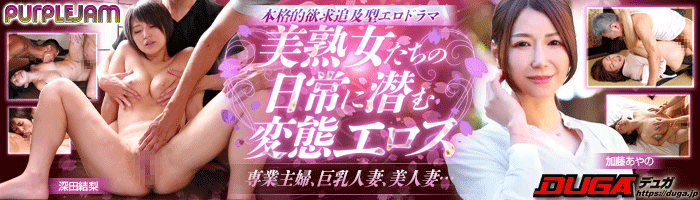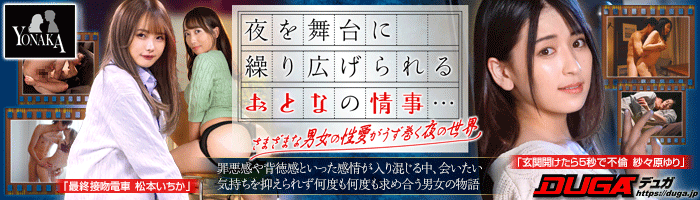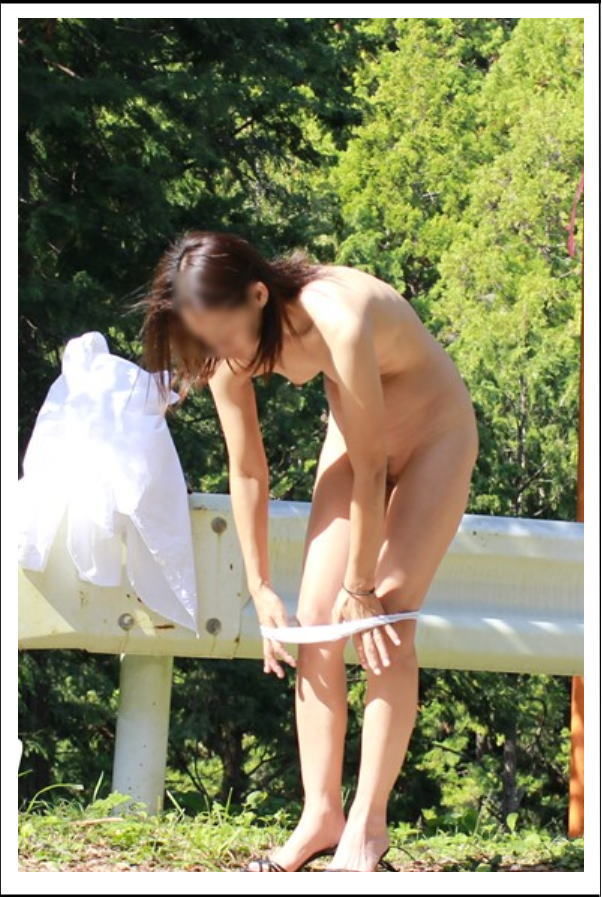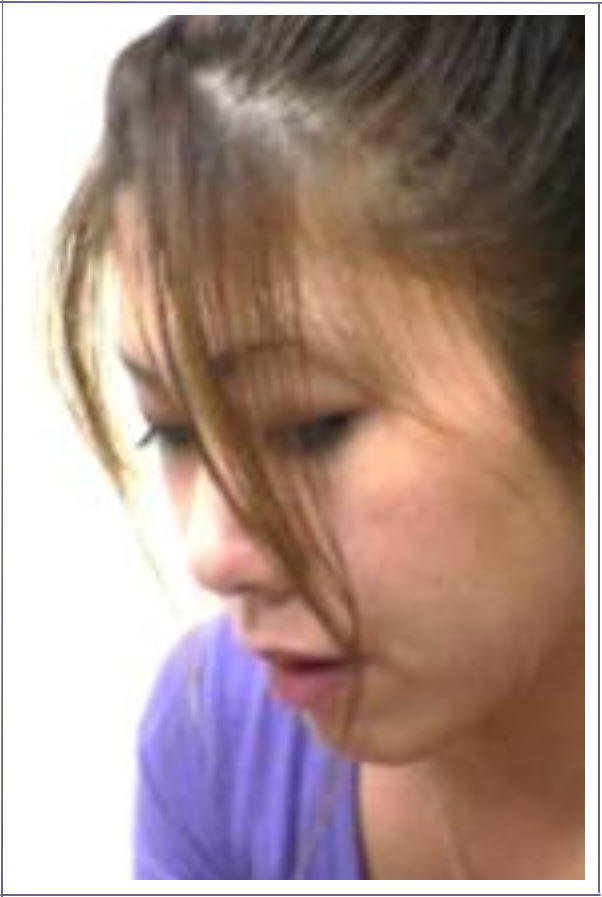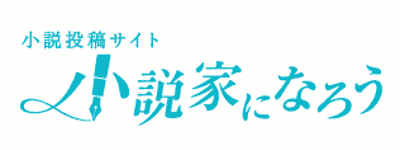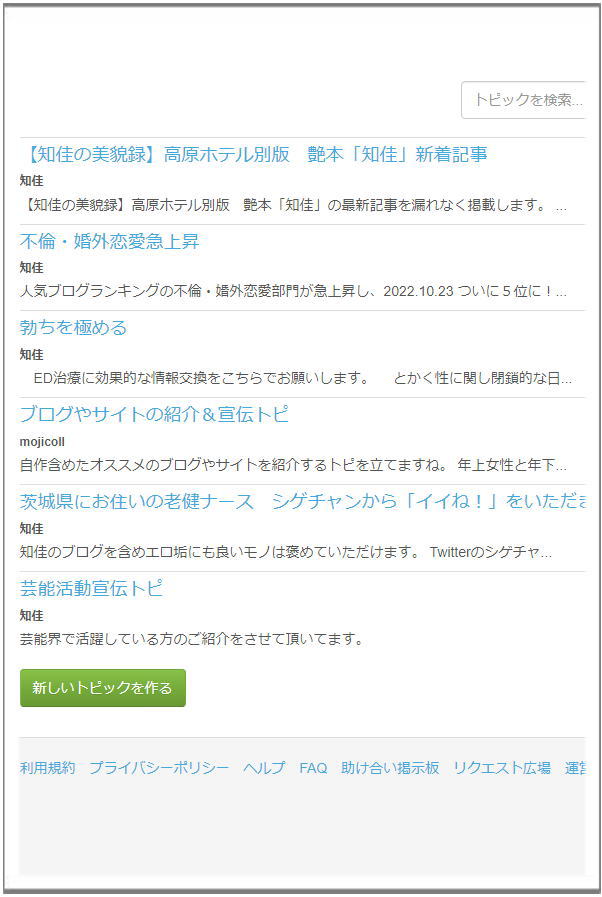淫靡な疼き 躊躇い
加奈の胸が喘いだ。
たまらなく恥ずかしかった。
ピンク色のシリコン製のバイブで久爾子に愛された。
その前にさんざん篠田に焦らされ、半端に身体が火照っていた。
だから久爾子に抱き寄せられた時に拒んだものの、いつの間にか優しすぎる女の愛撫を受けていた。
久爾子がないとテーブルの抽斗からバイブを取り出した時には唖然としたが、それもやがて受け入れていた。
肉の喜びに恍惚としていた時、篠田が唐突に寝室のドアを開け入ってきた。
思い出すだけで汗ばんでしまう。
消え入りたいほど恥ずかしかった。
「あんなに燃えていたのに一夜明けたらすっかり醒めてしまったのか?」
篠田が唇を緩めた。
「帰らなくちゃ・・・」
また加奈は繰り返した。
いけないことをしてしまった・・・。
そんな気がして空恐ろしい。
夫のことを考えると不安でならなかった。
昨夜の私は私じゃない・・・。
加奈は眠りに入る前の淫靡な時間を思い出し、自分の行為を否定した。
久爾子と破廉恥な行為をしていることを知った篠田は、それだけで我慢できなくなったと言い、加奈の目の前で久爾子を抱いた。
加奈は動揺し、昂った。
それなのに篠田は行為が終わるとさっさと眠ってしまった。
加奈は肉の火照りを覚ますため、こっそり指で慰めようとした。
それを気づかれ、結果的に篠田に火照りを消してもらうことになった。
何もかも夢のようだった。
いつものように正気なら久爾子が休んでいる同じベッドで自慰などできるはずがないししなかっただろう。
初めて他人の行為を目の当たりにし、おかしくなっていたのかもしれない。
「亭主のことが心配か?しかしそれなら父親のような男と3年も不倫を続けたりしなかったはずだ。亭主との生活に不満があるから外で男に抱かれていた。そしてまた昨夜から新しい時間が始まった。そうだろう?」
確かに云われる通しだった。
だがそれでも、篠田と深い関係になるとは会社勤めをしていた時でさえ考えていなかった。
話しを聞いて欲しかっただけ・・・。
ここに連れてこられたから、結果的にこんなことになっただけ・・・。
加奈は心の中で言い訳をした。
だが、篠田と久爾子の淫靡な時間はかつて経験したことのないほど強烈で蠱惑的だった。
「亭主に知られると修羅場になる。それが困るんだろう?平穏無事な生活の中で浮気が出来るなら、それに越したことはないって考えてるんじゃなかったっけ?」
図星なだけに言葉が出ない。
夫との生活は傍目には穏やかに過ぎている。
だが、加奈の中には夫婦の営みに不満があり、その欲求を満たしてくれる男が欲しかった。
それが亡くなった結城だった。
これまでの結婚生活のうち、半分は結城という男の愛があった。
結城が亡くなると夫とだけの性活が侘しく、他人も羨む性活だろうに哀しみと溜息ばかり。
平穏すぎる生活に、また石を投げこもうとしている。
いや、既に投げ込んでしまった。けれど、これ以上波紋が広がるのが怖い。
「連れ合いとの生活が破綻しないよう、最大限の努力をしよう。久爾子がいる以上、大丈夫だ。任せておけ。それとも、何もなかったことにするか?これからも、何もなしにするか?それならそれで仕方ないが」
篠田との関係がこれっきりになると思うと、家庭の不安よりめくるめく悦楽の時間が無くなるほうが惜しくなる。
愛する結城を亡くし、二度と再び悦びなど得られないかもしれないと思っていたのに、結城との営み以上に妖しい時間を過ごしてしまった。
将来これ以上の欲情を満たしてくれる者は現れないかもしれない。
今後、身体を開くことが出来る相手に出会う確率はどれほどだろう。
たとえ身体を重ねても、満足できるかどうかはわからない。
篠田の舌はまるで独立した別の生き物のように妖しげに動き回り、とろけるような悦楽を与えてくれた。
繊細に動く舌先も、確実に加奈を燃え上がらせてくれた。
久爾子の舌や口による愛撫も、そそけだつほど心地よかった。
短い時に様々な想いが加奈の脳裏を過ぎっていった。
「お終いにするか」
沈黙を打ち消すような篠田の口調が寝室に響き渡った。