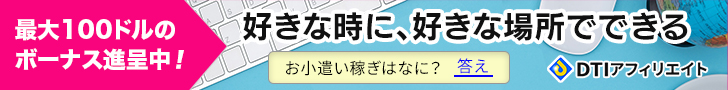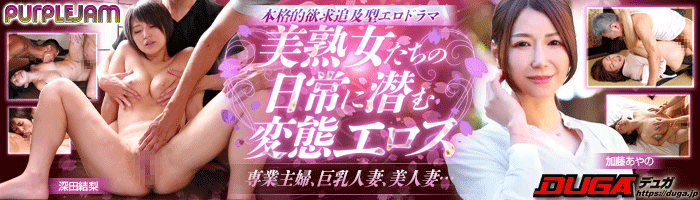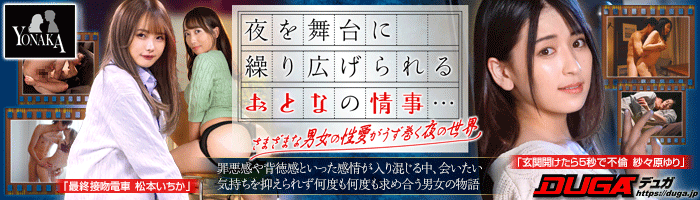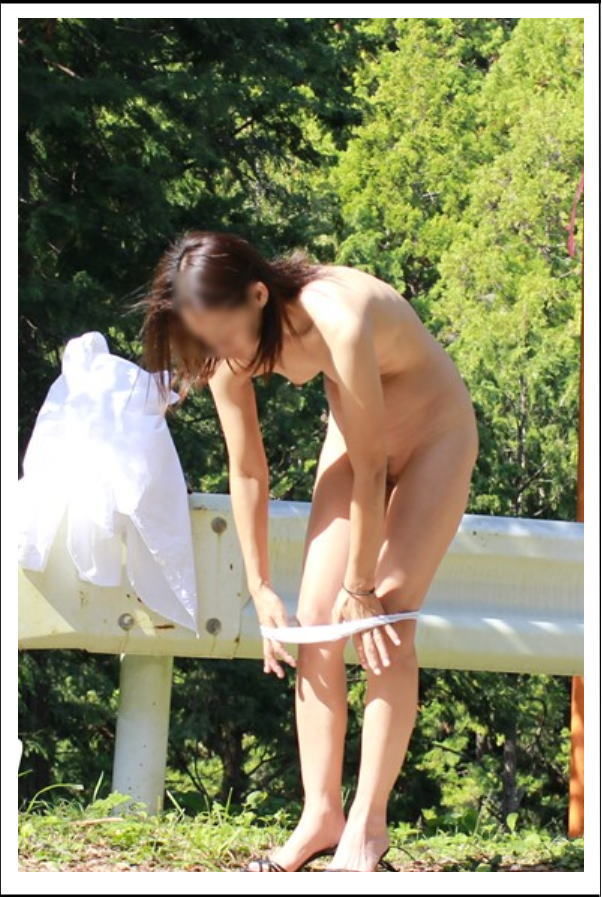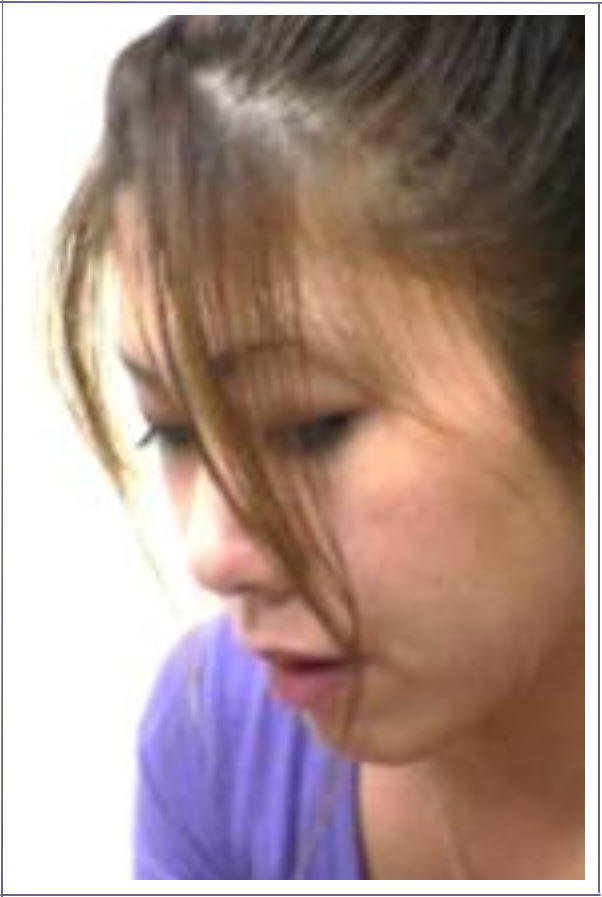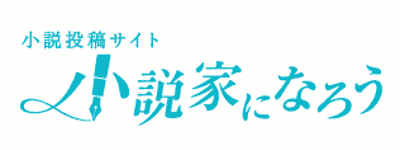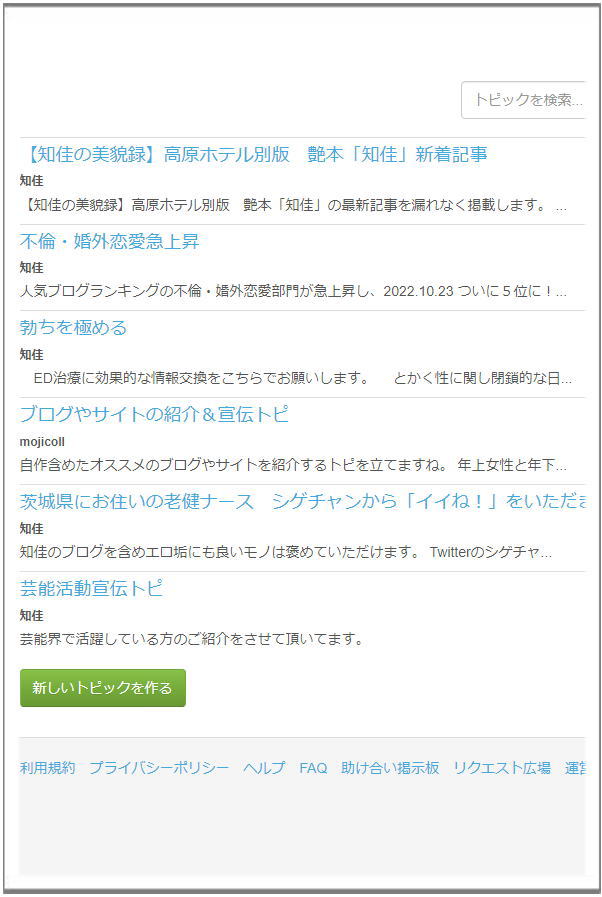美人ではあるけれど、何処か影があり しかも村でも一二を争う小柄さ、小さいがゆえに締りの良さを思わせ貞三郎さん、半勃ちであってもお世話になれるんじゃないかと樵道 (きこりもち) と言うより獣道と言った方が似合ってる山道を登って
珠子さんに逢いに・・・というよりお世話になりに出かけました。
険しい山道を登りつめ
安達家が見える峠に立って
安達家を見下ろしました。
安達家の
義道さんはマメな人で峠に通じる樵道 (きこりもち) の脇はきれいに刈り払ってあり家の周りの田畑が一望できるようになっているんです。
峠の三差路を谷に向かって下りれば
安達家、そのまま峠道を進めば
安達家の墓所に行き着きます。 貞三郎さんは峠に立ち
珠子さんの姿を探しました。
こんな山奥に住んでいて
珠子さん、樵仕事など一切やらず、もっぱら夫の
義道さんが耕してくれた畑の作物の収穫などを手伝い、残りの時間を家事に当てていると聞いていましたので、そのどちらかのいると思い畑を探しましたが見つかりません。
三差路を右往左往し
珠子さんを探し求めていた時、尾根道の
安達家の墓の方向から誰かがやってきました。
義道さんと出会ってはまずいと獣道を外れ大木の根元に身を隠す貞三郎さん。 ところがやって来たのは入江村でも棹癖の悪さでは評判のどこそこから嫁が嫁いで来たと見るや
足入れをやらかす、あの足羽
寛治さんでした。
すると安達家の田んぼの脇で小さな影が動き草刈りをしていたと思われる
珠子さん、草刈りを止め何かに吸い寄せられるように急いで峠に向かって登り始めたんです。
「遅くなったな。 義公に見つからんかったか?」
「あん人は今日は農協に行っとんさる」
「そうか・・・ 今日は炭の検査の日じゃったのう」
そう、
珠子さん 草刈りを擂るフリをして足羽
寛治さんが来てくれるのを待っていたんです。
炭焼きに適した良い材料に恵まれていながらこの村では白炭 (いわゆる備長炭) ではなく黒炭 (大量生産向き 燃焼温度が低く燃え尽きやすい) を焼いていました。
「止めちょけ言うたのに、ま~た火口に水ぶっかけたとか」
「あん人は力任せに木ば切り倒しんしゃる」
「検査員も歳食うとる。 炭俵持ってみりゃわかる」
検査とは半ば強引に水をぶっかけたりして火を消し生焼けの炭を作っていないかを持ち込んだ俵の中からランダムに俵を破り中の炭を手鉤で叩いたり、叩き割って内部の光具合を調べたりし等級を決めることを言います。
「おまんは行かんで良かったか?」
「真っ黒になって炭焼いてなんぼ稼げる思ちょりなさる?」
体躯も良く、ひょうひょうとした顔立ちに惚れて嫁いで来たものの、こんな山奥に暮らすことになるとはと愚痴を言い始めたんです。
「ほうかほうか、うん分かった。 何ぞええもんがあったら・・・」
「ほんに
寛治さんはええ人じゃ」
「ほいでの」
道端にべたりと座り込み話し始めたと思う間に
寛治さん、珠子さんの
モンペの中にモゾモゾと手を挿し込んだのです。
「スケベじゃのう、
寛治さんは」
言うが早いか珠子さん、
モンペをつるりと下げてアソコを丸見えにし指で開いて具を魅せ
寛治さんに
媚び始めました。
「ゆんべ使うたか?」
「気になさるんかいのう。 調べてみんさりゃ・・・」
珠子さん、寛治さんに棹を射れてみたらわかるだろうと言いけしかけました。
ご主人が出かけて行った農協方面への獣道はこの峠とは真反対の山を越えねばならず、用事を終えて帰って来たとしても滅多に出向かない入谷村方面に通じるこの峠には足を向けることはありません。
「義道は儂のことをなんと言っちょる」
珠子さんの股座 (またぐら) に顔を埋めカスやシルを舐め取りながら珠子さんの気持ちを探り始めた寛治さん、
「ま~たそれかいな。 嫉妬深いのう寛治さんは」
珠子さんは偶然を装い脛で寛治さんの膨らみ始めたアソコに触れ興奮し始めました。
こうなって初めて寛治さん、自分が地面に横になり珠子さんを顔面騎乗させたんです。
この時代、相舐めなどという荒業は寛治さんぐらいの遊び人しか知り得ません。
斜面に向かって下に頭を向けているのが寛治さんなら斜面の上に頭を向けているのが珠子さん。 下方から
義道さんの専用物を執拗に舐め上げられた珠子さん、屹立に掴まってはいるものの混乱が募り寛治さんの顔面に全体重をかけてしまいました。
「ああああ・・・いい・・・ 寛治さん、睦美さんに使わんとってな」
「わかっちょる。 儂は珠子だけじゃ」
「珠子って呼んでくれるん?」
それが合図となって寛治さん、珠子さんの下から這い出して後方から覆いかぶさり腰を使い始めました。
貞三郎さん、珠子さんと寛治さんがまぐわってる真下の大木に身を潜めていたものですから結合部が丸見えになってしまいました。
最初のうちは棹がめり込む折にチラチラとピンクが見えていましたが、時間と共に白濁液が棹にまとわりつき、ついに糸を引くようになっていったんです。
ゆらゆら揺れる乳房の向こうから珠子さん、鋭い視線を貞三郎さんに投げかけているのに気が付いたのは自慰で逝きかけたときでした。
亭主の稼ぎで遊んで暮らしているとはいえ幽閉の地、珠子さん、存外五感が鋭かったんです。 貞三郎さん、慌てて粗末なものをズボンの中に隠し再び身を潜めました。
程無くして寛治さん、珠子さんの中にしたたか飛沫き、手土産として巾着に
ぶえん (生魚) を入れたのを手渡しました。
ぶえん (生魚) はこの時代、こういった過疎地ではまず口に出来なかったからです。
珠子さん、ご主人の体躯を維持するため入谷村の男たちに
ぶえん (生魚) を無心し、お礼としてアソコを差し出していたんです。
寛治さんの姿が見えなくなったのだから、次は自分の番と貞三郎さん、じっと待ちましたがとうとう声を掛けず珠子さん、帰って行っちゃいました。 残してくれたのは獣が争ったような跡だけでした。
かくして貞三郎さん、最初の
足入れに失敗しました。
 就職のため里に下りてもう5年、女っ気のない生活を強いられて嫌気がさし入谷村に帰って来た貞三郎さん、入谷村に帰れば冨子さんのようなおばさんがシモの処理をしてくれるものと信じていましたが圧倒的に男性が多い中にあって若輩者ゆえ中々声がかけられず、諦めて再び里に出ようと考えていました。
そんな時に思いついたのが安達家の珠子さんで、役場の管轄では隣村に属しますが位置的には入谷村が最も近く、交流も半々になっていて年に数回顔を合わせますので雰囲気も良く知ってました。
学生時代に伝え聞いた噂によると ふた山越えた所にあるポツンと一軒家の珠子さん、頼みもしないのに入谷村の男衆を気の毒がってご主人の義道さんに内緒で時折くぱーしてくれるというんです。 とすれば、年に数回出逢ったのはそのくぱーに下りて来てくれた時?と思えたのです。
滅多に訪れる人とていない過疎地にどういう経緯で嫁いで来たか知らないけれど すこぶる美人の奥さんは界隈イチと思える体躯のご主人じゃ物足りないのかしょっちゅう遠く離れた入谷村内のあちこちの炭焼き小屋を訪ねては他人棒のお世話になり、いくばくかのお土産と言いますか貢ぎ物を手に帰っていくらしいんです。
就職のため里に下りてもう5年、女っ気のない生活を強いられて嫌気がさし入谷村に帰って来た貞三郎さん、入谷村に帰れば冨子さんのようなおばさんがシモの処理をしてくれるものと信じていましたが圧倒的に男性が多い中にあって若輩者ゆえ中々声がかけられず、諦めて再び里に出ようと考えていました。
そんな時に思いついたのが安達家の珠子さんで、役場の管轄では隣村に属しますが位置的には入谷村が最も近く、交流も半々になっていて年に数回顔を合わせますので雰囲気も良く知ってました。
学生時代に伝え聞いた噂によると ふた山越えた所にあるポツンと一軒家の珠子さん、頼みもしないのに入谷村の男衆を気の毒がってご主人の義道さんに内緒で時折くぱーしてくれるというんです。 とすれば、年に数回出逢ったのはそのくぱーに下りて来てくれた時?と思えたのです。
滅多に訪れる人とていない過疎地にどういう経緯で嫁いで来たか知らないけれど すこぶる美人の奥さんは界隈イチと思える体躯のご主人じゃ物足りないのかしょっちゅう遠く離れた入谷村内のあちこちの炭焼き小屋を訪ねては他人棒のお世話になり、いくばくかのお土産と言いますか貢ぎ物を手に帰っていくらしいんです。