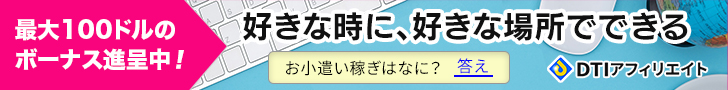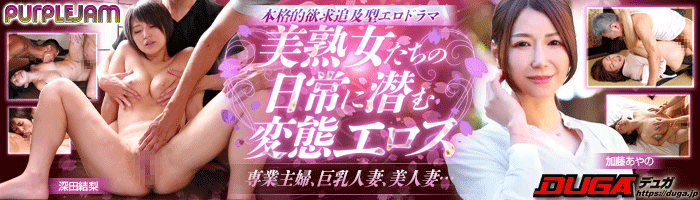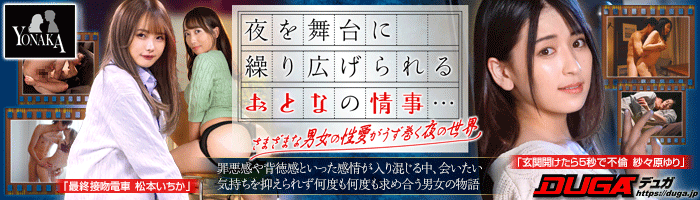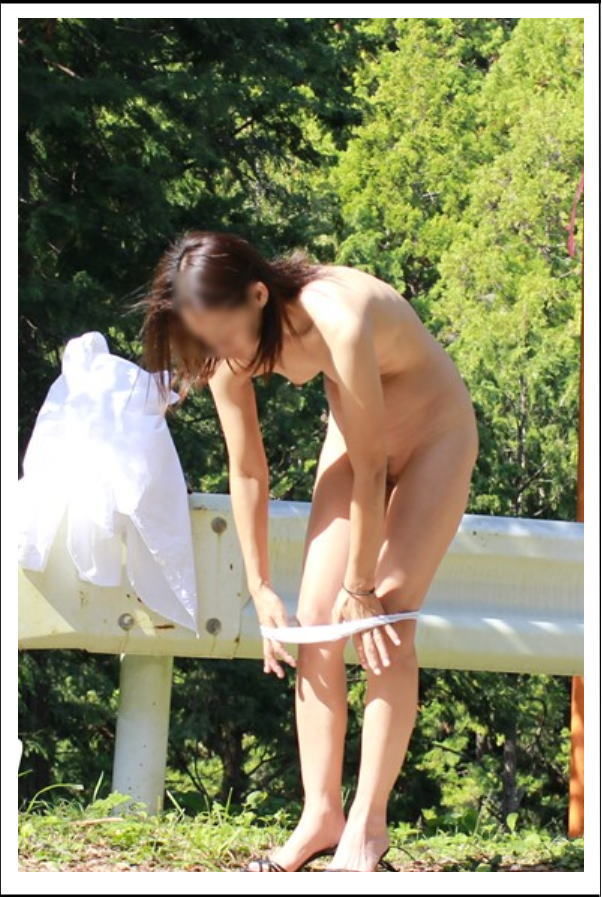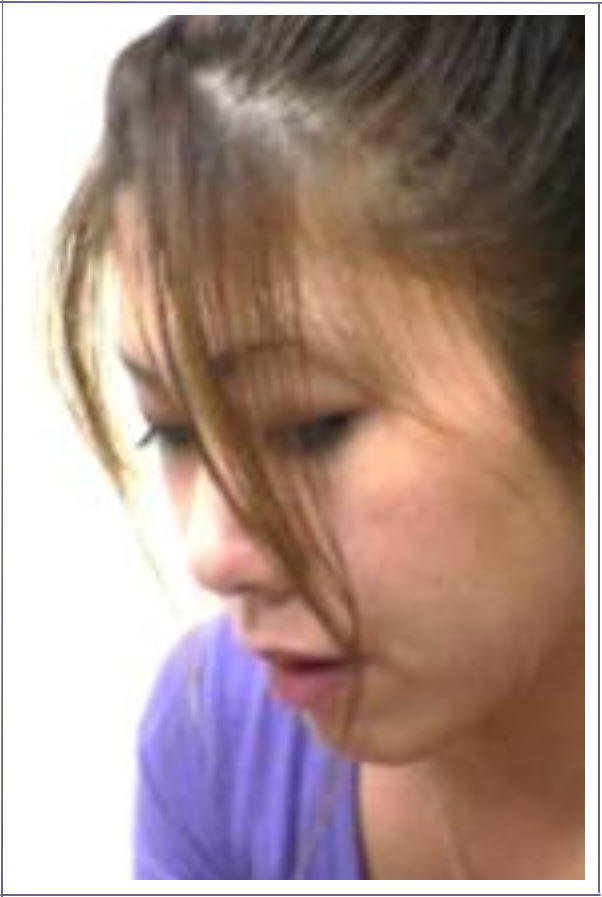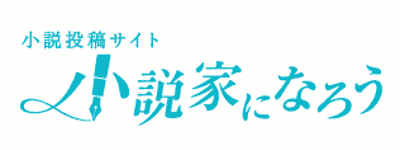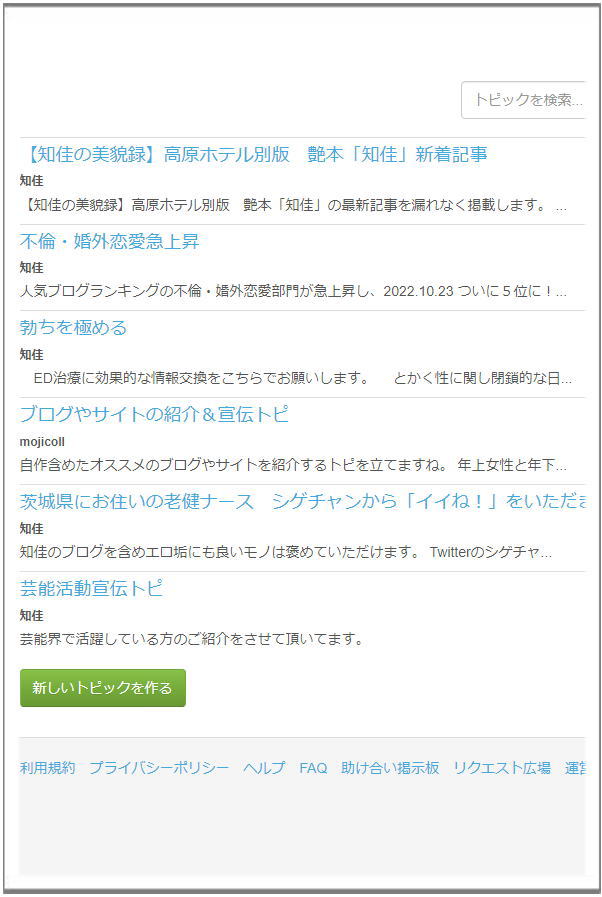紗江子の入り口は狭くても中は大人の女として熟成し切っていた
真面目一徹の男で、仕事以外はこれと言って趣味を持たない仕事人間だった。
先に結婚した友人が持ってきたお見合いパーティーで知り合った当時の紗江子は
そんな洋一に期待を膨らませていた。
学生時代から憧れていた自分なりの3高の条件 長身、裕福、美男にぴったりだった。
これだけ恰好が良くて、しかも仕事が趣味なら浮気などの心配もいらないし
しっかり稼いでくれれば家庭も将来も安泰だと思っていた。
母子家庭に育った紗江子、その苦労続きだった母ですら「よくこんないい男を見つけたね」と
手放しで喜んでくれた。
紗江子の幼少期は極貧に喘いでいた。
苦労して育ててくれた母、その影響もあって成長しても小柄で太っても体重は40キロにも満たない
そのかわり、母子を捨てて行った父の血筋か目鼻立ちはスッキリとして綺麗で、おまけに頭脳明晰だった。
唯一の欠点と言えば冷蔵庫もろくにない家庭で育ったためか料理は作る材料にも事欠き不得手だった。
幸いにして夫の洋一のご両親と同居ということ、義理の母が料理が得意だったおかげで夫は食通で
夕食だけは義理の母、姑さんが作ってくれていた。
だから、仕事から帰った夫は実の母の作ってくれた食事を摂り歓談し、
何もかも終わって初めて紗江子と顔を合わすというような生活が新婚当初から続いていた。
当然夜の生活は希薄で40歳を目の前にしながら紗江子には子供ができる気配がなかったし、
その分若々しかった。
ではなぜこのように紗江子が夜型生活になってしまったかというと、洋一の母は料理が出来ても
片付けは大の苦手だった。
掃除や洗濯は、だから時々家政婦さんを雇ったり業者に来てもらったりしながら間に合わせていて
たまたま嫁いできた紗江子が母子家庭でそれらが得意だったことからお鉢が回ってきただけのこと
家族が寝静まった深夜になってから台所を片付けし、洗濯をしてから床に就いていて、夫とは
全く歯車がかみ合わなかったが、裕福というだけ母子で暮らしていたころより楽だったため
疑問だに持たなかった。 少なくとも青年と出会うまでは。
青年は出会ってすぐに気づいてくれていた。
大人の女性とは思えないほどかわいらしい彼女の秘部の入り口は未だ開発されずにいて
とても狭く、ただでさえ敬遠されてしまうほど太く逞しい青年のそれを埋め込ませると
苦痛を伴うと。
そこで青年は最初に彼女の下に潜り込み舐めることから始めた。
散々舐めて潤ませ、ホトホトに柔らかくし それでも最初の少なくとも1時間は亀頭をあてがうだけで
挿入は避けた。
痛みに耐えさせるには紗江子が彼の怒張が欲しくて悩乱し自ら挿し込みに来るのを待ってやった。
夫の洋一のそれは大きくなったとしてもせいぜい5センチ程度で、入り口から僅かに先端が入るだけ
それでも狭い紗江子の膣入口ならそれで通用した。
だが、紗江子の入り口は狭くても中は大人の女として熟成し切っていた。
朝寝が得意と思われた紗江子が、ある日を境に突如としてご主人が出かけた瞬間に飛び起き
シャワーを浴び出かけたりしたのは熟し切って、どこから押し寄せているのかわからないが
悩乱が治まらなかったからに他ならなかった。
「ああ・・・」
青年が足元から覗き込むように紗江子の秘部を睨みつけたときの青年の股間のふくらみに、潤んでしまった
自身の秘部に甘い吐息を思わず吐いてしまっていた。
「脇にどけて・・・お願いもっと見て!」
青年にこう迫ったのも秘部を青年の逞しい亀頭で押し広げ中を掻き回してほしかったからだった。
「ああ・・」
「初めて見たときからあなたが好きでした」
青年に告白された。
「わたしも・・・一緒に行動しているうちにこうなりたいと思ったわ」
秘部を舐め続ける青年の顔に手を添えながら、そっと股間に引き寄せる仕草をした。
「紗江子さん・・」
「はい・・」
「力を抜いてらく~にしてください」
青年はここで初めて紗江子のパンティーのゴムに手をかけ引きづり下ろした。
その間にも膝といわず太腿といわず舌を這わせるのを止めなかった。
引きづり下ろしながら やや後ろに回り込み秘部から続く孔にまで舌を回りこませ、下腹部全体を柔らかくした。
下から見上げると、豊かな繁みの下にピンク色に色づいた一本のスジが見え、まばらに枝が伸びるその先端に
朝露が光り輝き滴り落ちるさまが見て取れた。
フォト股の内側に舌を這わせ昇っていくと、スジはグニャリと形を変え 森全体が小刻みに痙攣を繰り返し
それにつられて何処からか泉が湧き出し、太腿を伝う。
「・・・あああっ・・」甘い声が、えも言われぬかぐわしい吐息が漏れた。
ポチッとお願い 知佳


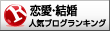
恋愛・結婚ランキング
- 関連記事
-
- 狭い通路をかいくぐって彼女を割る
- 紗江子の入り口は狭くても中は大人の女として熟成し切っていた
- 弥生の膣開発・中逝きも 素人人妻の動画撮影が目的だった。