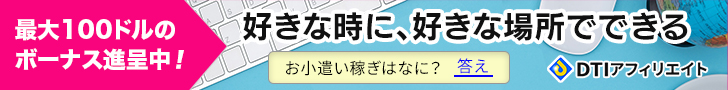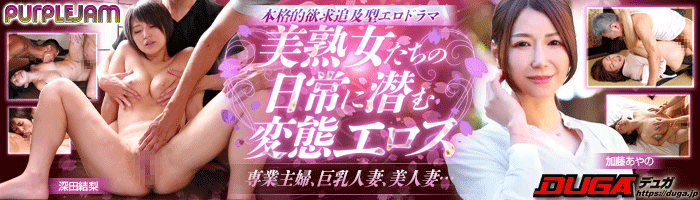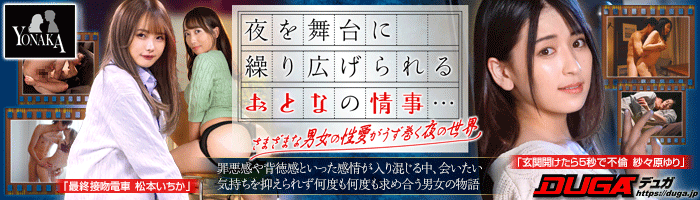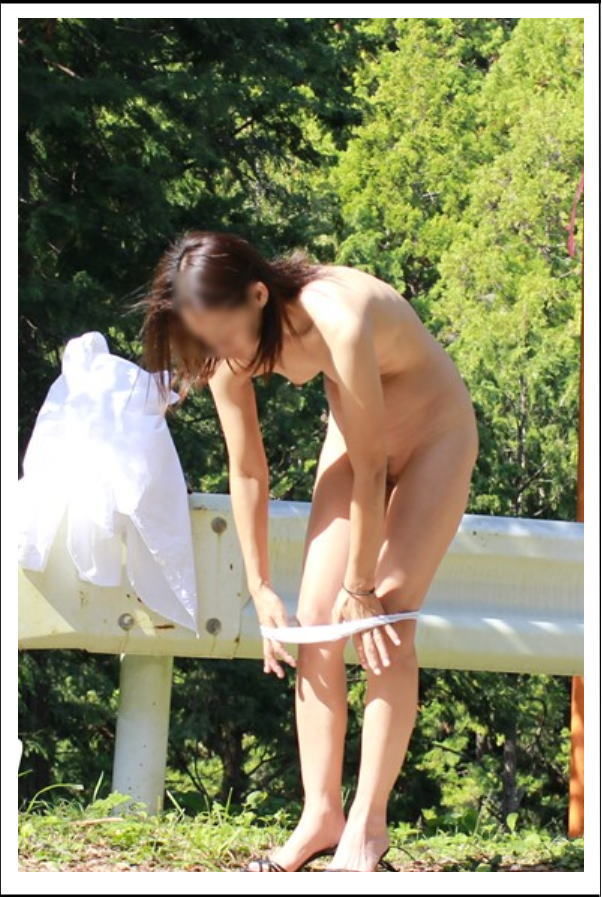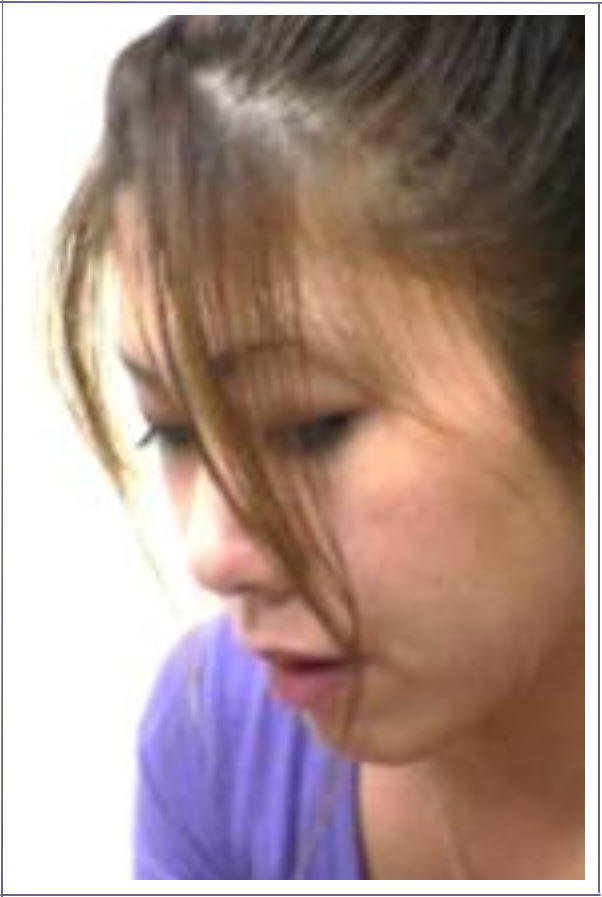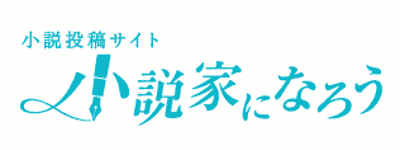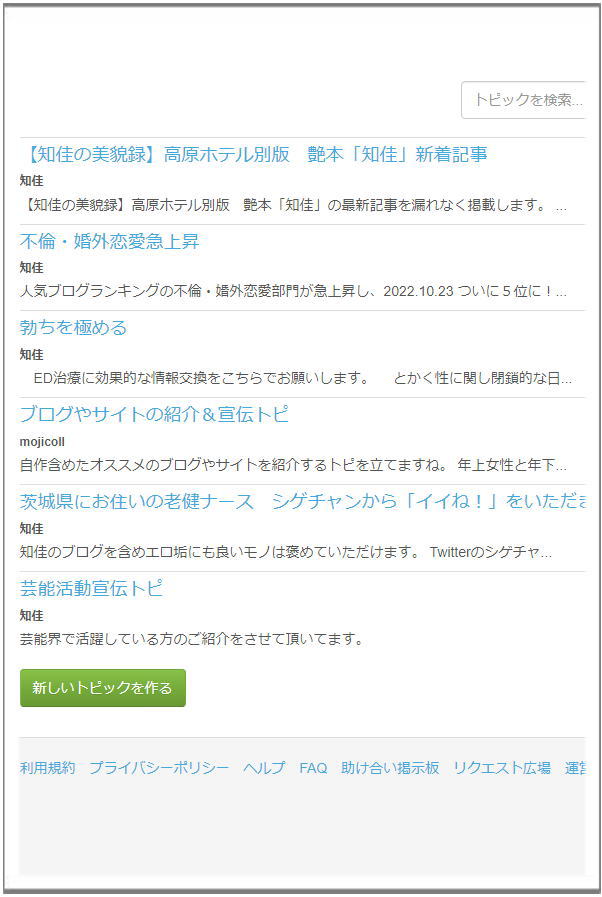渓流に舞う白い蝶 妻の冴をとの上司の提案に転職を繰り返す啓介の心は揺れた。
まだ外は明けきらない上に、どんよりとこの地方独特の雲が垂れこめている。
この暗さが人恋しさを募らせるのだろう。
和子は先ほどまでベッドの中で過ごしていた。
街で知り合ったばかりの既婚男性と、その日のうちにベッドインし、
いつの間に消えたかわからない男を薄暗がりの中 手探りで探し、いないと知ってその失望に目が覚めた。
既婚男性との逢瀬と言っても、相手が左手の薬指に光るものをつけていたとか、
誰かの噂話で素性を知ったわけではない。
あくまでも和子の感だったが これが外れたためしはなかった。
陽は西に傾き、暮れ始め、頼りなげな街灯の明かりでそれとわかる暮れなずむバス停に通ずる道を傘もささずに小走りで駆け抜けてくる男がいた。
脇道から飛び出してきた和子とぶつかりそうになって慌てた男は手に提げていた書類を水たまりの歩道に落としてしまっていた。
「急に降り出して・・・ 嫌ね、秋の空って気まぐれで」
「あらあら大変!!」
素知らぬ顔で和子は男の落とした書類を拾い上げた。
「すみません。書類が雨で濡れそうで急いでいたもので。ケガとかしなかったですか?」
「いいのよ、気にしなくて。 あれぐらいで転んだりしませんから、それより書類、ちょっと濡れちゃったけど大丈夫かしら?」
「あっ、大丈夫です。どうせ上司への報告書で取引先に提出とかじゃないから」
「そう・・・でもこれからバスに乗って帰るんでしょ? 私が飛び出したばかりに、ひょっとして乗り遅れちゃったわね」
「仕方ないです、ギリギリの時間まで会社で粘ってた僕が悪いんだから」
男の慌てていたわけはすぐに分かった。
このばすでバスターミナルまで行き、別路線のバスに乗り換えるわけだが、過疎の村に向かう最終バスはもう出た頃だと言った。
「そうだったんだ・・・ ごめんなさい、それじゃお食事もまだだし今夜泊まるとこもないわね」
「へっちゃらです。慣れてますから」
こんな日はネットカフェとか、会社の応接用長椅子で、暗くなりそうか表情を、敢えて笑顔で繕った男の横顔に疲れが見えた。
「それじゃ私の部屋に来ない?」
「いっ、いえそんな!!! 貴女に迷惑かけられません」
「こうして出会ったのも何かの縁だし、私の手料理で良かったら出逢いに乾杯っていうのはどう?」
それともぶつかってきたのは計略の内で、部屋に入った途端、私を襲うとでもいうの?
「本当のこと言いなさいよ! 狙ってやったのね!?」 まるで今にも叫び出さんかの如くの剣幕でまくしたてた。
ここで断りでもすれば大声を張り上げかねない和子の勢いに気圧されるように男は和子の後ろに従って歩き始めた。
降り注ぐ晩秋の雨が和子に、人肌恋しさを募らせていた。
その夜のセックスは帰り路半ばに既に始まった。
和子の差し出す小さな雨傘に、ガッチリとした体格の男は入りきらず雨傘から垂れ落ちるシズクが肩先を濡らす。
わざと男の肩先を濡らしておいて和子は、
「肩が濡れちゃう!」 そう云うなり男の胸元にしがみついた。
鼻腔をくすぐるような甘い和子の臭い、柔らかな感触につられ、仕事に疲れた男の理性が粉々に吹っ飛んだ。
もつれあうようにして雨の中を歩いたが、あいにくの雨とあって一通りは全くない。
それを良いことに立ち止まっては互いを確認し、歩き続けた。
そっと潜ませる和子のしなやかな指が熱くなった膨らみを捉え、お返しは小さな布切れ越しに行われた。
懸命に背を低くする男の首っ玉にしがみつくようにして和子の唇が男の舌を捉え自信を絡ませた。
マンションのエレベーターが昇りきるまでの時間が待てないほど燃え上がり、玄関ドアを開けて中に雪崩れ込んだ途端、
和子は男の体重をその華奢な身体に受け押し倒され「食事がまだでしょ」と遮るのに苦労したほどだった。
和子が睨んだ通り、ファスナーの下に隠された皺袋は巨大、
それに反し、欲望に我を忘れた和子の前に晒した瞬間の棹は、普通並みだった、が、
男は和子のしなりに合わせ、棹を逞しくすることを普通にやった。
ペッティング・クンニを時間をかけて行おうとする男に、ついに和子が先に折れた。
アフターピルは間違いなく飲んでいる、にもかかわらず危険と感ずるほどに探られ広げられ、注がれた。
姿見に映る自身と男の絡みは、まるで小さな女の身体の中に巨躯全体をめり込ますかのごとくに映る。
< 入ってきてくれてる・・・この人、本気になって割り入って・・・ >
幾度となく淫裂深く搾り取らされ、ようやく解放されて和子が眠りについたのは窓の外が白んでからだった。
セックスに対する大らかさはこの地方とて特別ではない。
既婚男性に許されても、既婚女性のソレは決して許されない。
最初こそ、物珍しさも手伝ってか夫も大目に見てくれたのではなかったのか、
垂れこめる雨雲を見つめながら、心は過ぎ去ったぎらつく太陽のもとに跳んでいた。
独身の和子は人恋しくなると薬にはなっても毒にはならない男を選んで声をかけさせ身体の関係を持った。
その中にほどなく定年を迎える、ある会社の幹部社員がいた。
とかく部下の面倒見がいいこの万年平課長の、唯一の取り柄が度を超えた頭の低さだった。
「おはようございます、新藤さん。いつもご無理ばかり言って申し訳ないです」
中途採用で入ってきた新藤啓介にも頭を低くして自身のサポートを願い出るほどだった。
「こんな時間まで残業させちゃって、ホント申し訳ない」
デスクの脇に並んで下目線でこの言葉を発したなら啓介は即座に仕事を放りだし、辞職したろう。
ところがこの万年平課長の長瀬時雄はデスクの前で深々と頭を下げてきた。
まるで平社員が課長に呼びつけられ怯えきって平身低頭の図そのままだった。
「そんな恰好やめてくださいよ、先輩たちだって残業してるじゃないですか」逆に啓介こそジロジロ見られ小っ恥ずかしかった。
「イヤイヤ、彼らは自分の仕事やってるんで、僕の仕事手伝ってくれてる新藤さんとはわけが違うんですよ」
「ふ~ん・・・ そうなんだ・・・」 転職に転職を重ね、歪み切った啓介の心を癒すような課長の気配りだった。
なんとなく納得できたような出来ないような気持ちでいると、
「どうです?日を改めて」 お猪口を口には首仕草のそれで一杯やりませんかと誘われたのである。
この一言で啓介は ”ついに自分の価値が認められたんだ” と有頂天になった。
そんなある日のことである、啓介が勤めることが出来たような下請け零細企業には外回りという大事な仕事がある。
その日新藤は長瀬課長のお供を授かって外回りに出た。
なにしろ零細企業、社用車はほとんどなく啓介は長瀬の車の助手席の乗せられ、なんだか見も知らぬ僻地に誘われた。
< ひゃ~っ、こんな田舎に取引先あるんだ~ 流石我が社だな~ >
製造業ともなると人件費が安い山間地に製造拠点を設けると話には聞いていたが、まさかと思った。
途中の分かれ道から分け入った林道は、下手すれば転落して一巻の終わりと思えるほど狭路・悪路の連続だったからだ。
< こんな場所に、よく住めるよな~ >
そんなことを考えていると小さな広場に車は止まった。
そこから先は行き止まりと思えるほど狭路になっていた。
終末の午後、山奥の簡素な駐車場に車を止めおくと、課長は生き生きとして先に立って藪の中に分け入る。
このような僻地は手慣れたものと見え、トランクから取り出したリュックをいつの間にか背負ってトレンカに履き直している。
小高い丘をぐるりと回って辿り着いたのが巨岩の間を清流が流れる別天地を見下ろせる大きな木の根元、
そこにドッカと腰を下ろした。
リュックから取り出した手拭いで噴き出た汗を拭うと、
続けて巨大なレンズ付きのカメラを取り出し、三脚の上に取り付けだした。
< えぇ~~、まさか熊でも撮る趣味あるんかいな・・・ >
それはもはや怯えに似ていた。
狙いすます眼下の渓流に、それらしき獲物の蔭は見えない。
あたりを静寂が包んだ。
聞こえてくるのは渓流のせせらぎと耳元で飛び交うブユの羽音、
汗のにおいを嗅ぎつけてか、矢鱈滅法ブユが五月蠅い。
誰もいないと思ってみていると、清流脇の木陰から薄絹だけを纏った女が現れ、水と戯れ始めた。
行先が渓流とは知らされていなくて、水着を持ってきておらず、仕方なく決心の末脱いだのかもしれなかった。
「フフフッ、お楽しみはこれからですよ」 唸るような課長の声、
暫く清流で戯れていた女が急にキョロキョロとあたりを見回し始めた。
何か、誰かいないか確認すると小さな流れにしゃがみこみ、おしっこを放ち始めた。
黄金の水が清流めがけて迸った。
放ち終わったアソコを、その流れで洗うのかと思いきや、
シズクを滴らせたまま再び岸辺で戯れ始め、
立ち止まるとシズクが垂れるアソコに指を挿し込んで、あらぬ方向を見ている。
「ふふっ、頃合いかな?」
誰かがフイに襲ってきて、旦那の目の前で犯されそうになる。
そんな淫らな情景を思い浮かべるにピッタリな光景になりつつある。 「飢えてるんじゃよ、あのメスはよ」野太い声が脇で発せられる。
裸身の女が戯れ始めた水辺の、ほんの少し離れた場所で微かに煙が立ち昇っていた。
「旦那とキャンプでもするつもりで来たんでしょうがね・・・ふふっ、ふっ」
こんな良い場所を知っていたとでも褒め殺し、手渡しておいたものを飲ませたんでしょう、
「旦那が邪魔する心配は絶対にありませんよ」
よく観ててごらんなさい、面白いものが始まりますから、
そういい終えた長瀬課長の股間は、はっきりそれとわかるほど膨らみを増していた。
旦那は爆睡、その隙に・・・ それがこの計画と長瀬が口にしてしばらく、
何処から現れたのか、数人のこれも半裸の男たちが白い蝶のように渓流に舞う女目掛けて群がった。
「外回りのターゲットには、彼女らのような身を持て余す奥様も含まれてましてね」
日頃レスで溜まりきったソレを、ああやって寝盗ってあげることでお仕事を回していただけるんです。
「オカズには最適でしょう?」
どうです? 新藤さんも奇麗な奥様がああやって辱められ、悶え苦しんでくれたとしたら
「それでもまだ勃ちませんか」
なんなら、計画に必要な費用とか案は残部出しますよ。
せっかく注いでくれた大吟醸を半ば溢してしまってもそれと気づかないほど啓介は興奮した。
「あれが寝盗りか」
白い蝶がゆらゆらと渓流の谷間を逃げ惑う、
右に逃げては 通せんぼした男にぶつかり左に逃げ、
上流に逃げては屈強な男たちに押し返されて下流に逃げるが、
上流に立ちはだかる滝には抗いきれず、さりとて下流は断崖絶壁のような急流になっていて、逃げ惑おうにも目の前の小さな水辺しかなかった。
小さな悲鳴を上げて逃げ惑っていたはずの女は、
次第次第に間を狭めてきた男たちの輪の中に取り込まれるような形になった。
男たちが人妻を追い込もうと画策したのは旦那が眠る岸辺と渓流を挟んだ反対方向だった。
目を覚ました旦那から丸見えの好位置に、追い込みの場所を構え嬲り始めた。
何しろ清流に放ってシズクが垂れるアソコに指を挿し入れ、
うっとりするほど飢えていた人妻、
ひとたび追い詰められ逃げ場を失うと、あとはもう男の要求に唯々諾々に従ってしまっていた。
頭をがっしりと掴んで女の顔を己の股間前に固定させ、隙が出来た腹や臀部に別の男が持ち物を擦り付ける。
アソコに手を差し伸べることを差し控え、女の耳たぶや乳房をまず嬲った。
「誰も見てやしないじゃない、強情はらなくても告げ口なんかしないからさ」
「奥さん、こんなに我慢できなくなった俺たちに、このまま何もしないで帰れっていうのかい?」
人妻の身体が身の置き場所に困り蠢き始めた。
「ちょっとぐらい含んでくれたってバチ当たらないと思うよ」
臭い立つアソコを頑なな彼女の口元に運んで自虐的な言葉を吐く。
「お前らのサービスが足りないから奥さんその気になれないじゃないか!!」
脇腹に執拗に先走りが始まった屹立を擦り付けていた集団の中では特にイケメンの男に向かって、
彼女の頭を押さえ込んだ男が軽く蹴りを入れた。
「ヤメテください乱暴は!!」
ややもすればイケメンの屹立に応じようとしていた彼女はついに、押し付けられたソレを含んだ。
「おっさんよ~ 蹴ったりしないでやってくれないかな~ ほ~ら奥さんのアソコ、イケメン君が欲しくてもう糸引いてるじゃない」
可哀想にと言いながら、そっと指をアソコに忍ばせたのは太腿を屹立で嬲っていた男だった。
真っ白で小柄な肢体の、なお小さなアソコに向かって赤銅色で毛深い巨躯の節くれだった持ち物が情け容赦なくめり込む。
夫を呼ぶか弱い悲鳴と逝くまいと耐えながらの喘ぎを漏らし、まぐわいが目を覚まし震えながら見守る夫の前で始まった。
啓介は堪らなくなりファスナーを開け、自身を取り出していた。
課長が用意してくれたオカズで絞り出そうとして、目の前に晒された妙な形をした皺袋に目が留まった。
毛むくじゃらの体躯から生えている棹はごく普通の大きさなのに、根っこにぶら下がるはずの皺袋だけが棹にぶら下がるにしてはやけに大きかく、まるで巨大な茄子と先端のヘタのようにも見える、
しかもその皺袋ときたら、目の前の人妻が何かをしでかすたびにグニュリと躍動、
袋の中に、明らかに注ぎ込む濁流をため込んでいる。
「ふ~~・・・ たまらんわい」
唸り声に反応するかのように棹の怒張が始まりキツキツの妻では受けきれないほどに腫れ上がった。
先端が張り詰めもはや常識では考えられぬほど黒ずみ、握りの部分には血管がクッキリと浮き出て反り返りを繰り返している。
「こいつを挿し込んで・・・泣かせたいもんじゃのう・・・ むむ グッ う~む ふふ」
唸りながらも執拗にカメラを回し続ける長瀬に、いつしか啓介は妻を預けてその様子を盗み見したい気分に駆られていた。
偶然が重なり、仕方なかった妻の不貞。しかしそれが度重なると、競い合うためなのか男は必ず告げ口をする。
冴の夫、啓介の場合もそうだった。
新藤一家は晩夏のある日、この長瀬課長が教えてくれた渓流でキャンプを計画した。
「なっ、俺の言った通りだろう」
「信じらんない・・・こんな場所で自由にBBQなんかしていいの?」
長瀬が渡してくれた、まるで有名写真家が撮ったような渓流写真に、ただただ妻の冴は喜んだ。
子供ふたりを連れてBBQ体験をしながら、日頃の疲れをいやすつもりだった。
計画をしたのはもちろん夫の啓介の方だったが、家事を手抜きできるとあって冴も渋々合意した。
それというのも、計画は確かに夫の啓介がしたが、
準備は決まって冴の手にゆだねられた。
家の中の、どこに何が仕舞ってあるのかさえ 外で働く啓介は頓着しない。
子供が生まれてこの方、
冴はいつも置いてけぼり、
この夏だって、家事に追われ買い物以外何処にも出かけることなどできなかった。
冴は確かに苛立っていた。
家計を支える収入のほとんどを、冴は実家からの仕送りで賄っていた。
悪いと知りながら、夫の啓介には辛く当たった。
互いの反発は、次第にレスを常態化させていた。