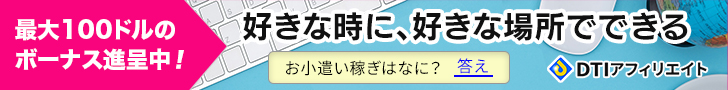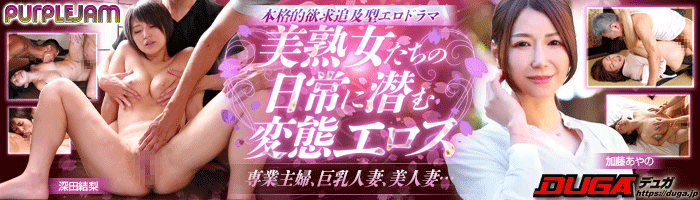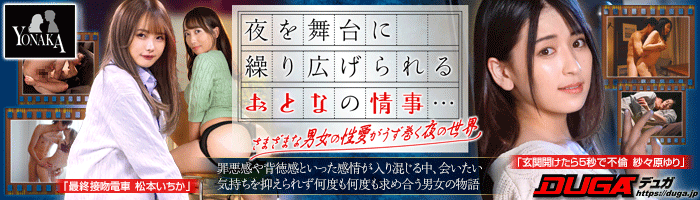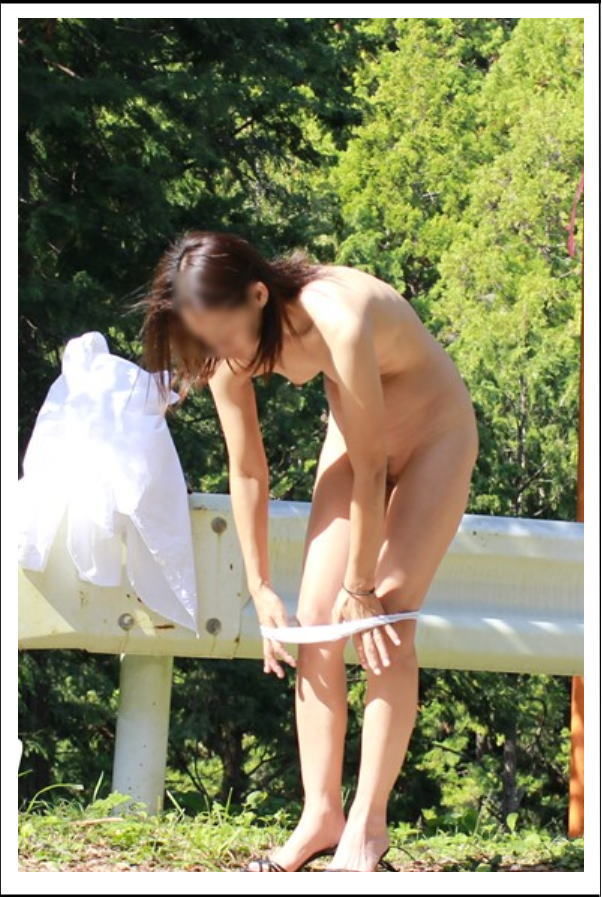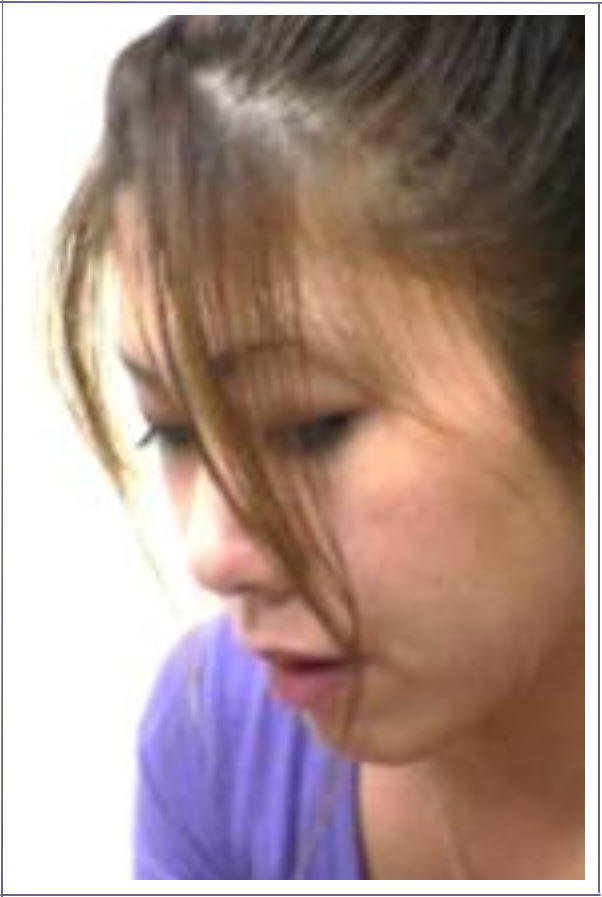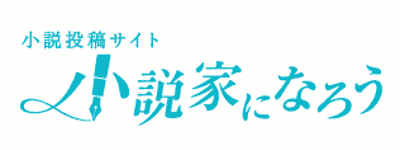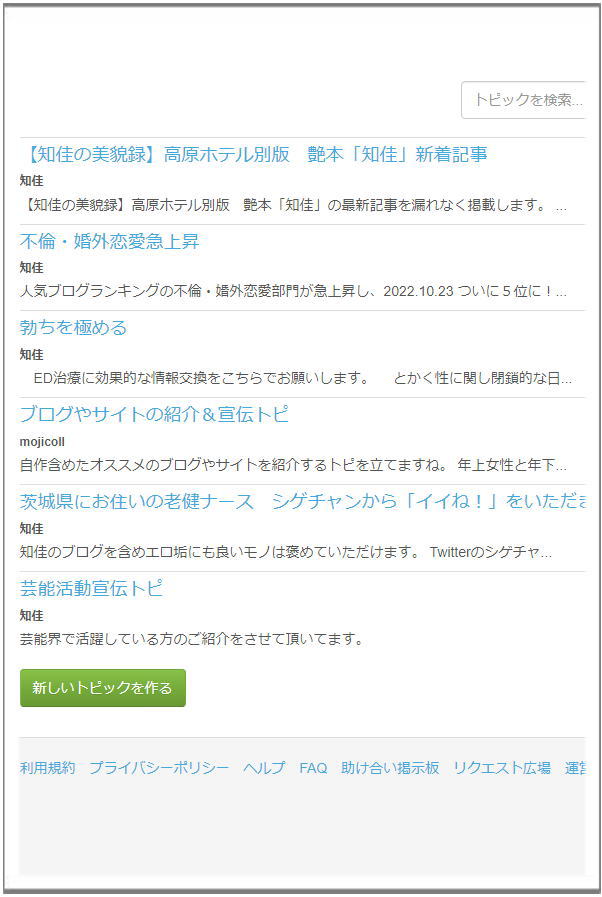【シェアハウスのように】 有閑マダムのご乱交
 芙由美の朝は遅い。
芙由美の朝は遅い。薄明かりの中、夫の了が会社に出かける支度をしているような音が聞こえたことだけはうっすらと覚えている。
「んとにもう。 毎朝毎朝うるさいんだから」
聞こえよがしに罵声を浴びせたが、
芙由美の枕元には了が用意してくれた朝食が何時ものように置いてあった。
「朝からこんなに食べれるわけないジャン、何考えてんだか・・・」
愚痴をこぼすも睡魔に負け、再び寝入って、
次に目を覚ましたのは10時を少し回っていた。
「あら大変!! 約束していたランチに遅れちゃう」
了が用意してくれていた朝食をゴミ袋に叩き込むとシャワーを浴び化粧をはじめた。
「いやだわ、今日何着ていくか決めてなかったんだっけ」
女子会よろしく彼女らは互いに相手を紹介し合うことになっていて、今日は芙由美のために紹介となっていた。
初めて遭う彼のために魅せる下着を決めていなくて焦りを覚え、
姿見の前であれやこれやと 迫りくる時間に追われつつもとっかえひっかえ履き比べていた。
決め手は2か所、
ヘアの魅せ具合とマンスジあたりの透け具合。
それで勃起を呼び起こし、嫌われないうちに目的を果たすというもの。
紹介してくれた彼女の説明ではアンダーは濃い目が好きだと言った。
芙由美はその部分だけは自信が有り余るほどあった。
負けん気の強い芙由美は体毛がどちらかというと濃い、処理を怠ればマンスジが隠れて見えないほどに。
エステに通ってレーザーで全身脱毛をやって、
アンダーも理想の形に整えてもらってある。
その卑猥な様子が薄い布越しに見え隠れしなければ意味がないとエステでその道のプロに教わっていた。

散々悩んだ末に彼女が選んだのはスケルトンのパンティー。
股上が浅く僅かにヘアがラインの上から覗き、それでいてワレメも魅せることができるタイプ。
セフレゲットの勝負用としていつか使おうと、
夫の了には内緒で女子会で彼を紹介してくれる話が出たついでにネットも教えてもらい手に入れ、
機会が訪れるのを待って伸びに伸び 今日に至っていた。
芙由美はある意味で待ちきれなくなっていた。
夫婦といえば何事につけ許された仲、
それを良いことに了は家庭にまで仕事の話を、たとえ食事中であってもベッドでも持ち込んだ。
これといって趣味のない了にとって仕事の話しだけは人に負けないほど話せたから自慢だったかもしれないが、
芙由美は聴くだけで気の利いた返答が出来ない。
すると決まって夫の了は「そんなことも知らなかったのか」
という風な顔をしてそっぽを向いた。
自然会話がなくなっていった。
死ぬほど懸命に働き、給料を持って帰る夫、
死ぬほど退屈な時間を自宅で過ごし給料を待つ妻。
先に我慢が出来なくなったのは妻の芙由美の方だった。
人との関わりを持たなくなった芙由美はとかく孤立した。
誰でもいいからこの締め切った開かずの間から引っ張り出してほしいと、叶わぬまでも願っていた。
そんな鬱に近い状態になっているときに声をかけてくれたのが、
今回彼を紹介してくれるという女子会のメンバーだった。

知り合いでもないのにいきなり街で芙由美に声をかけてきた彼女たち、
実は人ごみの中で次回企画しようとしていた3Pメンバーの女性を探しているところだったのだが・・・
そこに偶然通りかかった芙由美をメンバーのひとり、雪乃が、
「ねえ、あそこ! あそこを歩いてる女って動画で見た堕胎の例の女じゃない」
偶然は重なる。 見つけてくれたのが芙由美にとって穏やかならざる日。
久しぶりに夫の帰りを寝ずに待つ日が続き、
意を決して昨夜、夫の了をベッドにそれとなく誘ったが、(結婚してしばらくしたころからベッドは別にしていた)
誘ったその時間帯が午前を回っており 「明日があるから」
疲れが出ないうちに寝たいと言われ
「何かといえば仕事仕事って!! どうせ私なんか家政婦ぐらいにしか思ってないんでしょ」
諦めの言葉は口にしたが身体は治まりがつかなく眠れないでいて、
わざと部屋の中をバタバタ歩き回っていた。
すると、寝ていた筈の了が起き上がり、こういったものだ。
「子供もいないんだから、そんなにイライラするならどこかで遊んできてもいいよ」 深夜にである。
それも外に出て誰かと寝て来いという。 自分でも半ば認めていたとはいえ使い古しのような言い方に益々イラついた。
私だってまだまだオンナ、
いつもなら近所のスーパーまで普段着のまま自転車で買い物に出るが、その日は久しぶりにめかし込んで期待を胸に出た。
そんな気持ちのままに街に繰り出したものだから3Pメンバーを探す雪乃の格好の標的となったようだった。
彼女らの業務はそれは厳しい、
丸1日中声をかけても誰ひとり見つからないときもある。
運よく見つかっても丸太棒のような女もいて、その気にさせるのも彼女らの仕事のひとつだった。
このメンバーの女性らをその気にさせる為、雪乃らは時々AV動画を仕入れている。
そのお得意先が柏木優美で、芙由美親子の動画も古いながら仕入れて新顔に魅せたばかりだったが、
これが意外に好評をよんでその日のまぐわいが盛り上がりをみせたものだった。
殊に娘を前に欲情が止まらず、挿し込んでくれた男性の棹が折れんばかりに腰を振り扱きあげるさまは、
絡みが始まる以前に既に女たちは潤沢に潤ませてしまい男どものアソコをビンビンにさせたものだった。
「次も頼むぞ!!」
勝手なことを言って雪乃の男は遊びに出かけた。
「あいよ! 任せときな」 気前よく応えたまでは良かったが皆目見当がつかなかった。
そこに飛び込んできたのが堕胎の娘 芙由美だった。
「あのヤブ医者、堕胎に使う麻酔代わりに母親のまぐわいを魅せ、興奮させ痛みを忘れさせ」
掻き出すなんて・・・柏木って本当にヤブ医者なの? 腕が立つんじゃない? 最高ね。
「こんな女が揃ってんなら私たちよりよっぽど使えるんじゃない?」
「なにしろ親が親ならって言うでしょ?」
シングルマザーに育てられ、身体を売るしかなかった新顔の女が捨て鉢に云う。
「あんたたちみたいなアバズレでもあの淑子だかっていう母親の絡みと娘の自慰魅せられ〆ってしまったほどだから」
でもね、あの女が本当に動画に出てたなら結構なご身分のはずよ、
「あまりに良かったから、次はないかって聞いてみたら無いっていうのよ」
期待しても無駄だという雪乃。
「どうせ雪乃さんのことだから半分脅しで聞いたんじゃなくて?」
「それがどうした!」 ざけんじゃないと一喝し、
地方の有力者の妻とその娘だが内密を条件にならと一部始終話してくれたという。

その話の端緒から柏木優美が倉庫の片隅から探し出してくれたのが、
不貞の味を覚えた芙由美の母淑子と、襲い割ることがなによりの趣味という男との野良のまぐわい動画、
突然襲われ逃げ惑う淑子を執拗に追い詰め、
爪を立て手当たり次第にそこらじゅうの物を取って投げ、真に迫っていた。
懸命に抵抗する淑子がついに追い詰められ押し倒されて太腿を割られ肉棒の良さを教え込まれ・・・
淑子のほうは諦めがつかず、
かといって割り込む男の良さに身体が自然と反応を始め、
声を押し殺し身悶えるというものだったが男の興奮度が勝っておりやがて逝かされぐったりする。
その人妻の始まってしまえば自然と欲望にのめり込んでしまう演技ではないところに良さが光った。
言葉では拒絶の姿勢を崩さぬまでも、
互いの絡み合う芯部のアップでは愛液まみれの肉棒が執拗に他の男の体液を襞奥から掻き出しにかかっていて、
男が奥を抉るたびに女の腹部が亀頭冠を求めてしゃくる、
乳輪は黒ずみ、乳首が固く尖って天を向いて反り返っていた。
「おばさん、久しぶりだったんじゃない? よがってる!!」
豊かな下腹部が巨大に腫れ上がった亀頭冠のワレメ入口への嬲りに待ちきれなく、耐えられなくて揺れていた。
「襲ったはずの男もおばさんが好きになったんじゃない? 急いで中田氏せずに入り口を嬲ってるもん」
3Pみたいなん向きじゃない? このおばさん。
濡れ始めたことを隠そうとして新顔が身をよじってもじもじし始め一同の笑いを誘った。
「これを魅せ付けて不貞は仕方がないこと、悪いことじゃないと教えてやれば、或いは・・・」
雪乃が取ってつけたような言い訳をしたが、むろん賛同は得られた。
本気になってまぐわうことは、たとえキャッチされた女たちとはいえ嫌いじゃなかった。
ハメ合ううちに本気シルを溢れさせてしまうことは度々ある。
母は男が欲しくて仕方がない歳だった、
女の目から見れば娘の芙由美もおそらくその血は引いていると思え、
「これを魅せたら用意した初の客のアレを喜んで咥え込む」 筈と雪乃。
口説き落としに使った場所は、
かつて芙由美の母が行きずりの男に襲われた場所が敢えて選ばれた。
計画からすればリアリティーに富んでいたからである。
小さな画面ながら雪乃はスマホに動画をダウンロードさせ当日持ち込み、
芙由美に撮影場所にいちいち立たせて魅せた。
画面が小さく、もちろん襲われている女性の顔は見えない。
それでもその雰囲気に一瞬で呑まれた。
それよりなにより、顔を合わせたばかりの女性たちからAV動画を撮影現場、リアルに富んだ状態で魅せられる、
芙由美はそのことに興奮した。 素人さんは不貞でこんな絡みをするんだとレスならでは期待を募らせた。
「紹介する彼と、こんなエッチなこと・・・ 出来る?」
無理しなくていいのよという雪乃に、
「・・・出来ると、 思います」
芙由美はきっぱりと言い切った。
夫の了が慰めてくれなく、
「外で遊んで」というからには、
シミを作ってしまうワレメを使ってくれる男にすがるしかないと思い始め、
雪乃が教えてくれたネットショップでスケルトンを求め、
サロンで全身脱毛・繁みのレーザーを済ませ、
わざわざ送ってくれた動画を観て興奮に胸を高鳴らせ、その時を待っていた。