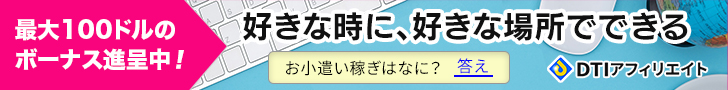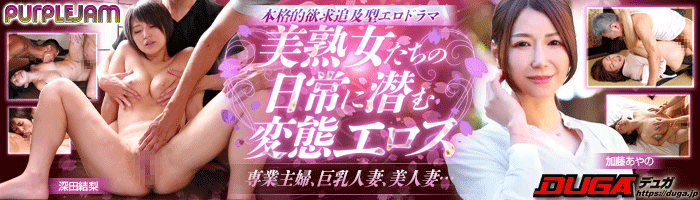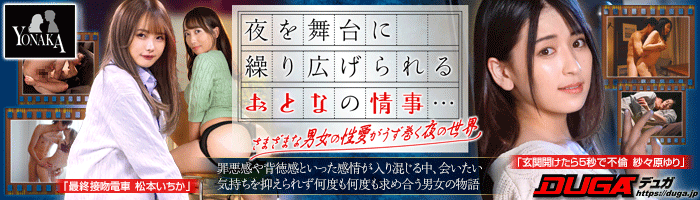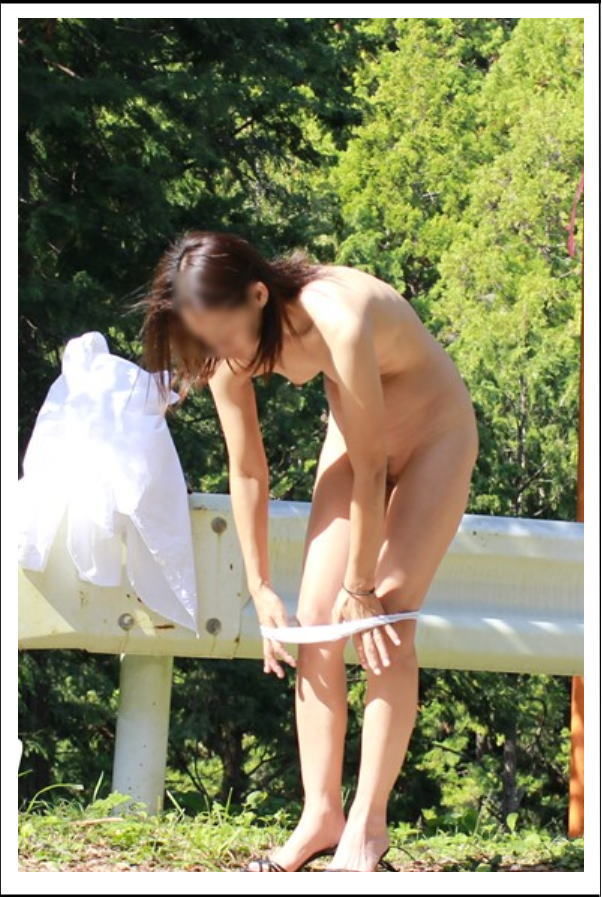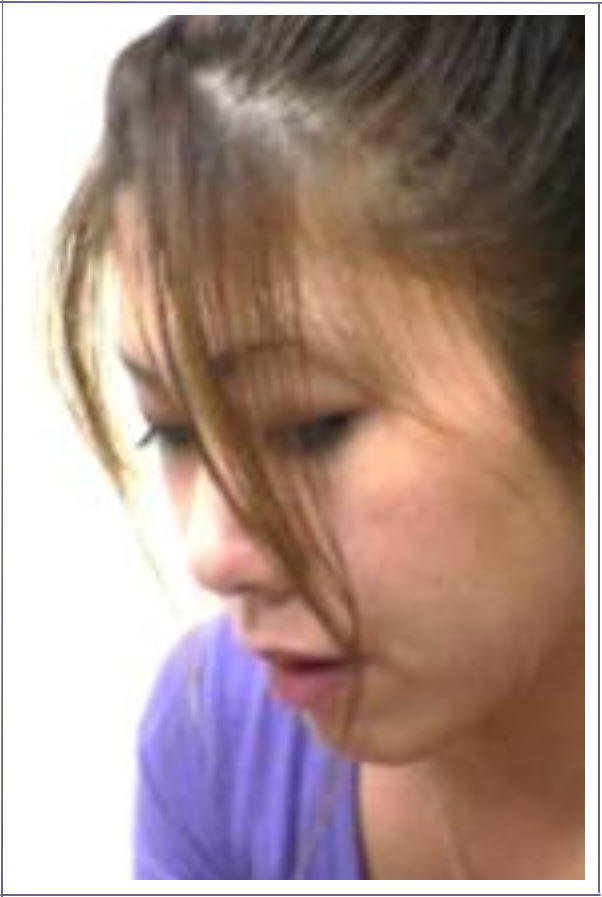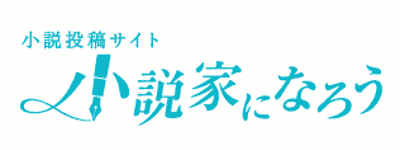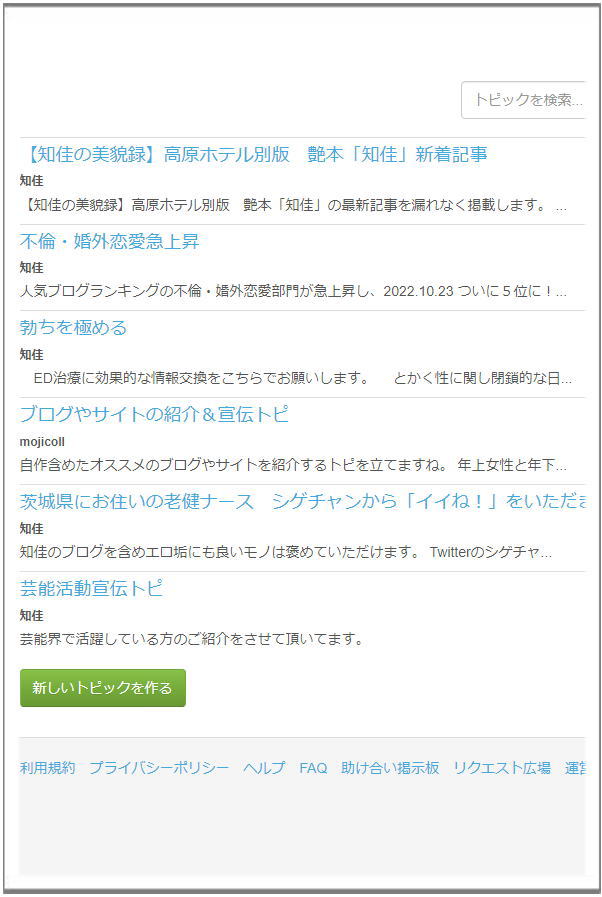疑惑 人妻おカネのモンペや腰巻に執着し始めた庄衛門は
 男と女の、このようなふしだらな行為を許せる風潮では、当時はなかった。
男と女の、このようなふしだらな行為を許せる風潮では、当時はなかった。入沢村でなくとも、男女が並んで歩いただけで厳しくとがめられた時代だった。
それ故、気持ちを伝える手段と言えば、
何かをそれとなく届けるとか、
周囲の目に触れるか触れないかの瀬戸際のところで、
相手にだけわかるよう晒すしかなかった。
おカネと庄衛門はこれを、村の若い連中が行うように秘かに行った。
妙な話だが、当時は排泄行為を、今のように完全密閉の空間で行う習慣を貧乏屋では行えなかった。
潜むように物陰に隠れて、女はしゃがむ以外になかった。
男は堂々と道端に放出するのが普通だった。
だがそれは、気になる相手からみれば、
まだ温もりのある間に嗅ぎに行き、
手で触れることが出来たなら、
「オラのために・・・」
気持ちが伝わるのである。
そこで庄衛門は、決まった場所で決まったように放出した。
それを見たおカネは、それとなく物陰に忍び込み、しゃがむのである。
その距離が次第に縮まったのは言うまでもない。
ある日庄衛門は、おカネが用を済ませて立ち上がった瞬間を見計らって、
素知らぬ顔で近づき、
湯気の上がる地面にしゃがみこんで、
今放出し終わったおカネを見上げた。
おカネは慌てた。
なにしろ、モンペの前ひもは後ろに廻して最初から結んであってよかったものの
前で結んでいた紐をほどいて、尻をまくっていたからたまらない。
焦るあまり、たくし上げようと試みたモンペの後ろが、
豊かな臀部に引っかかり、
まだシズクの垂れるアレを覆い隠せなかった。
庄衛門はそれを見逃さなかった。
「おいっ、まだシズクが垂れとるぞ!」
こういったかと思うと、
おカネの背をポンと押した。
前のめりで倒れた拍子に、おカネは四つん這いでアレを庄衛門に晒す格好になってしまった。
「どれどれ、しょうのない奴だ」
再びしゃがみこんだ庄衛門は、ぺろりとおカネのシズクを舐めとってしまった。
しまったという思いがおカネに沸き起こった。
〈 他人じゃなくなってしまう 〉
夫の甚六に知れたら・・・
そう考えただけで胆が冷えた。
地面に崩れ落ちるようにおカネは身を投げ出し、
必死で胸を押さえた。
この状態から庄衛門に押さえ込まれ、胸を開けられ、吸われたりすれば
拒絶しきる自信がなかったからである。
「恥ずかしいシルまで舐めとられた気がした・・・」
相手を、横目でにらみながらジリジリと地面を這いずって逃げようとした。
「えらい匂いがしたぞ。どうれ、儂もひとつ」
おもむろに庄衛門は前を開くと、
すっかりそそり立ってしまったアレを取り出し、
おカネの放った痕に向かって放出の姿勢をとった。
微妙な時間が流れた。
庄衛門の、充血しきったソレからは
放出しようにも路が開かなかった。
反り返りながら、懸命に力む庄衛門。
だが、滴の一滴も その先端方出てこない。
豪快な、そのさまを見せ付ければおカネも納得しやすまいか、
その考えが甘かった。
ただでさえ、おカネ欲しさに充血し放出を妨げているのに、
その狙うアレから滲み出たシルを舐めてしまっていた。
前を開く直前に褌の端で我慢汁を拭い取り、
何の変哲もないソレを晒し、力みに合わせ腰を振る
妙な格好をするだけになってしまっていた。
「おいっ、おカネ。手伝って・・・」
言いかけて脇を見ると
おカネの姿は消えていた。
おカネはおカネで、甚六に見つかってはと
懸命に水場に向かって走っていた。
「見つかる前に洗い流せねば・・・」
庄衛門の唾液で間違いが起こってしまう。
生まれて初めて男の愛撫というものを、まさかの庄衛門から受けてしまっていた。
それも、庄衛門のやることなすことに、
すっかり我を忘れシルが垂れるほどになっていたソレにである。
混乱する頭を冷やすには、
ソレごと谷川に冷水で冷やし、清める以外に方法がなかった。
尻を隠すべきモンペは後ろを開け放ったまま、転がるように走っていた。
地面にシルの一滴も垂らすまいと、前を掌で押さえつつ走った。
「庄屋が・・・庄衛門さんが・・・」
押さえた掌に生暖かいシズクが溜まるのが分かった。
「どうにか・・・せんと・・・」
しゃがみこみ、指を挿し込んでは溜まったのもを掻き出して、誰にも、殊に庄衛門に見つからぬよう秘かに枯草の柔らかい部分を使って拭い取った。
なんとか乾いたと思いきや、また立ち上がって走った。
「あんた・・・オラ・・・悪いことした」
水辺に辿り着くと、
モンペを脱ぎ捨てて水に入り、下半身を洗った。
すっかり下腹部が冷え切って、
どんなに指を挿し込んで掻き出そうとしても
ヌルミすら感じなくなるまで探った。
すっかり擦れて血が滲むほどに擦り洗った。
それを覗き見ていた庄衛門には、
おカネが庄衛門のいきり立つものを、実は欲しくて、
治まりが付かず、
指を使って感情を押し殺そうとしているように映った。
透き通るような谷川の水の中で、
すっかり上気したソレに指を挿し込んで、しゃくりあげる腰を空いた掌で抑えつつ鎮め
自身の指で興奮が治まるまで掻き回している。
そう感じた。
おカネ自身、なにがなんだかわからないまま、とにかく洗い清めた。
それでも、自宅に帰り着き、甚六と向かい合わせに坐して食事のもてなしをするときなど、
庄衛門の臭いを甚六に嗅ぎつけられはすまいかと冷や汗が出た。
正座でもしようものなら、
踵が嬲ったソレに食い込む。
すると再び庄衛門の舌の、唇の感触が甦って濡れた。
甚六の手前、もてなしが忙しく、正座もできないという風に装いはしたが・・・
〈 オラを欲しがってた。押さえ込まれる 〉
これまでのように、気安く近寄れば、きっと犯される。
そう思う先から濡れた。
「あん人も、オラのこと・・・だのにオラは・・・どうしたらええだか」
腰巻のその部分は、もう危ういほどに湿っていた。
モンペを通して、腰巻の中が危うい状態になっていることを、
甚六に悟られはすまいかとヒヤヒヤしながら給仕を済ませた。
庄衛門から逃げ延びながら、いつのまにか身体が庄衛門を受け入れようと蠢いていることに気づいた。
甚六は食事を終えると昼間の疲れが出たのか、
その場で横になり、鼾をかき始めた。
その隙に、おカネは外に出て裏に回り、モンペを下にずらし腰巻を脱いだ。
替えの腰巻を履くまでの間、モンペに下はスッポンポンだが、
腰巻の濡れがモンペを通して透けて見えるのは何としても避けたかった。
汚れた腰巻は何気ないように汚れ物と一緒に洗い場に置いておいた。
この様子を、裏の竹やぶの中から、眼を光らせ盗み見るものがいた。
その翌日からだった。
モンペや腰巻を干しておくと、
肝心な部分に何かが付着して黄ばみ、ゴワゴワになってしまっている。
ぶっかけだった。
おカネの奥深く、渾身の思いを注ぎ込みたくて、
実は、治まりが付かなくなった庄衛門はおカネの自宅付近を連日うろついたのだが、
どうにも同意を得て押さえ込む手段と言おうか、
突破口が見当たらなかった。
だが目の前には、熟れきった人妻が立ち働いている。
板壁の隙間から覗き見ては、己の分身を擦った。
秘かに貢物を置いて「逢に来た」の合図代わりとし、立ち去ることも忘れなかった。
そうこうして見つけたおカネの、大切なまだ洗わない下着に向かって鼻面を突き付け、
胸いっぱいに香りを吸い込んだ。
吐き気がするほど肉体はおカネを欲し、その興奮ゆえの血圧上昇で後頭部が傷み、行き場を失った皺袋から飛び出せない胤の圧が前立腺を圧迫し、下腹部にも鈍痛が走る。
「あのアマめが・・・」
己のもとに屈しようとしないおカネに、焦がれるゆえの憎しみが増していく。
咄嗟に思いついたのが、ぶっかけだった。
せめて分身に向かって放出でもせねば、気が治まらなくなっていた。
このことに気が付かないおカネは、ひょっとすると付着したままの下着を、
それともとうに知っていて、秘かに身に着け楽しんでくれるかもしれないとも思った。
もしも知ったうえで身に着けてくれ、身悶えてくれることさえ分かれば、
それこそ真の気持ちを、秘かに推し量れる、またとない手段だと思ってしまい、ありったけぶっかけようとした。
たまりにたまった胤は、自身の力で寸止めすることなどできないほど勢いよく飛び出しきった。
射出の瞬間、全身に鳥肌が立つほどゾッとするような快感が駆け巡った。
「ふふっ、この勢いのあるモノをアソコが受け入れたなら、間違いなく惑乱するはず」
妄想の中で、おカネが何度も欲しがり、よがり声をあげしがみつく。
「ええ具合なアレじゃった。儂のを挿し込むとキツキツじゃった風に見えたでのう」
やっとのことで萎えたオノレをズボンの、褌の中にしまった。
帰り際、おカネの家の、いつもの庭先で、おカネがかつて喜んだ臭い付けを試みると、膀胱が空になるほど放出できた。
庄衛門の頭上に幸運が、一気に舞い降り、おカネと間もなく結ばれるような気がしてならなかった。
初手は妙だな、〈 ひょっとしたら月のものでも着いていたことがくがわからず洗濯を 〉、が、どんなに考えても思い当たるふしがなかったし、生まれてこの方見たことも聞いたこともなかったので頓着しなかった。
貧乏暇なしというが、のんびり洗濯をしている暇などない。
洗いあげたはずの腰巻の、アソコに触れる部分が妙に、多少ゴワゴワするけれど、〈 生地が傷んでいたところに太陽さんの照り返しが当たったものだから 〉そう思って、おカネはそのままの状態でいつもの通り身に着けた。
働き出すと、もうその忙しさに気が紛れてしまったが、その間にもアソコは汗蒸し、じんわりとゴワゴワがその汗様のモノで元の射出された時の形に戻り始め、おカネの女のオンナの部分を刺激し始めていた。
身に着けて働き出し、おおよそ小半時も過ぎたころ、妙にアソコが火照り、湿るのに気がした。
それに加え、胸元からなにやら人恋しい臭いが立ち上って鼻腔をついた。
その匂いをかすかに感じるたびに、風邪を引いたわけでもあるまいに頬が火照った。
そして、何位に反応してか、しっとりと、さらに一層アソコが潤みを帯び始めている。
おカネの放ったシルの刺激に耐えかね、庄衛門が洗濯を終え干していたおカネの下着に残していった胤に、おカネのオンナが反応し始めているとは・・・おカネこそ、どこか懐かしい香りだと感じてはいたが、さすがにそれが庄衛門の胤だとは思い浮かばなかった。
甚六から日頃、お情けを受けていなかったから、胤の、卑猥な気持ちにさせられた時に滲み出るシルとの混合臭いをすっかり忘れ、己の身体の、男への変化に気づかなかったのである。
庄衛門が秘かに忍び込んで、おカネに向かってまぐわいたい合図を、胤を擦り付けるという卑怯な手段でよこした。それが秘かにおカネの下腹部付近を通して実を結んだのである。
おカネは、甚六に気づかれないよう作業の合間に、付近の野で手に入れた柔らかそうな枯草を使って、用を足すように見せかけながら、とにかくこまめにシメリを拭き取った。
「オラとしたことが、漆にでもかぶれたか・・・」
恥ずかしさでいっぱいになった。
「あぁイライラする、妙な臭いに乳まで張りよるわ」
さては先だって冷水につかりながら、指で擦りすぎたんではあるまいかと、しゃがんだ時に中を覗き見たりもした。
「あれ嫌だ。拭いたばかりというに、まだ出てきよる」
だがそれが、甚六の、何とも言えない不可解な行動で、その原因を知ることになる。
いつぞや、秋野法然まつりの宿になった、あの家の奥の間で呆れたことにまぐわい合っていた男女から発散されていた臭い・・・
それが今、女房のおカネの身体から発せられている。
ねめつけるように甚六はおカネの御居処を見て回った。
寝床に入ってからも、時々布団を持ち上げて、中から香り来る臭いのもとを探った。
そうしてとうとう、ある夜のこと、甚六がたまりかね
おカネの臭いがする部分に手を伸ばしてきたのである。
その時になって初めて、おカネはゴワゴワしていたものが何か、思いついたが、知らん顔でその場は通した。
添い遂げて初めて、我が女房のソレの様子がすっかり変わり果てていることに気づいた甚六。
下手に疑えば、せっかく嫁いできてくれた女房を手元から解き放つことにもなると、
己の中に沸き起こる悩乱に、わざと背を向け、素知らぬ顔をする哀れな甚六は、
ここで我妻を取り戻さねばという焦りから、尚更のこと委縮してしまっていた。
寝ぼけた拍子に触ったように見せかける甚六だったが、身に覚えのあるおカネは、それだけで身体を固くしてその場から逃げようとし、寝返りを打って夫に背を向けた。
夫婦は、息をひそめ背を向けながら夜の明けるのを待つようになっていった。
本人は気づかないようなふりをしていようとも、
庄衛門がおカネの衣服に浸み込ませたゴワゴワするものから発散される淫臭いという、
下腹部がもたらす温もりとシルで溶け出し、開いた胸元から立ち上る、或いはシル同士が交じり合い醸し出す粘りというものの刺激に
女としての本能からか、たとえそれが洗濯物に付着させただけの胤であっても性で感じてしまい、焦がれた男に対し、その懐かしさのあまり、身体の芯からごく自然に潤みが生じているのは確かだったからであった。
- 関連記事
-
- 嬲り合い
- 疑惑 人妻おカネのモンペや腰巻に執着し始めた庄衛門は
- 疑惑 庄衛門の言付け