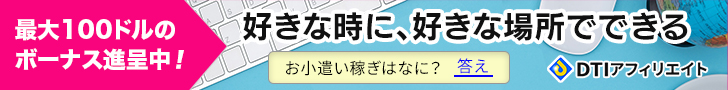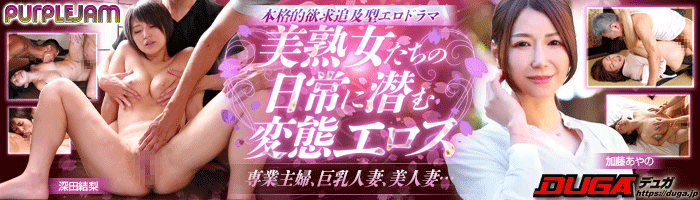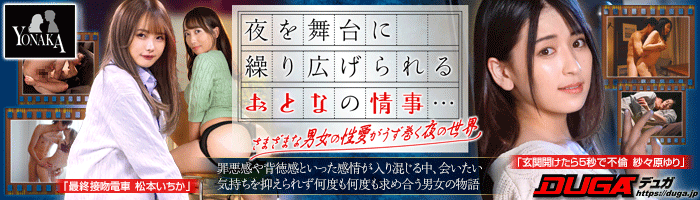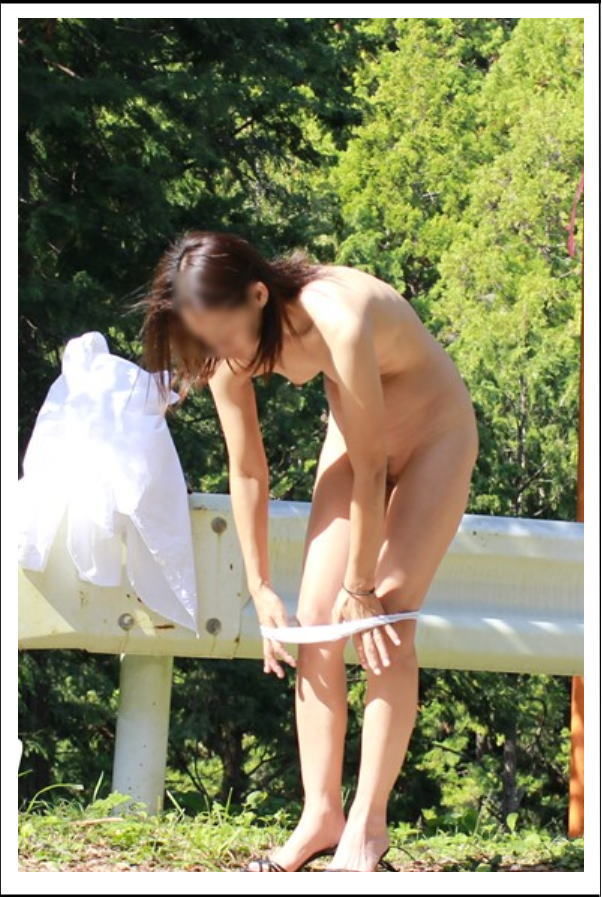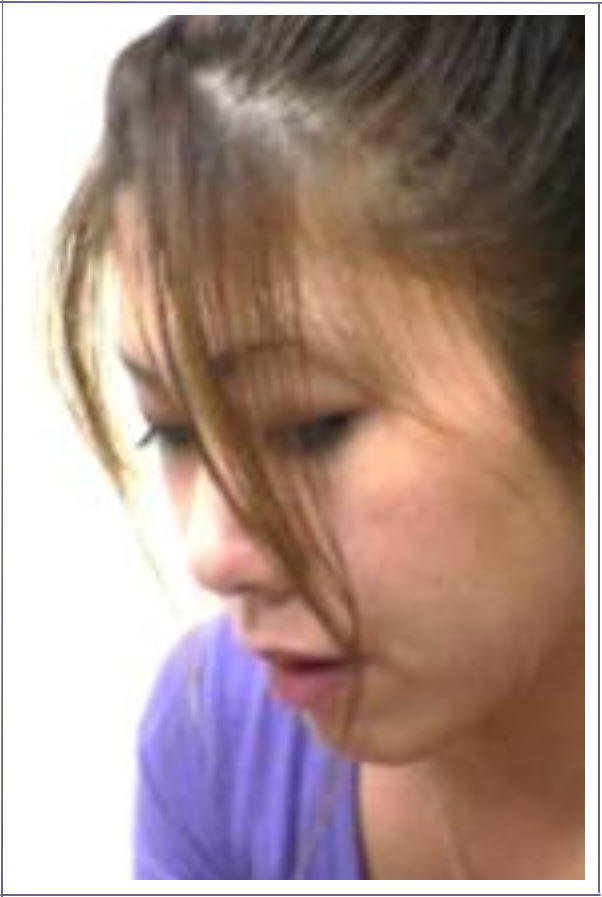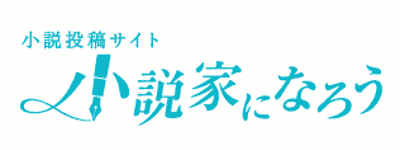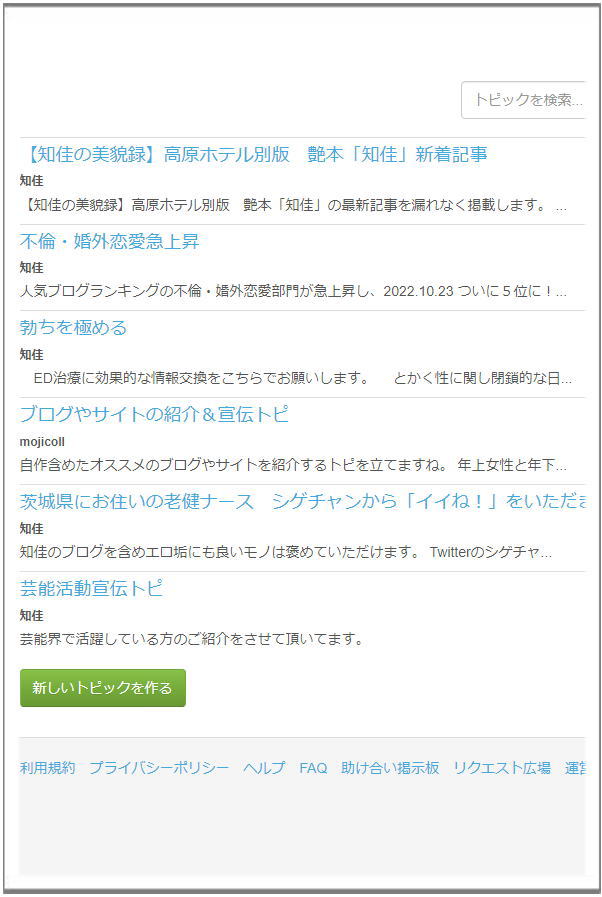敦子と清美は見抜いた 視姦で雄々しくさせてやれば底なしに厭らしさが増してくると
 恭介は気づいていなかった。
恭介は気づいていなかった。フル勃起しているとはいえ、清美の深部を突くには恭介の棹は短すぎた。
深部を突いていると勘違いをしていた。
なぜにこれほどまで勃起したかというと、清美の体格が弥生に比べダイナミックで、例えばワレメなど弥生なら広げたところで中は見えないが清美のそれはバックリ割れ、丸見えになる。
尻も豊かなら、乳房など恭介の顔がそのまま埋まるほどに豊かで張りがあった。
恭介の逸物を清美のワレメに出し入れしていると、ともすれば陰嚢までワレメの中に埋まるほど大きく開いており、それを その包みこみを先端が深部まで届いたと勘違いしていたふしがある。
敦子はというと、弥生に比べ表現が上手かった。
恭介が欲しいという気持ちを素直に表現したし、積極的な行動にも、何のためらいもなく移した。
例えて言うなら自宅で妻を抱くよりピンサロで周囲が異様な雰囲気に包まれる中、露わな女の子と卑猥な行為にふける方が興奮しやすいと言った程度だろう。 見栄えでフル勃起させたのである。
それほどに、恭介自体 女性経験は少なく ましてや孕ます楽しみなど必要ではなかったのである。
清美にしてもそうで、これほど夢中になってくれる男性にこれまで巡り合ったことはなかった。
デリで客から味気ないとまで言われたことならごまんとあるほど、日本人としては見栄えは良くても中はゆる過ぎた。
恭介はそんな清美を必死で突きまくっていたのである。
実は、恭介の切っ先は先ほどから清美のGスポットを子宮頚部と勘違いして突いていた。 胤だの孕むだのの段階ではない。
だから、突き損ねると愛液で滑った亀頭はワレメから弾き出た。
興奮し切っている恭介はそれとは知らず壺口すら子宮を突き破るがごとく勢いで切っ先で何度も割った。女に狂っていた。
恭介とそれほど違わない体格の清美が、上から責める男の雄々しさに完全に屈しているさまは敦子にも興奮として伝わった。
敦子は狂いまくる恭介を見ていて、ひょっとして清美とふたりで企てた完熟婦人を相手の乱交も、自分たちが恭介に対し火付け役を演じれば出来はすまいかと思うようになっていった。
「・・・・・あっ、イっく・・」
遮二無二何度も突きまくられた清美の息がついに止まり、興奮のあまり伸ばした手が宙を仰いだ。
完全に逝ったのを見て敦子は清美と入れ替わった。
清美の枕元で恭介に向かって広げて見せつけていたワレメを、清美が逝ったのを見届けると清美を跨いで迫り、恭介の鼻先に押し付けた。
「みせつけられてこんなになったんだから、なんとかしてよね」太腿にクッキリと愛液が流れ落ちるさまがみえる。陰唇はとっくに脇にどけ、ワレメが開ききってグニャリと蠢いていた。興奮が常軌を逸脱しているさまが見て取れた。
ベッドの上に立ち上がらせると、恭介にしがみつき、まだ大きくなったままの男根を掴んで手の中で扱いた。
恭介が尻を鷲掴みにして引き寄せるのに合わせ、切っ先を蜜壺にあてがった。
するりと敦子の中に棹が滑り込んだ瞬間には、もう敦子の中を掻き回しはじめていた。
雄々しかった。思った通りだった。
恭介に対しては壺の襞と棹が触れ合い醸し出す情欲の肉感で雄々しくなり胤をつけたくなるのではない。
視姦で雄々しくさせてやれば底なしに厭らしさが増してくる、いわゆる卑猥・妄想タイプのようだった。
恭介が懸命にワレメを突いていくれている間中、敦子は乳房を見せびらかしながら乳首を恭介の胸に触れさせ、耳たぶに熱い吐息を吹きかけ、わざとらしい喘ぎ声を聞かせてやった。
敦子の演技が増すごとに恭介の身体が何度もヒクつき始めた。
放精の予感がした。
敦子はここぞとばかりに手を伸ばし、またもや根元を握って射出を止めた。
清美ほどではないものの、敦子もまたモデルタイプのすらりとした身体つきをしていた。
見栄えだけは良い、だが顧客からは大味だと皮肉を込めて言われ続けている。
それだけに清美も敦子も、実のところ男には餓えていた。
恭介の放精を許したら、恐らく今日は二度とふたりとも抱いてもらえない。
出来る限り先延ばしして満足させてもらわなければ、恭介を苦労して探し当てた甲斐がなかった。
寸止めさせてしまった男根を丁寧に手のひらで包みながら恭介の唇を奪っていると、気が付いた清美が起き上がり後ろから恭介の尻に舌を這わせ始めた。
清美は恭介の足の間に潜り込むと舌はそのまま蟻の門渡りをなぞりはじめた。
寸止めで萎えはじめたと思われた男根が、それで蘇った。
亀頭が盛んに敦子の腹部を突く。早く挿し込みたいと先端から涙を流しながら。
清美は恭介の亀頭冠を口に含むと先端から流れ出る液を舐め取った。
そうしておいて敦子のワレメにそっと切っ先をあてがった。
後ろに回って肌をピタッと擦り付けると皺袋をギュッと握って精液を増殖させつつ放精をあおった。
ふたりの女の間に板挟みされ忘我の域に達し、敦子の肉球に絞られた亀頭冠の先端からついに濁流がしぶいた。
前後から女に挟まれ、放精が終わっても引き抜くことができない男根、その膣壁との隙間から白濁した液が僅かに流れたが、多くは敦子の体内に吸収された。
胤をつけない主義の恭介が、たまたま今日は予定日ではなかったにしても、まさかの敦子に向かって胤をつけるようなまねをした瞬間だった。
敦子はしめたと思った。
これで恭介を自分たちの計画に巻き込む理由ができたとほくそ笑んだ。
ポチッとお願い 知佳


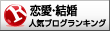
恋愛・結婚ランキング
google51904d4c43421b58.html